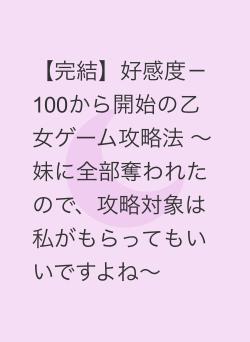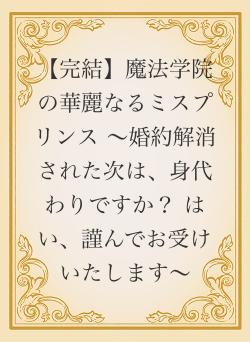ドンドン、ドンドン。
ウェンディは朝、若干強めなノックの音で目を覚ました。重い瞼を擦りながら、身体を起こす。書斎の机に突っ伏したまま眠っていたため、首と肩がひどく凝っていた。
「いたた……。朝?」
凝った筋肉を解すように首や腕を回しながら窓の外を見ると、眩しい光が入ってきて目を眇めた。そんなことをしている間も、ひっきりなしに扉が叩かれて、「ウェンディ様!」と呼ぶ声がする。どうぞ、と入室の許可をすれば、怒った様子のアーデルが入室した。
「ウェンディ様! また書斎でお眠りになったんですか!? 家庭教師の先生がとっくにいらしてます!」
「えっ嘘……もうそんな時間!?」
チェストの上の置時計を確認すると、10時を回っていた。王子妃教育のために、とある夫人を家庭教師として招いているのだが、予定まであと30分しかない。昨夜は、週末の朗読会のために原稿を書いていて夜更かししてしまったのだ。
(生活習慣の乱れは本気でなんとかしないと……)
……と、毎度毎度反省だけはするウェンディである。身支度をするために書斎を飛び出して廊下を走っていると、イーサンに遭遇した。
「イーサン様……! おはようございます!」
「おはよう。ウェンディ」
爽やかな笑顔を浮かべる彼に、アーデルが後方から苦言を呈す。
「イーサン様からもウェンディ様におっしゃってください! 寝るときは寝室にお戻りになり、規則正しい生活を心がけるようにと……!」
「はは、ウェンディ。また書斎に篭っていたのか?」
アーデルの話を聞き、こちらに尋ねてくる彼。
「つい……夢中になって」
「そう。夢中になれることがあるのは、とてもいいことだね」
にこにこと笑うだけのイーサンに、アーデルは「ウェンディ様を甘やかしすぎです」と叱るのだった。イーサンはとにかくウェンディに寛大というか――甘い。何をしてもいいよいいよと笑って許してくれる。彼は懐から本を取り出し、おもむろに差し出した。
「はい。――これ」
「えっ、もう読んでくだささったんですか!?」
「うん」
実は昨日、新刊を一冊イーサンに貸していた。上流貴族を主役にしているため、王族の生活に詳しい彼に感想を聞いてみたかったのだ。まだ1晩しか経っていないのにもう目を通してくれたらしい。かなりの速読だ。
「…………そ、それで、感想は……」
ごくりと息を飲むウェンディ。彼はにっこりと笑みを浮かべたまま言った。
「とても面白かったよ。心理描写が繊細で感動したし、脇役の侍女のキャラクターが良い味を出してたよ。でも、あなたが助言が欲しいと言ったから、気になったところにいくつか付箋を付けておいた」
返却された本には、いくつか印が付けられている。そこには、設定の矛盾点や違和感が指摘してあった。それは、普通の校正や校閲では分からない、上流階級だからこそ分かるものだった。
「わ……これ、とても参考になります!」
「よかった。作品作りに役に立つならいくらでも僕を使って」
「いいんですか!?」
「うん」
こんなに熱心に読み込んでくれて、アドバイスまでしてくれるとは思わなかった。
すると、彼の手が伸びてきて、そっと頬に指先が触れた。
「……な、なんですか?」
「髪、食べてるよ」
唇に入っていた髪の束を抜いてくれたのだ。寝起きのままで髪はボサボサ。みっともない姿を見せたことが恥ずかしくなって、頬が赤くなる。それに、彼に触れられたところがやけに熱い。俯きがちに立ち止まるウェンディ。
「ウェンディ様! お急ぎください!」
「あっ、は、はい!」
アーデルに急かされてようやく我に返り、自室に戻った。
◇◇◇
慌てて身支度を整えて、客室に行く。
「遅れて申し訳ありません! 寝坊しました!」
「遅刻ですわ。全く。礼儀のないレディーだこと」
家庭教師、リズベット・ビアラスはわざとらしく怒った表情を浮かべ、腕を組んで言った。
「う……ごめん、本当に」
「どうせまた、朝まで小説を書いていたのでしょう? わたくしじゃなかったら本当に怒って帰宅していたかもしれませんわよ」
「おっしゃる通りで……」
なぜ親友の彼女が王子妃教育を任されているかというと、彼女は幼いころから侯爵夫人になるべく厳しい教育を施されており、今では男の子の母親をしながら、若い令嬢のマナー講師をしている。家庭教師を選ぶなら、気の置けない相手がよいだろうというイーサンの提案の元、彼女に依頼したのだ。
(……私が本に夢中になっている間に、周りの人たちは普通に恋愛したり家庭に入ったりしたんだよね)
リズベットだけではない。ウェンディと歳の近い友人たちは皆結婚して子育てを始めていたが、ウェンディは好きなことがやれて満足していた。まぁ、おかげで恋愛経験0の痛い引きこもり女として振られたのだけれど。
ウェンディは社交の場に出た経験がろくになく、ダンスは下手、礼儀作法も身についていない状態。
姿勢矯正のために本の山を頭に乗せられて歩くウェンディに、リズベットが横から言った。
「年下の王子様とは案外よくやってるみたいじゃない?」
「……イーサン様って、すごく寛大なの。私に素敵な書斎や読み切れない本を与えて、好きに過ごしていいっておっしゃるのよ? それに……今まで経験したことがないくらいに甘やかされてて」
「何、もしかして惚れた?」
「そ、そんなんじゃ……」
かっと顔が赤くなるウェンディ。
今朝、唇に入っていた髪を取り除いてくれたことを思い出す。イーサンはいつも、そういう細やかな気遣いをしてくれる。
それにこれまでは、文章を書いていると家族や元婚約者が咎めてきたが、イーサンは「精が出るね」とむしろ褒めてくれた。
「へぇ……至れり尽くせりね。イーサン様、もしかしてあなたのファンだったりして」
「うーん……それはナイ」
なぜならウェンディは、著作『嫌われ者の王子様』で名誉毀損を訴えられ、その罰でイーサンの仮の妻になってしまったのだから。
むしろ彼は、ウェンディの本が好きではないはずだ。
「それで、最近第1王子殿下とはどうなの? あれから話はした?」
「ううん。特には」
エリファレットは、ウェンディにとって思い入れのあるたったひとりの男性ファン『ノーブルプリンスマン』だ。イーサンとの結婚が成立した直後に求婚され、それ以降話していないし会ってもいない。
休日の朗読会に以前はよく通ってくれていたけれど、今は全くで。
「……そう。まぁお互い、以前のように気軽に話せる立場ではありませんよね」
ウェンディもエリファレットのことが気がかりだったが、立場上会いたいとは言えなくなってしまったのだった。
頭の上に乗せていた本の山がずり落ちて床に落ちる。それを拾い上げて、小さく息を吐いた。