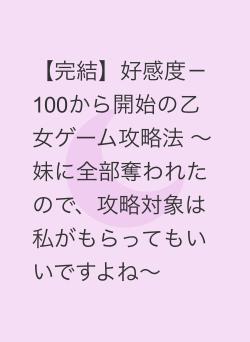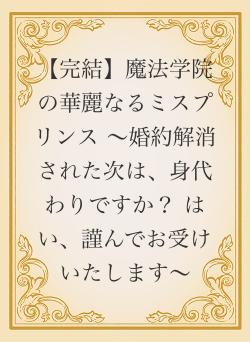「ウェンディ先生、今日も面白かったです!」
「ありがとうございます……!」
「続きも楽しみにしてますね!」
「はい……! ぜひ」
休日の朗読会終わり。女性客が帰っていき、ウェンディはほっと息をついた。今日はこの後、イーサンと買い物に行く約束をしている。――いわゆるデートだ。
キャラメルカラーのドレスワンピースに、後ろで編み込んだ長い髪。今日はいつもよりお洒落をして来ている。待ち合わせの場所の近くのショーウィンドウに映る自分の姿を確認する。
(……変じゃ、ないかな?)
家の方針により婚約者はいたものの、恋愛経験0のウェンディにとって、異性とデートは初めてのこと。そわそわした心を鎮めようと胸に手を当てて、深呼吸を繰り返す。
「ねえ見て? あの人かっこいい……!」
「本当だ。王子様みたい」
「声かけてみる?」
「あれだけ素敵なんだもの。きっと誰か素敵な恋人がいるわ」
集合場所の時計台の前で、ひとり明らかに異彩を放っている美丈夫がいた。ジャケットにスラックスといった簡素な装いでありながら、華やかなオーラは少しも損なわれていない。金髪に緑目の彼は、『王子様みたい』ではなく正真正銘の第3王子、イーサン・ベルジュタムその人だ。
(うわ……行きづらい)
人々の注目を集めている美男子の待ち人であれば、ウェンディは値踏みの対象になるだろう。その場に立ち尽くしていると、イーサンは人混みの中でも目ざとくウェンディを発見し、こちらに駆け寄って来た。
「こんにちは。ウェンディ」
「……こ、こんにちは」
朝食ぶりの再会だった。まるで後光が差しているかのような煌めく笑顔に、ウェンディは目を眇めて1歩後退する。イーサンはすでにどこかで買い物をしていたようで、紙の包みを片手に抱えていた。
「何かお買い物をされたんですか?」
「うん。本屋でね」
「本ですか! どんな本をお買いに!?」
「小説……かな」
「推理ですか!? 歴史ですか、それとも――恋愛だったり!?」
つい気になり、前のめりになりながら尋ねると、今度は彼の方が困惑して1歩後ろに下がる。鼻息を荒くさせて迫るウェンディの額を指でつんと弾き、「内緒」と優美に微笑んだ。
「好きな作家さんがいるんだ。……その人の新刊は絶対に3冊買うようにしてる」
「3冊、ですか?」
「読む用と保管用、布教用に」
「ふ。なるほど。好きなものがあるのは素敵なことです」
よほどその作家のことが好きなのだろうと理解した。最近ウェンディも新刊を出したのだが、まぁまかり間違っても彼が自分の作品を買うことはないだろう。イーサンはウェンディの作品を恨んでいるはずだから。
目的の店は、仕立て屋だ。夜会に備えて、イーサンの馴染みの店に、対の礼服を作ってもらうことにしたのだ。
街は活気に満ちていて、人の往来が激しい。人混みに紛れ込み、イーサンと何度がはぐれそうになった。すると、彼はこちらに手を差し伸べた。
「――はい」
「その手は……なんでしょうか」
「はぐれるといけないから。手、貸して」
父親以外の異性と手を繋ぐのは初めてのことで、戸惑ってしまう。けれど、そうしている間にもすれ違う人と体のあちこちがぶつかる。しばらくためらったあと、ウェンディは思い切って手を握り返した。
(これじゃ……本物の夫婦みたい。手……あったかい)
小さいころに繋いだ父親の手とは全く違う、若い男性の手。指は長くしなやかで、でも少し節がある。ウェンディの手をすっぽりと覆ってしまうほど大きくて逞しい。どきどきと加速する脈動を感じながら、石畳を踏み歩く。
彼は歩調をこちらに合わせてくれた。
「ウェンディの手は小さいね」
「……イーサン様が大きいんです。あの……私、汗とか大丈夫ですかね。緊張して……」
「ふ。全然気にならないよ。というか多分僕の方が緊張してるし」
「え……?」
どういうことですかと聞き返すと、彼は僅かに頬を染めて「なんでもない」と目を逸らした。
仕立て屋に着く前に、ある雑貨屋が目に止まった。ガラス細工でできた美しいペンが並んでいて、思わず足を止める。青いガラスは精巧な装飾が施されていて、細部まで凝っている。上端には大きな宝石が嵌め込んであった。そのガラスペンにウェンディは一目惚れした。
(綺麗……)
気になったけれど、今日はドレスを買いに来たのだ。余計な場所で足止めしては悪いと思い、ぶんぶんと首を横に振って買いたい欲を抑え、歩みを再開する。
一本限りのデザインで、次に来たときには売れてしまっているかもしれないが、もしなくなっていたら縁がなかったということだろう。
しかし、ウェンディがガラスペンを物欲しそうに眺めていたことを、イーサンは見逃さなかった。
そして、仕立て屋に到着する。外観から高級感が漂っていて、さすがは王族御用達の店といった感じだ。恐縮しつつ従者たちとともに店内に足を踏み入れると、何人もの店員がやって来て、イーサンに恭しく挨拶した。
「夜会のためのドレスと礼服を仕立ててほしい」
「かしこまりました」
ウェンディは着るものにあまり頓着しない方だが、イーサンは流行に敏感なのかウェンディ以上に服について詳しくて、店員に的確に指示を出していた。
その間、ウェンディは着せ替え人形のようにされるがままだった。生地やレースなどの素材選びから、デザインまでイーサンは熱心に口出ししていた。
採寸を終えてソファに腰を下ろし、出してもらったオレンジジュースを飲む。宝飾品や靴を決める前に休んでいると、イーサンが一旦店を出た。しばらくして彼は帰ってきた。
「どちらに行っておられたんですか?」
「……ちょっとね。それより、少しは疲れが取れたかな?」
「はい。おかげさまで。今日は色々と親切にしていただいてありがとうございます。おかげで素敵なドレスができそうです」
「とんでもない。むしろ楽しかったよ」
イーサンは嫌味なくふっと微笑んだ。彼はテーブルに頬杖を着きながらこちらに手を伸ばし、編み込んだ髪の束をすくい上げて目を細める。
「今日の髪型、凄くいいね。デートのためにわざわざ準備してくれたの?」
「……えっと、はい」
「何それ、可愛いな。そのドレスもあなたによく似合っているよ」
ストレートに可愛いと褒められて、こそばゆい気持ちになるのと同時に顔が熱くなる。ロナウドが婚約者だったときは、髪型を変えても全く気付かないし、お洒落をしても褒められたことはなかった。しかしイーサンは、僅かな変化さえ拾ってくれる。
「……ありがとうございます。イーサン様」
◇◇◇
外出から帰ったあと、書斎で原稿に向かい合っていたらイーサンが訪れた。手ずから紅茶を用意してくれた。
「今日は疲れているだろうに、執筆作業か?」
「はい。……締切が近くて、ちょっと余裕がないので」
本当はもっと余裕を持ってスケジュールを立てていたので、散々後回しにした自分が悪いのだ。毎回計画倒れで、後悔するのがお決まりのパターンである。
「無理はしないように。何事も体が資本だから」
「お気遣いいただきありがとうございます」
イーサンは紅茶をウェンディに出し、その後も中々部屋を出て行こうとしない。何かまだ用があるのかと聞くと、彼は懐から縦長の箱を取り出して机に置いた。促されて開けてみると、中には昼間に街で一目惚れしたガラスペンが。
「どうしてこれを……」
はっとして顔を上げると、イーサンは愛想よく微笑む。
「昼間に、街で見ていたでしょ。気に入ったのかなと思って買っておいたんだ。今日のお礼だと思って受け取って」
まさかウェンディの何気ない一瞬を覚えてわざわざ買ってきてくれたなんて。
箱からガラスペンを出して、そっと掲げてみる。小さな凹凸が光を反射して、繊細な輝きを放つ。ウェンディは大事そうに胸に抱きながら笑みを浮かべた。
「ありがとうございます。大事にします……!」
「うん」
こちらを射抜く緑の双眸は、甘く、優しくて、何か大切なものを見つめるようで、ウェンディの胸の奥がくすぐられた。
初めてのデートで、ウェンディとイーサンの親睦がぐっと深まったのだった。