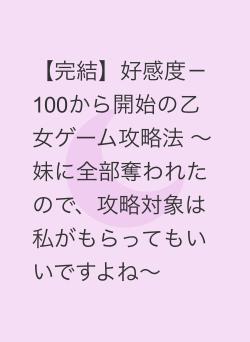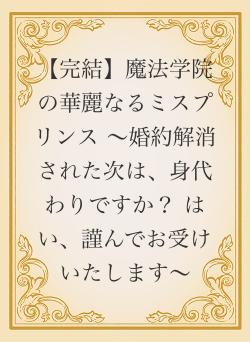イーサンの王宮内の立場は、想像以上に深刻なものだった。まずおかしいのが、使用人が2人しかいないことだ。そのうちの一人がアーデルなので、王子の世話をするのはたった1人しかいないということになる。
だから、彼は家事を自らやっていた。輿入れの日の昼。薪割りをする王子を目撃したウェンディはあんぐりと口を開けた。
「イーサン様!? 一体何をなさって……」
「見ての通り。薪割りさ」
「薪割り」
それは見たら分かるのだけれど。ウェンディが聞きたかったのは、どうして一国の王子が召使いと一緒に肉体労働に従事しているのかというところだった。王族の権威にも関わることなのに、アーデルともうひとりの召使いも、ごく普通のことのようにそれを受け入れ、一緒に汗を流しながら薪割りを手伝っていて。
イーサンは斧を持ち上げながら爽やかに言った。
「離宮は万年人手不足でね。ああ、でもあなたの手を煩わせるつもりはないから。気にせず中で休んでいて」
「さすがに気が引けます!」
薪割りをする夫を放ったらかしにして、自分だけ部屋でゆっくりするという訳にはいかないだろう。
ウェンディは髪を高いところで束ねて袖を捲り、イーサンの隣に立って「手伝います」と言った。彼は困ったように眉尻を下げる。
「全く。人がいいんだから。どこの国に薪割りをする王子妃がいるんだ?」
「薪割りをする王子様も聞いたことがありませんが」
しかし、驚いたのは薪割りだけではなかった。
薪割りを終えてすぐ、イーサンはごく自然に食堂の掃除をし始めた。ほうきを使って手際よく掃き掃除をし、テーブルを布巾で拭いていく。その様子を外の廊下から唖然と眺めながら、アーデルに尋ねる。
「イーサン様はいつも、召使いの仕事をご自分でなさっているの?」
「この離宮では当たり前の光景です。イーサン様を忌み嫌う王妃様が、召使いを減らすように采配なさっているからです。ですが、あのお方はこのような境遇でも不満ひとつおっしゃいません」
「……ずっと、冷遇に耐えてきたということ?」
「はい。――幼いときから」
もしかしたら、イーサンは自分が冷遇されることに慣れてしまっているのかもしれない。けれど初めて目の当たりにしたウェンディは困惑した。ウェンディが顔をしかめていると、アーデルはなぜかとても不安そうな様子でこちらを見ていた。
また、専属のシェフが食事を用意するということはなく、本宮での他の王族の食事の残り物が分け与えられるだけ。
それを召使2人が温めたり調理し直したりするのだ。
(これじゃ、イーサン様の面子が立たないじゃない……)
まるで、王族ではなく王宮の召使いのような扱いだ。本宮に務める召使いたちでさえ、イーサンのことを見下したような態度で食事を運んできた。応対したウェンディだが、彼女たちの嘲笑するような眼差しを向けられた瞬間、思わずスカートを握り締めていた。
夕食の席。固くなったパン。黙々と食べながらイーサンは、自分は婚外子だから、王家に対して強く発言できる立場ではないのだと苦笑した。しかし、王宮を出て自分の領地を持てば、生活も変わるはずだと付け加えて。
「……私のせいですか? 私があの小説を書いたから……」
「違うよ。僕が嫌われているのは元々だ」
「…………」
差別されているのは出自が原因だと説明する彼。王妃ルゼットが愛人の子であるイーサンを毛嫌いしていて、本宮から追い出したのが始まりだったという。エリファレットは双子でどちらもルゼットの子なのだが、2人の王子も成長期とともにイーサンを憎むようになり、いつしか、大臣から使用人まで、王宮全体がイーサンを蔑視する風潮ができあがっていた。
彼は手に持っていたパンを置き、こちらを見た。
「――嫌になった? 僕の妻になるのが」
「今更何をおっしゃいますか。私に選択権がないとおっしゃったのはイーサン様でしょう」
「……それも、そうだね。すまない」
冷遇されている様子を目の当たりにして、今後の生活に不安を抱いたのは確かだ。
選択肢はないと言ったのはイーサンだから、どうせ逃げることはできない。それに、契約の条件である執筆活動を容認してもらっている以上、ある程度のことは我慢するのが当然のことだろう。
「私の作品のせいで迫害に拍車をかけていたなら謝罪します。ごめんなさい。『嫌われ者の王子様』については、これ以上執筆しませんから」
「…………」
やけに残念そうな顔を浮かべた彼を、不思議に思った。
彼はこほんと咳払いして続ける。第3王子妃として、最初の役目があると。およそひと月後、王妃の誕生日を祝う夜会が行われる。王族はもれなくそこに参加しなければならず、イーサンは彼女に、妻を紹介するように命令されているらしい。
イーサンは子犬の耳が垂れたような、しゅんとした悲しげな様子で詫びを口にする。
「王妃様は僕を憎んでおられる。もしかしたらあなたにも辛く当たるかもしれない。……苦労をかけた、本当に悪いと思っている」
「イーサン様……」
権力を振りかざして、半ば強引に婚姻を結んできたのはイーサンなのに、どうして今更ウェンディのことを気遣うような態度ばかり取るのだろう。だったら最初から、契約結婚なんてしなければよかっただろうに。
「私たちは期間限定の契約夫婦です。十分すぎる恩恵も与えていただいてますし、イーサン様がそう負い目を感じる必要はないですよ」
「僕は、ひどいやり方であなたを妻にした。嫌われて当然のことを……」
どうしてあのときのことを今になって悔やんでいるのか理解できないが、悲しそうな顔をするイーサンが、なんだか可哀想に見えてくる。
「……そんなお顔をされたら、嫌いになれません」
ひどい人だったのは最初だけで、イーサンはずっと親切にしてくれている。また、侮辱した罰として仮の妻になったはずが、ご褒美なのではないかと疑うほどの高待遇だった。
すると直前までうじうじ悩んでいたはずの彼が、ぱっと表情を明るくさせて、こちらを見上げた。
「なら僕にも、まだ名誉を取り戻すチャンスはある?」
「……え、まぁ……努力次第で……?」
イーサンはすっかり舞い上がった様子で立ち上がり、こちらに寄って来た。じりじりと距離を詰められて、後ろに後退るウェンディ。しかし、がっしりと両手を握られ、身動きを阻まれる。
「ちょ、な、なんですか……!?」
「ありがとう、ウェンディ先生。あなたが寛大な人でよかった……! 夫として少しでも好きになってもらえるように頑張るよ」
「!?」
うっとりとした甘い顔つきで呟かれ、心臓がどきんと跳ねる。至近距離にあるイーサンの顔があまりに綺麗で、混乱してしまう。
(顔近いから……! ていうか好きになってもらえるように頑張るって何!?)
まるでそれは、ウェンディに好意があるような口ぶりだ。ウェンディはただただ、混乱とともに疑問符を頭に浮かべることしかできなかった。
◇◇◇
その夜。寝室でウェンディはイーサンのことについて考えていた。
(私は体裁を守るための仮の妻なのに、どうして親切になさるの? 理解に苦しむわ)
イーサンは、求婚のときを除いて今のところ優しくしてくれている。けれど、まだ結婚生活は始まったばかり。彼の人柄やこれまでのことなど、まだ知らないことばかりだ。
今日の出来事を頭の中で思い返していると、寝室の扉がノックされた。
扉を開くと、アーデルともうひとりの召使いが。彼女たちはウェンディが扉を開けてそうそう、額を床に擦り付けた。
「2人ともどうしたの!? 顔を上げて……!」
彼女たちは涙ながらに懇願した。
「今日一日過ごされて、もしかしたら離宮を出て行きたいと思われたかもしれません。ですがどうか、どうかウェンディ様だけはあの方を見放さないで差し上げてください!」
「ただでさえ、王宮に味方が少なく、心細い思いをされてきたお方です。私たちは気の毒なお姿をずっと傍で見て参りました。けれどあのお方にとって、ウェンディ様は必ず救いになるはずです……!」
ウェンディが何度顔を上げるように促しても、彼女たちは土下座し続けた。
「どうかここにいると約束してください。後生です……っ」
彼女たちの並々ならない姿に、よほど主人のことを慕っているのだと伝わった。そして、イーサンが長いこと相当苦労してきたことも。
「……私はまだ、イーサン様のことをよく知らないの。だから、聞かせてくれる? あの方がどんな方なのか」
すると、彼女たちは顔を上げて、イーサンのことを沢山聞かせてくれるのだった。2人の話を聞いて、イーサンが優しくて、孤独で、寂しい空っぽの王子様なのだと分かった。正直、今日の様子を見て今後の生活に不安を抱いたことは否定できない。
しかし2人の思いが伝わり、ウェンディは冷遇されることを受け入れてイーサンの妻になる決意を改めて固めた。