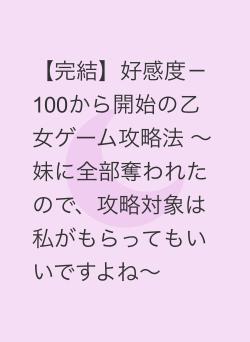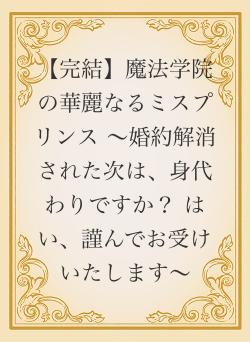第3王子を勝手に作品のモデルにして侮辱したという件について、ウェンディはひとまず、弁明を試みることにした。
「な、何かの誤解です! 私が殿下にお会いするのはこれが初めてです。よく知りもしないお相手を勝手にモデルにすることなんてできないはずです!」
そもそも、王族のような高貴な身分の方にお目にかかれるような身分ではない。
ウェンディは一代限りの成り上がり男爵令嬢。王族を含めた上流階級の集まりに、まかり間違っても足を踏み入れることはなかった。冷静に弁解をするが、イーサンの心にはちっとも響かない。
「言い訳を聞くつもりはないよ。あなたの作品のせいで僕が社交界でなんて呼ばれているか知ってる?」
「さぁ……社交界の噂には詳しくありませんので」
「――嫌われ者の王子、だよ」
「!」
それはまさに、ウェンディの作品のタイトルみたいなあだ名だった。
イーサン・ベルジュタムは、この国の第3王子だ。彼は宗教上の理由で忌避される婚外子でありながら、王族としての位を与えられているため、他の王子や王妃から反感を買っているという話は聞いたことがあった。イーサンは離宮に引きこもりがちで、社交界にほとんど出たことがないとも言われている。
彼いわく、最近では『嫌われ者の王子様』の主人公イザルのモデルはイーサンだと不名誉な噂が流れたため、より心証が悪くなったそうだ。
更に、仮に直接会ったことはなくとも、憶測だけで小説を書くことはできるだろう――という主張を押し付けてきた。加えて、『嫌われ者の王子様』のイザルと自分には共通点があると続ける。
目の前にびしっと人差し指を立てるイーサン。
「まずさ、名前が似てるよね。似た発音の組み合わせになっている。これは何か作者の意図があるとしか思えないな」
「たまたまです」
「それに、見た目もそっくりだ。長身で、金髪に緑の目の飛び抜けた美丈夫。こんなのは僕かイザルくらいしかいない」
「たまたまです。というか世界中の金髪緑目の人に謝ってください!」
「あとは、振る舞いとか言動、性格もどこか似ているし、何より――王子ってところが同じだ」
「だから、たまたまだって言ってるでしょーがっ!!」
いぶかしげな眼差しでこちらに迫ってくる彼に言い返す。
(というか、言動や性格まで似ているなら、それはもはや殿下がイザルに寄せてるんじゃないの!?)
――と、内心で思うが喉元で留める。彼はすっかりウェンディを黒だと決めつけていて、偶然の一致だと何度言っても取り付く島がない。
しかし、この作品は本当に、全てフィクションだ。イーサンとも、他の実在する人物とも一切関係がない。考えられるのは、イーサンをよく思わない人が、嘘の噂を面白おかしく吹聴しているという可能性だけだ。ウェンディはというと、イーサンのことも、『嫌われ者の王子様』のモデルに関しての噂もよく知らなかった。
「あなたは僕を侮辱した。王族を侮辱するってことは――国家に対する反逆と同義だ」
「…………」
国家反逆という言葉に、ウェンディは萎縮する。突然捕まったことに疑問を抱いていたが、ここに繋がるのか――と。
(……やっぱり、冤罪じゃない)
「私を断頭台送りにするおつもりですか?」
「そんな物騒なことはしないよ。ただね、僕はあなたの作品の風評被害に遭っている。その責任は取ってほしいってこと」
「責任……」
ウェンディはぐっと喉を鳴らした。今まで、誰かに楽しんでほしくて執筆してきた。今回の件は、自分の意思とは関係ないとはいえ、自分の作品をきっかけに彼が不愉快な思いをしたのは確かだ。悪気がなくても、誰かに迷惑をかけたら謝り責任を果たすもの。今回はただ、相手が悪かった。
覚悟を決めて、ふぅと息を吐く。
「もういいですよ。分かりました。煮るなり焼くなり、なんなりとおっしゃってください」
投げやり気味に伝えれば、彼はにこりと読めない笑顔を浮かべたまま告げた。
「じゃあ――僕の妻になって」
「…………今なんと」
「僕の妻に、王子妃になってほしい。つまり、ウェンディ先生に求婚しているってこと」
「!?」
唖然呆然とするウェンディに、イーサンが詳しい事情を説明する。今回の件で評判が落ちたことで、縁談の話が全ては白紙になってしまった。
また、王位を継がない王子は、公爵位と新たな姓を与えられ、賜姓降下して王家を出ることになっている。賜姓降下に先立って、婚姻を結んでおくのが本来の習わしだが、ウェンディのせいでそれが困難となった。
そこで、公爵位の叙爵まで体裁を守るための――仮の妻になれ、という話である。
(い、いやいや! 自分の名誉を傷つけた相手を妻に望むってどういう心理!? 怖いんだけど……)
仮の妻といえど、妻は妻だ。突然の求婚に狼狽え、一歩退く。憎んでいる相手に求婚という矛盾した行動をする彼が不気味に思えてきて、乾いた笑いを浮かべる。
「あはは、おかしな人だなぁ。何言ってるんですか。理解に苦しみますよ全く。結婚なんて無r――」
「さっき責任を取るって言ったよね? まさか、自分に選択権があるとか思ってないよね?」
「ひっ……」
無言の圧力。微笑んではいるものの、目は据わっている。
すぐにでも逃げなくてはという本能から、身じろぎして手錠を外そうと試みるが、がちゃがちゃと金属が擦れる音が部屋に響くだけだった。
すると、彼は書面とペンを持ってきた。内容を確認すると、この契約婚は驚くほど良心的な内容だった。
叙爵式を無事に終えて以降に、ひっそりと契約関係は解消されることがまず書かれている。そして、イーサンはウェンディに最低限の妻としての役目を要求する代わりに、こちらの要望にできうる限り応える意思がある、と。
(じゃあ、もしかして……)
ウェンディは契約書を握りながら、恐る恐る口を開く。
「……で、殿下。私は物書きです。結婚してからも、作家としての活動を許していただけるということでしょうか」
「契約書に記した通りさ。役目を果たしてくれるなら、僕を侮辱した当該作品については除き、あなたの活動を放任するし、必要があれば援助するよ」
「……!」
彼はウェンディの心を惹く話を追加した。王宮でイーサンは暮らしており、仮の妻になればウェンディも叙爵式までそこに住まいを移すことになる。
彼は、ウェンディのために書斎を用意し、歴史ある図書館をウェンディのためだけに解放し、必要なものは買い揃え、好きなときに好きなだけ執筆活動をしていいのだと言った。
家族や元婚約者は、創作活動に反対だった。なぜなら、ウェンディが好きな大衆小説は、下々の庶民が楽しむ低俗な娯楽とされており、貴族からは軽んじられていたから。だから今まで、家族が眠っている間に寝室で毛布を被りながら書いたり、図書館に籠ったり、負い目を感じながら物語を書いてきた。
周囲に認められず苦労してきた趣味だったが、それをイーサンは容認してくれると言うのだ。
それに、契約期間を終えたあとも、王子の元夫人という地位があれば、作家として話題作りになり新たな道が開けるかもしれない。
(最っ高の条件じゃない……っ! いやいや、騙されちゃ駄目よ騙されちゃ。でも……この機を逃す訳には……)
心が大きく揺らぐウェンディに、彼が畳みかけてくる。
「それから、契約期間を終えたあと、君の言うことをなんでもひとつ聞こう」
「なんでも……」
「王子の妃という重役を務めてもらうんだ。――相応の対価を払わなくちゃね」
ごくりと唾を飲む。王子という立場があればきっと、叶えられない願いはないだろう。
歴史書の数々が保管された禁書庫の出入り。
一生かけても読み切れないほどの本に埋もれること。
憧れの作家との対談。
小さなころから抱いていた夢が、ロイヤルパワーを使って叶えられるかもしれないのだ。
ウェンディの瞳の奥が煌めくのを、彼は見逃さなかった。ぐいとこちらに顔を近づけ、圧をかけるように言う。
「どう? 仮の妻、なってくれるよね?」
「……そ、そんなすぐに決められません! よく考えてから返事を……」
イーサンは大きくため息を吐く。
「あなたの作品のせいで僕は縁談と叙爵を逃した。その責任を取るとさっき言ったはず。こっちはあなたの要望まで受け入れてかなり譲歩してるんだけど、まだ納得できない? ――ルイノ、告訴の手配をしろ」
するとどこからともなく騎士服を着た男が現れ、「御意」恭しくと返事する。
(告訴!? さ、裁判でもする気なの!?)
「ま、待った待った! ――分かりましたよ! もう、なればいいんでしょなれば!」
もうこうなったらやけくそだ。契約書と婚姻書にサインをする。
(ああもう、私どうなっちゃうのかしら……)
イーサンの声で思いに耽っていた意識が現実に引き戻される。
「書けたか?」
「どうぞ、契約書です! これで私はお望み通りあなたの仮の妻ですよ!」
契約書を彼の鼻先に突きつける。そこでようやく手首の錠が外された。赤くなった手首を擦りながら、彼を睨みつける。
かくしてウェンディは、第3王子イーサンの契約妻になったのである。(契約結婚、次の作品のネタにしよう……)なんて密かに思いながら。