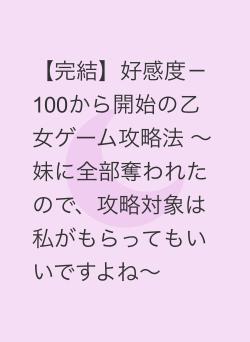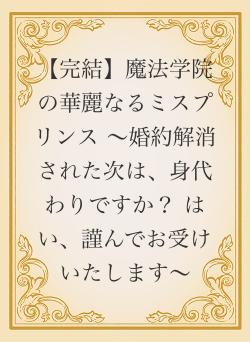一年後。
イーサンは新たにナーセリテイルという姓と公爵位を賜り、王都から離れた広い領地に屋敷を構えた。
温厚で、人当たりもよく、思いやりがあり、おまけに美男子であることから、領民にすぐに好かれるようになった。時おり彼は娼婦の子だと揶揄する声もあったが、それは本人の耳には届かないほど小さな声だった。
元婚約者のロナウドだが、借金が時効になるのを狙って夜逃げし、未だに行方不明になっている。どこに隠れているのかは知らないが、少なくともまともな生活を送れているとは思えない。
他方、ウェンディは今日も変わらず、屋敷の書斎に引きこもり、原稿と睨めっこしていた。
(やばいやばいやばいやばい……! これ絶対に間に合わないやつ……!)
真っ白な原稿を前にして頭を抱える。新しいジャンルの書き下ろしを依頼されたはいいものの、アイディアが何も浮かばず、ただ締め切りが近づいてくるだけだった。
今までの執筆活動で、幾度となく修羅場をくぐってきたが、今回は三本の指に入るくらいには焦っている。
すっかり行き詰まって天井を仰いでいると、書斎の扉がノックされて、イーサンが入ってきた。彼のにこにことした爽やかな笑顔を見て、ほんの少しだけ疲労が和らいだ気がする。
「作業は順調?」
「え、あー……まぁ……」
「はは、その顔。だいぶ行き詰まってるみたいだね」
「う……当たりです」
イーサンは書きかけの構想の紙を手に取って眺めた。
「へぇ、今回の依頼は小説じゃなくて――恋愛指南書なんだ? って、君が!?」
「ちょっと。君が!? って、どういうことですか!」
「…………」
「失礼な人」
イーサンと結婚するまで、恋愛経験0だったことを言いたいのだろうが、失礼な反応だ。ウェンディは唇と鼻の間にペンを挟み、口を尖らせながら「私だって断りたかったですよぅ」と愚痴を零す。
しかし、その編集者がどうも押しが強い人で、いつの間にか引き受ける流れになっていた。ウェンディは下級貴族の出身でありながら、第3王子と結婚し、更には第1王子にまで求婚されたということで、男を籠絡する恋愛マスターかのように世間では思われている。
(恋愛マスターどころか初心者みたいなものなのに……! 人様にどうアドバイスしろっていうのよ)
額に手を当てて、大きなため息を吐く。
「もう少し、肩の力を拭いて、物語を作るときみたいに書けばいいんだよ。僕はウェンディ先生の物語に出会えたから、どんな辛いことも耐えてこられた。きっとこの本だって、今までのジャンルではなくても、どこかに励まされる人がいるんじゃないかな」
「そう、ですよね……! これも滅多にないチャンスだと思って、頑張って書きます……!」
「ふ。その調子だ。僕も楽しみにしているよ。――あ、そうだ」
彼に励まされ、ようやくやる気を取り戻すウェンディ。イーサンはポケットから棒のついたキャンディを取り出して、包みを剥がした。
「頭疲れたときは甘いものがいいと言うよ。ほら」
キャンディを差し出され、食べさせてくれるのだと思って顔を近づけ、口に含もうとしたそのとき――。
「ありがとうございま――す」
『す』の言葉を発するのと、ちゅ、と音がして暖かいものが唇に触れるのは同じタイミングだった。彼は、ウェンディがキャンディを食べようと口を近づけた拍子に、口付けしたのだ。優しくて、キャンディよりずっと甘やかな感覚に身体が痺れる。
イーサンは硬直したウェンディの反応を見て楽しそうにくすと笑うと顔を離し、ウェンディの口の中に今度こそキャンディを押し入れた。
「午後は沢山のお客さんが来る。くれぐれも無理はしないようにね。ウェンディ先生?」
いたずらに成功した子どものように目配せした彼は、ひらひらと手を振って書斎を出て行った。
口の中にいちごの味が伝わる。
ウェンディはキャンディを舌で転がして頬に入れたあと、そっと唇を手で押えた。柔らかな感触が未だに残っていて顔が熱くなり、ぷしゅっと湯気が立ち上る。
(恋愛指南書、イーサン様が書いた方がいいのでは……!?)
そんなこんなで午前中は仕事に没頭し、午後はドレスを着替えて屋敷の敷地内に佇む講堂へ向かった。
講堂には、大勢の女性が集まっていて、ウェンディが登壇するのをまだかまだかと待ちわびていた。今まで屋外の噴水広場で行われていた週末の朗読会だが、この講堂に開催場所を移したのだ。この講堂は、イーサンの意向で建てられた。
ウェンディが壇上に上がると、客たちは拍手で彼女を出迎えた。片手に本を持ったウェンディは挨拶をしてから、聴衆に語りかける。
「私はずっと……物語の主人公みたいになりたいと思っていました。でも今は、どんな人生も、美しくて、愛おしくて、特別なものに見えます」
見目麗しい王国のお姫さまでなくても、世界を救えるほどの偉大な魔法使いでなくてもいい。
ウェンディはウェンディのままで、自分の人生を懸命に歩んでいき、日々の些細な出来事を噛み締めていきたいと思う。
「物語のような出来事は、どこにでも転がっています。ここにおられるおひとりおひとりの人生が、一冊の本では描ききれない尊い物語なんです」
ウェンディは持ってきた本を開いて朗読を始める。
「今日も物語を語りましょう。『嫌われ者の王子様』が恋をして幸せになる、特別な物語を……」
◇◇◇
ナーセリテイル公爵夫妻は、本好きで有名だった。国立図書館に匹敵する蔵書数の私有図書館を、庶民のために無償で解放した。公爵は時々、本を読めるようにと自ら領地の子どもたちに文字の読み方を教えることもあった。
また、公爵は結婚する前から、有名作家である妻の熱心なファンで、変装して朗読界やサイン会に通うほどの気合と熱量の持ち主だった。
公爵邸の講堂では週に一度、ウェンディの朗読会が行われ、主婦が家事の途中で抜け出して彼女の物語を聞きに訪れた。
そして、公爵は誰よりも熱心に、妻の語りに耳を傾けていたとか。
〈おしまい〉