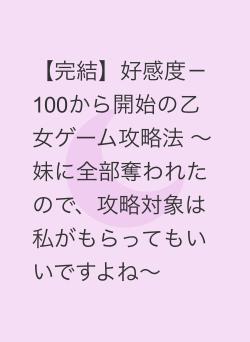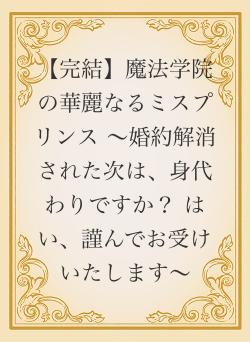エリファレットはウェンディの作戦を聞いたあと、急ぎ王宮へ戻った。ばたばたと音を立てて廊下を走り向かった先は、王妃ルゼットの部屋。
一週間も行方をくらましていたため、ルゼットは心配していた。
「エリファレット! この一週間どこで何をしていたのだ!? 心配したのだぞ」
「……心配をおかけしてすみません」
「いや、まずは無事で何よりだ。それに今、第3王子妃が失踪して大騒ぎになっているのだが、まさかお前……この件に関わっていないな?」
「その件について……お話があります」
ルゼットの前にがくっと項垂れ、青白い表情を浮かべると、彼女はエリファレットからただならぬ何かを感じ取った。
「実は、その……」
「どうしたというのだ? 早く申してみよ!」
「……はい。実は、第3王子妃を攫ったのは――この俺なんです」
「なんということを……っ」
彼女は額に手を当てて大きく息を吐く。
「勝手な行動をお許しください。彼女の作品を政治利用する目的だったのですが、予想外の裏切りがあって、その事実をイーサンに知られまして」
そして、ラティーシナが生きていることも彼に知られたと打ち明けると、ルゼットは血相を変えた。
「それで、あの者はなんと?」
「――俺のことを告発する、と」
ルゼットはそれを聞いてふらりとよろめき、眉間を指でぐっと押した。イーサンに渡ってしまった王位継承権を取り返そうという大事な時期に、取り返しのつかない失態をしたと罵ってくる。
エリファレットは頭を床につけ、ひたすらに詫びの言葉を繰り返すしかなかった。彼女は爪をぎりと前歯で噛み、地を這うように呟いた。
「……消すしかないな」
ぞくりと背中に冷たいものが走る感覚がする。
「……それは、イーサンを……ということですか? 彼の母親を殺したときと同じように……」
「ああ、そうだ。他に誰がいる」
イーサンの母親は毒による中毒で身体が弱り、イーサンを産んでからすぐに死んだ。しかし、毒を用意するためにルゼットがどこに依頼したのか、彼女以外に知る者はいない。
「しかし、暗殺にはリスクが伴う。毒ではなく別の手段を検討してからにしよう」
別の手段を検討すると言われ、エリファレットは下唇を噛んだ。
するとそのとき、扉の外で待機していた侍女が、来客を伝える。
「王妃様。イーサン様がお見えになりました」
「!」
エリファレットとルゼットは顔を見合わせた。彼女に『隠れていろ』と命じられ、衣装室の奥に隠れる。イーサンは底冷えするような冷たい表情で入ってきて、ルゼットをねめつけた。
ルゼットはひとりがけのソファに足を組んで座り、挑発するように彼を見上げて言う。
「そのような怖い顔をして、どうしたのだ?」
「……兄上が私の妃を誘拐しました。そして……第1王子妃の舌を切ったのはあなたであることも聞きましたよ。ラティーシナ妃殿下は現在、私が保護しています」
「……だから何が言いたい。はっ、私を脅す気か?」
「お2人のことを告発するつもりです。あなたの子どもが、王弟との不貞でできたことも、裁判で証言し、国中の人々に知ってもらいましょう」
「なっ……! そのような真似をして、ただで済むと思っているのか!? 私に逆らえば――」
「――第2妃のように消す、ですか?」
ルゼットは「なぜそれを……」と絶句し、固く拳を握り締めた。イーサンは顔色を全く変えずに、冷たく答える。
「それだけ伝えに参りました。明日にでも準備をするつもりですので、どうぞお覚悟を」
イーサンは踵を返す直前、衣装室の方をちらりと見た。その瞬間、エリファレットは彼と目が合う。
彼が宣戦布告して部屋を去ったあと、エリファレットが衣装室から出ると、ルゼットは怒りに顔を染めて重々しく言った。
「やはり、検討している暇はなさそうだ。すぐにでもあの生意気な口を黙らせなければ……」
彼女は部屋の引き出しから紙を出して、人の名前と住所を書いた。
「これは……?」
「この男に会えば、致死性の高い毒を手に入れることができる。銀にも反応せず、死後に毒を使ったと分からない毒だ。イーサンの母親を殺したときもこの者を頼った。至急毒を用意し、召使いを使ってイーサンの食事に混入させろ。そして、ラティーシナを奪い返すのだ」
「……分かり、ました。母上」
エリファレットは紙を受け取り、寂しげに眉尻を下げた。
「……母上は、ご自分の野望のためならどんなに手を汚すこともいとわないのですね」
「今更何を言うのだ。お前もよく知っているだろう」
「……はい」
部屋を出て廊下を進んだ先で、イーサンが待っていた。エリファレットは誰も見ていないことを確認し、ルゼットから受け取った紙をこっそり手渡す。
「お前の母親を殺すための毒を仕入れたのはこの男だ。この男をただちに尋問にかけろ。……そうすれば、王妃は今度こそ終わりだ」
ウェンディに提案された、ルゼットに勝つ方法とは、彼女が悪事を働いたことを証明することだった。
彼女に、イーサンを殺さなければ自分たちの立場が危なくなるのだと迫り、不安を煽れば、判断を鈍らせることができるだろうというところまでが、ウェンディの考えだった。
彼女の狙い通り、急かされたルゼットは毒の入手ルートをあっさり教えた。それがかえって、自分の首を絞めることになるとも知らずに。
「……想い人を守ることができるというのに、随分と暗いお顔をされていますね。兄上」
「あれでも血の繋がった母親だ。情はあるし、できることなら裏切りたくなかった。母親がいないお前には分からんだろうがな」
イーサンはそんな嫌味を受け流し、怒るよりも同情をあらわにした。
「母親に対する愛情は分かりませんが……兄上が妃殿下を守ろうとなさったお気持ちは……よく分かります」
そのとき、イーサンの剣につけられた首の傷がつきりと痛んだ。彼もまた、想い人のためなら誰であろうと刃を向けるのだろう。イーサンもひとりの女性を想う、自分と同じ男なのだと理解した。半分血を分けた、自分と同じどこにでもいる普通の男を、これまで深く傷つけてきたのだとようやく少し、自覚する。
「悪かったな。……もう誰も、お前の自由を邪魔することはしない」
「……!」
エリファレットは去り際、イーサンの肩にぽんと手を置いてそう伝えるのだった。彼は今までに見せたことがないような、意外そうな顔を浮かべていた。
◇◇◇
イーサンはすぐに、王国騎士を連れて、紙に書かれた男を訪れた。尋問にかけると、彼は過去に王妃に毒を売ったことがあるとあっさり自供した。
ルゼットは、イーサンを殺そうとしただけではなく、過去に第2妃に毒を盛り、第1王子妃ラティーシナの舌を切り害そうとした。多くの罪が重なり、処刑されることが決まった。エリファレットも廃位され、王宮から追放されることに。しかし、ラティーシナの実家が真面目に生きていくことを誓わせた上で彼を受け入れた。王宮を出て行く日、エリファレットはどこか清々しい様子だった。
彼の出立の日、ウェンディは離宮の書斎でひとり原稿に取り組んでいた。
「……どうして、兄上に力を貸したか聞いても?」
イーサンは机に片手を着き、こちらの顔を覗いた。イーサンがずっとエリファレットに邪険にされてきて、少なからず彼を憎んでいる。それに、ウェンディのことを誘拐し、監禁した相手だ。
同情があったとしても、そんな相手に協力したことを不思議に思うのは無理もない。
ウェンディはペンをことんと置く。
「……私たちは、人に完璧を求めすぎだと思うんです。エリファレット殿下は……言葉を選ばなければ欠点だらけで、多くの人の人生にとって悪役だと思います。でも彼には彼なりの事情があって……好きな人を守ろうと、歪ながら足掻いていたお姿は、人間臭くて好きなんです」
物語は、善人と悪人がいなければ成り立たない。いい人だけで刺激がない物語なんて、つまらないから。個性豊かな人たちがいるから、どんな物語も色彩豊かで面白くなるのだ。
「それに、王妃様を野放しにする限り、イーサン様に自由はないと思ったんです。私……あなたの力になりたくて」
ルゼットを放っておいたら、遅かれ早かれ彼女はイーサンを殺していたかもしれない。そう思うと怖くてぞっとする。だから、エリファレットを助けたのは自分のためなのだと説明すると、彼は納得した。
「僕の人生は……あなたに助けられてばかりだよ」
彼はこちらを見つめ、困ったように笑った。
「お互い様ですよ。……それより、立太子式はどうなったんですか?」
本来なら一週間後に行われるはずだったが、今回の件で延期になったのではないか。すると彼は、気まり悪そうに言った。
「中止だよ」
「中止? 延期じゃなくて?」
「あー、……実は僕、王太子にならないんだ」
「…………はい?」
「だって、どう考えても僕、王にふさわしくないでしょ?」
「それはそうですけど」
「否定はしないんだ……」
そんなことないよという慰めを期待していたのか、少しだけしょんぼりするイーサン。
彼いわく、ウェンディが失踪したあとに平常心を失い、『国なんかどうなっても知らない!』というような発言をし、立場を無視して王宮を飛び出して好き勝手したせいで、国王と大臣の信頼も見事に失ったらしい。当たり前である。
国王は贖罪のつもりでイーサンに王位を譲ろうとしていたが、結局、カーティスが代わることになった。イーサン本人も、大臣たちも誰ひとり異論なし、満場一致で次期国王が決まったのだ。
(なら……私の涙と覚悟は一体……)
イーサンから『自分が王太子になる』と告げられたときに、涙ながらに傍にいさせてと懇願したのが恥ずかしくなってくる。
「それから僕は……この先も婚外子として生きていくつもりだ」
「では……イーサン様はこのまま『嫌われ者の王子様』でいるおつもりなんですね」
「そうだね。僕は人から揶揄されようと、もう構わないんだ。大切な人ができたから。……兄上が僕の代わりに治世をする代わりに、汚名くらいは僕が背負ってもいいかなと思って」
彼は、おどけたように笑うが、相当の覚悟だと理解する。カーティスが王弟の子だと知れたら、どれだけ批判されるか分からない。今まで後ろ指を刺されてきたイーサンにはよく分かるのだろう。
「それからようやく、賜姓降下することになったんだ。好きな土地を選んで、自由に生きることができる。王家を離れれば、血筋のことを指摘する声も小さくなるはずだ」
「ええ。そうですね、きっと」
イーサンを忌み子だと嫌悪するのは、王家に対抗する上位貴族ばかりだ。権力から遠い場所なら、王族の揚げ足を取ってのし上がろうという気概があるような者はいない。
すると、イーサンが真剣な顔をして言った。
「ウェンディ。契約結婚は、ここで終わりにしよう」
「…………!」
彼がウェンディを手放すことはないと分かっているので、もっと何か、特別な提案をされるのだろうと予想した。
彼はウェンディが座っているすぐ傍まで歩いてきて、その場に跪き、その真剣な眼差しでこちらを見上げた。ウェンディも慌てて立ち上がる。
「……書類上だけじゃない、本物の妃になってくれませんか。ウェンディ」
「はい。喜んで……!」
ウェンディはぎゅっと彼に抱きつき、涙ながらに頷いた。
国家反逆罪の疑惑で捕らえられ、体裁を守るための仮の妻になったことが今では懐かしい。自分勝手で悪い人なのだと思っていたが、本当は違った。イーサンは、王家の思惑からウェンディをら守るために求婚してくれたのだ。
そしね彼はずっと、ウェンディの熱心なファンとして応援し、深く想い続けてくれた。
きっとこの先も、この人以上にウェンディの好きなことを受け入れ、ウェンディ自身のことを愛してくれる人は現れないだろう。
(この人は、私の運命の人なんだ)
物語のようなロマンチックな始まりではなかったが、それは、紛れもなく特別な出会いで。
窓から風が吹き込み、書斎の机に置かれた一枚の紙がふわりと飛んで、イーサンの目の前に落ちる。ウェンディの代表作である『嫌われ者の王子様』の2巻の原稿の1枚目だった。
イーサンをモデルにしたつもりはなかったけれど、最初に彼に指摘されてから、主人公のイザルはイーサンにしか思えなくなってきた。
孤独で、空っぽで、可哀想な王子様。心の乾きを癒したくて沢山の女の子と遊ぶのに、その乾きは増していくばかり。
一巻は、嫌われ者の王子が痛い目を見て終わるだけの内容になっている。
「2巻はどんな内容に?」
「嫌われ者の王子様に……救いを与えたいです。どんな嫌われ者だって、悪い人だって、いつかは幸せになっていいんだよって……」
イーサンは目の奥を揺らし、ウェンディの頬を優しく撫でて囁いた。
「――なら、僕があなたに出会えたようにしてやってくれ」