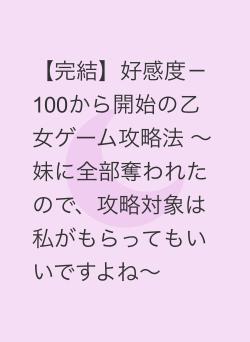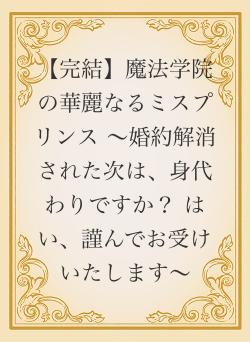「それで……完成した原稿というのは?」
「こちらをご査収ください、殿下」
その日の夕方。紙の束を差し出すと、エリファレットは性急な仕草でそれを奪い取り、目を通し始めた。
彼の隣で、ラティーシナがどこか緊張した面持ちでそれを見守る。
「これは……っ」
一枚、二枚、と読んでいくうちに、原稿を握る手の力が強まっていく。
険しい顔つきで読み耽っていたかと思えば、クライマックスに入るころに彼は目に涙を滲ませていた。全ての原稿を読み終えたあと、エリファレットはその場に崩れ落ち、とうとう堪えきれなくなったように嗚咽を漏らした。ぽたぽたと紙が涙で濡れていく。
「…………どうしてこんなものを書いた。俺は……イーサンの名誉を貶める小説を書けと言ったのに、こんな……っ」
「最初に言ったはずです。そんな小説を書くくらいなら死んだ方がマシだと」
ウェンディはエリファレットの命令に従うフリをして、全く違う内容の小説を書いていた。
それは、エリファレットとラティーシナをモデルにした悲恋。執筆にあたって、ラティーシナが2人の過去を、筆談で沢山聞かせてくれたのを役立てていた。
エリファレットが床に散らばした原稿の後ろには、ラティーシナが思い出を綴った文章が集まっていた。そこには、彼女の紛れもない真心が込められている。
「政略結婚から始まった、暴君と美しい妃の切ない恋……。お二方の尊い思い出を物語として描くことができて幸せでした。ラティーシナ様と殿下がどれほど互いを深く慕っているのかよく伝わって……読む人の心を熱くするでしょう」
ラティーシナは床に散らばった原稿とメモ書きをひとつひとつ拾い集めて、エリファレットに持たせた。
「お前……俺のことを……憎んでいないのか? 俺のせいでお前は、舌を失ったのに……」
エリファレットは鼻をすすりながら彼女に尋ねる。
彼は長い間、自責の念と負い目を感じて、ラティーシナを避けてきた。しかしラティーシナは、彼のその思いも全部見抜いていた。自分勝手で、横暴で、ろくでもない王子の心の奥に灯った小さな火の温かさを、彼女だけは知っていた。
ラティーシナは彼の両肩に手を置いて、ゆっくりと首を横に振り、小さな唇を動かして『あいしている』と舌っ足らずに伝えた。エリファレットは華奢な娘にみっともなく泣き縋り、何度も詫びの言葉を口にした。
抱き合う2人を見下ろしながらウェンディは言う。
「エリファレット殿下。この物語はまだ、途中なんです。悲恋で終わらせず、ハッピーエンドにするために、展開を少し書き換えてみる気はありませんか?」
「ハッピーエンド……?」
「はい。今は物語の佳境。悪人を倒さなければ、主人公たちに幸せなエンディングはやってきません」
だから、無実のイーサンを蹴落とそうとするのは間違っているのだと暗にほのめかす。そして、本当に倒すべき悪人は――ルゼット王妃なのだと話した。
「母上を倒そうって言うのか? そんなこと……一体どうやって……」
「ここまで、沢山の伏線が散りばめられてきたじゃないですか。あとは、それを回収するだけです」
ウェンディはびしっと人差し指を立てた。
「その方法はですね――」
伏線回収のための妙案を伝えようとしたそのとき、後ろでガラスの窓が割れる音がして振り返る。板を打ち付けて開かないようにしていたのに、板ごと破壊される。
ガラス片が飛び散り、エリファレットはラティーシナを庇うように前に出た。
そして、窓から押し入って来たのは――イーサンとルイノだった。
「大丈夫ですか? ウェンディ様。お怪我は?」
「わ、私なら平気です」
ルイノが心配そうに声をかけてくる。対して、イーサンは今までに見たことがないほど怖い顔をしていた。ちらりとウェンディのことを一瞥して頬が腫れていることを確認したあと、また眉間の縦じわを深くさせて腰の剣を引き抜き、エリファレットの首筋に突きつける。
普段は温厚なイーサンの並々ならない気迫に、エリファレットは本能的な恐れを感じてぐっと喉を鳴らす。彼が両手を掲げて降伏の意を示すが、剣を下げようとはしない。
「どうしてここが分かった? イーサン……!」
「僕は剣の腕は兄上より上でしたよね。……兄上はこの世で最も手を出してはいけない相手に手を出しました。命をもって償う覚悟はとうにできているんですよね?」
刃がエリファレットの肌を擦れて、血が滴り落ちる。ラティーシナがやめてと声を張り上げるのと、ウェンディがイーサンの後ろから抱きついて宥めるのは同時だった。
「私なら無事です。……だから、その剣を下ろしてください」
彼の体は、震えていた。それはきっと、怒りであり、ウェンディを失うことへの不安と恐怖が理由だと悟った。ぎゅっと強く抱き締めて、私はここにいるのだと伝える。強く抱き締めれば、次第に震えが治まっていくのが分かった。
「私のメッセージ……受け取ってくださったんですね」
「もちろんだよ。ウェンディのことなら……なんでも分かる」
「ふ。さすがは……私の熱烈なファンです。あなたなら汲み取ってくれるって信じていました」
剣を握る手に自分の手を重ねると、怒りで我を失っていたイーサンは、ようやく剣を収めた。ウェンディはここまでの事情を打ち明けた。
「私はエリファレット殿下を許すつもりです。……それより、2人に協力をしたくて」
「2人……?」
イーサンはエリファレットの後ろに隠れているラティーシナの姿に気づき、目を見開いた。死んだはずの元妃が、実は生きていて下女に扮したのだから驚くのは当然だ。
ウェンディは、エリファレットがルゼットから守りたくて、一連の騒動を起こしたのだと説明する。
「あなたがお人好しということはよく分かったよ。――それで。今度はどんな方法を使ってストーリーを作るつもりですか? ウェンディ先生」
「簡単なことですよ。ここに役者は揃っています」
そう言ってウェンディは、エリファレットに視線を向けた。ウェンディが考えた作戦を説明すると、エリファレットは暗い顔をした。