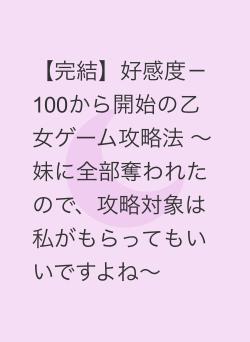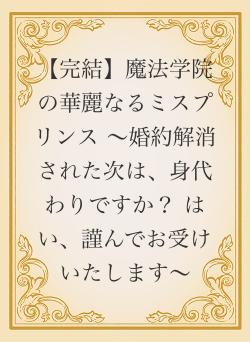ラティーシナが初めてエリファレットに会ったのは、輿入れの日だった。
彼は素行が悪く、不真面目だと評判が悪い王子だ。それを心配した母親のルゼットが、彼女の勢力下の公爵家の令嬢で、生真面目なラティーシナを、エリファレットの教育係兼妻にあてがったのである。
形式的な挙式を上げて夫婦となった初夜。ラティーシナは念入りに体を清めて、美しい絹のナイトウェアを身にまとい、寝室で待っていた。
(……緊張してきましたわ)
政略結婚ではあるが、夫婦になったのだ。初めて過ごす夜に不安と緊張をしながら待たされること数時間――。日付が変わるころにようやく寝室を訪れた彼は、開口一番に言った。
「お前を愛するつもりはない」
という言葉を。
「えっと……それはどういう……」
「言葉のままだ。俺はお前に対外的な妃の役目以外は一切要求しない。そして、逆も然りだ」
それは、ラティーシナに干渉しない代わりに、自分にも関わるなという意思表示だった。
◇◇◇
それから、エリファレットはラティーシナのことを無視して勝手な行動ばかりを取った。夜な夜な社交の場を遊び歩いては、国民の血税で豪遊三昧し、おまけに人に横柄な態度を取る。絵に書いたような暴君だった。
(ああもう……エリファレット様はどうしてこうなのでしょうか。あの方がていたらくだと、教育係の私が王妃様に叱られてしまうのに)
先日、エリファレットが重鎮の娘にひどいことを言って泣かせたせいで問題になっている。そのことで王妃に呼び出されて、ラティーシナが叱責される羽目になった。妃として、彼の行動を監視する責任があるのだと。
とぼとぼと廊下を歩いていると、絨毯の端につまずいて転んでしまった。
「きゃっ……」
変な体勢で転んだせいで足を挫き、起き上がれなくなる。そのとき、「邪魔だからそこを退け」という声後降ってきたので顔を上げると、エリファレットが忌々しそうにこちらを見下ろしてきた。
「は、はい殿下……」
道を塞いでしまったことを詫び、急いで退こうとするが、捻った足首の痛みに顔をしかめた。すると彼はこちらに身をかがめる。
「なんだ、怪我でもしたのか?」
「……つまずいて転んだんです」
「鈍臭い女だ。……ったく、仕方がないな。じっとしていろ」
「へっ……!?」
エリファレットはラティーシナを横抱きにして立ち上がった。彼の手を煩わせる訳にはいかないと腕の中で身じろぐが、大人しくしていろと上からねじ伏せられる。
程よく鍛えられた腕でしっかりと支えられていて、精悍な顔が間近で観察できる距離にいるのが、妙に落ち着かない。
「あの……重くはありませんか」
「まぁ……軽くはないな」
意地悪に鼻で笑う彼。
「…………ひどいです」
こういうときは、嘘でも軽いと答えるのが礼儀なのに、正直にものを言うところは彼らしい。ラティーシナが不機嫌に頬を膨らませると、「むくれるな」とまたからかうように笑った。
医務室にラティーシナを運んだあと、彼は手当までしてくれた。ソファに腰を下ろし、足に湿布を貼ってくれている彼の姿を眺めると、顔を上げた彼と視線がかち合う。
「俺がこういうことをするのが意外だったか?」
「えっと、あの……はい。……お優しいところもあるのですね」
「……!」
褒められて照れたのか、エリファレットの頬がわずかに赤くなる。
「別に、優しくなんてない」
一瞬見せた子どもっぽい姿がいじらしくて、もっと冷酷なだけの人だと思っていたという言葉は喉元で留めた。
「あまり私のことを避けないでくださいませ。でないと……私が王妃様に叱られてしまいますので」
「……考えておく」
手当てはしてくれたが、そっけなく返事をしたまま医務室を出て行ってしまった。けれどこのときに、少しだけエリファレットへの印象が変わった。
その日から、2人の関係性は少しずつ変化していった。相変わらず、エリファレットは横暴で素行が悪かった。しかしラティーシナだけには、優しさを向け心を開くように。
「殿下……! 昨晩、国宝の壺を割ったとお伺いしましたよ……!」
「ラ、ラティーシナ……! それは、違うんだ。訳があって……。わざと割った訳ではない!」
「それはそうでしょう。千鳥足になるまでお酒を飲まれたのですからね……!」
「……次は気をつけるから」
教育係として、厳しく叱責する。エリファレットは子どものころから甘やかされ、叱られることなく育ってきた。だからここまで自由奔放でろくでもない人に育ってしまったのだろう。
ラティーシナは教育係だけではなく、彼の妻であった。どんなに遊び回っても、夜更けにはラティーシナの部屋に戻ってくる。
「今何時だとお思いですか」
「またそんな大衆小説を読んでるのか」
「話を変えないでください。……これは今一番人気のウェンディ・エイミス先生の本なんですよ? 読みますか?」
「俺はいい。興味ないからな」
すると彼は、背中に隠していた小さな箱を取り出してこちらに渡した。箱の中には美しい首飾りが入っていて。
(……誕生日、覚えていてくださったのね)
今日はラティーシナの誕生日だった。
照れくさそうに頬を赤くしたエリファレットを見て、胸がきゅうと締め付けられる。ラティーシナは本を置き、彼に抱きついてありがとうと感謝を口にした。
――そんな風に、夫婦として少しずつ仲良くなり始めたころ、事件が起きた。
ルゼットとエリファレットが、3人の王子の出生について話しているのを聞いてしまったのだ。
「イーサンが最近、死んだ第2妃にますます顔が似てきた。……なんと忌まわしい」
「親子ですからね。……国王陛下はなぜあいつを婚外子として王宮に置いたのでしょうか」
「決まっている! 私から我が子を守るためだろう。そしていずれ私を廃位し、肝心な王位はイーサンに渡す魂胆なのだ」
ちょうどその日、エリファレットの私室にルゼットが訪れていた。扉の外で話を盗み聞きしていたラティーシナは、その事実に戦慄する。
(そんな……。エリファレット殿下とカーティス殿下が、国王の弟の子で、イーサン殿下が本物の王位継承者だったなんて……)
重大事実を王家が隠蔽していたのだ。イーサンは婚外子として、王妃を中心に強く迫害されていたが、それは不貞への嫌悪ではなく、王位を奪われるかもしれないという脅威から来ていたのだと理解する。
この事実が知れたら、とんでもない混乱が生じることは間違いない。正統な王位継承者を迫害してきたエリファレットまで非難されるのはもちろんのこと、もしかしたら、王家に対する民衆の信頼そのものが揺らぐことになるかもしれない。
(聞かなかったことにしなくては……)
早くここを立ち去り、今耳にしたことは決して他人に話さずにいよう。知ったことがあの王妃にバレたら、何をされるか分からないから。それなのに、足が竦んで、床に縫いつけられたように動けない。
呆然と立ち尽くしていると、ふいに人の気配を感じてこちらを見たルゼットと目が合い、盗み聞きしていたことを知られてしまう。
ラティーシナは私室の中に引きずり込まれた。
「すぐにその者を殺すのだ! エリファレット!」
「申し訳ございません、どうかお許しを……! 全て聞かなかったことにいたします。決して口外せず、胸に秘めたまま墓場まで持っていくことを誓いますから……!」
「信用ならぬ! 今まで……秘密を知った者は全員殺してきた。王子の妃だからと言って、お前だけを許すことはできぬ」
床に手を着き、必死に命乞いをするが、取り付く島もなかった。
すると、傲慢で他人を見下してばかりだったエリファレットが跪き、ルゼットの隣で初めて頭を下げた。
「……どうか、彼女の命だけは助けてやってください。なんの罪もない娘です」
ラティーシナは驚いて、自分のために懇願する彼を盗み見た。汗を滲ませ、眉間に皺を刻んでいる。
(エリファレット様……)
初夜に『お前のことを愛すつもりはない』と告げられ、ラティーシナを一方的に遠ざけてきた彼だが、今ではラティーシナに対する情が芽生えたらしい。
ルゼットは嘲笑するようにふっと鼻を鳴らした。
「そなた……その娘に惚れているのか」
「…………」
ぎりと歯ぎしりしたあと、エリファレットは唇を開いた。薄く形の良い唇が発したのは、「――はい」というラティーシナの予想外の言葉だった。
「そうか。私も我が子の愛する者を殺すほど冷酷ではない。そなたの気持ちに免じて助けてやろう」
「ありがとうございます……!」
エリファレットは乱暴で、自分勝手で、思いやりもないどうしようもない人。分かっているのに、嬉しくなって泣きそうになった。
(私も……お慕いしております)
喜びも束の間、ルゼットはチェストの上の花瓶の近くに置いてある花バサミを手に取り、こちらにらつかつかと歩いて来た。彼女はぐっとラティーシナの顎を掴む。
「母上っ!? 何をする気だ!?」
「――望み通り、命は助けてやろう。だが、害さないとは言っておらぬ。お前は二度とラティーシナという名を名乗ることもせず、王宮の外で死んだように生きるのだ。そして、この痛みを胸に刻んでおけ」
花バサミの刃先がシャンデリアの光を反射して、不気味にきらりと輝きを放つのを見て、恐怖に身が竦む。
「嫌……っ、何をなさるおつもりですか!? やめて、いやぁぁ……!」
ルゼットの言いつけを守れなければどうなるのか知らしめるかのように、彼女はラティーシナの舌を切り落とした。
強烈な痛みとともに、口から血が溢れ出て、ドレスやカーペット、手を汚していく。
その後のことはよく覚えていない。すぐに気絶してしまい、目が覚めたら王宮の外の小さな病院にいた。
ルゼットは、ラティーシナが病死したことにした。ラティーシナの実家は、結婚を命じられたときと同じようにルゼットの圧力に逆らえず、遺体も返ってこないのに娘の死を受け入れた。
ルゼットが勝手に葬儀を取り計らい、ラティーシナの死の真相を王家は追求することもできず、闇に葬られたのである。そして、彼女の死はエリファレットの家庭内暴力に耐えかねた自死だったのではないか、という噂が流れた。
一方のエリファレットだが、事件からしばらく、抜け殻のようになってしまい、遊び回るのを一切やめた。彼は度々王宮の外に出かけたが、夜会に出かけるのではなく、実際は死んだはずの妃に会いに通っていた。しかし、エリファレットが改心して献身的に想い人の世話をしていることなど、誰も知らなかったのである。
◇◇◇
ラティーシナから筆談で過去の真実を聞かされたウェンディは、あまりに悲惨な内容に戦慄した。
(なんて卑劣な……。同じ人間がすることとは思えないわ。まるで創作の中の悲劇みたい……)
ラティーシナがどれほど辛く、悲しい思いをしてきたか分からない。きっとそれは想像を絶するもので、今も彼女の心を苦しめているのではないか。
彼女やエリファレットのここまでの苦悩を思うと、胸が張り裂けそうだった。
「――それで、あなたはここで下女のフリをしてひっそりと暮らしてきたということですね。……息を潜め、死人のように……」
彼女はまた小さく頷き、筆談用の手帳に文字を書き始めた。
そこには、こんなことが書かれていた。
『王妃様にされたことは許せませんが、それでも今日まで幸せでした。エリファレット様に愛していただけて、誰かを愛することを知れたのですから。舌を失う前に戻ったとしても、エリファレット様に出逢えるのなら、喜んでもう一度同じ道を選ぶでしょう』
彼女は、男を想う女の表情をしていた。
エリファレットは、横暴で冷酷、危険な人だ。それでも、ひとりの妻を愛する男であり、悪人ではない一面も持っているということだろう。
彼に殴られた頬がずきずきと痛み、ウェンディは苦笑した。
(本当に……『愛』というのは困ったものね。理屈ではどうにもならないものだから。でも……だからこそ、たまらなく美しくて惹かれる。ずっと書き続けていたいと思う)
エリファレットに出会わなければ、舌を失うことも、名前を失うこともなかったはずなのに。その痛みさえ愛すというのだから、病気みたいなものだ。……愛というのは。
『あの人にも優しいところが沢山あるんですよ』となおも彼を庇おうとするラティーシナの腕を掴んで、首を横に振る。彼女が彼を思う気持ちは、もう十分すぎるくらい伝わったから。
「愛していらっしゃるんですね。……エリファレット殿下のことを。とても深く」
「…………」
彼女は優美な表情で、しっかりと頷いた。その頬はほんのりと色づいている。
ルゼットは、ラティーシナを殺さない代わりに、エリファレットに言うことを聞かせていた。目の前で非力な女の舌を切る残虐性を知ったエリファレットは、彼女の意に背いたら大切な人を殺されるかもしれないと思い、彼女に従っていたのだ。
ルゼットの目的は、イーサンではなく、自分と王弟の血を引く子を王に据えること。だからエリファレットは、イーサンを王位から引きずり下ろそうとウェンディに近づいたのだろう。
そこで、ウェンディは思案した。ルゼットに迎合し陰に隠れて苦しみ続ける以外に、2人を救う方法があるのではないかと。エリファレットが王位に興味がないなら尚更。
「では……こういうのはどうでしょうか。ラティーシナ妃殿下さえよろしければ、協力していただきたいのですが」
ウェンディはその日から、彼女の協力のもと、小説を書き始めた。