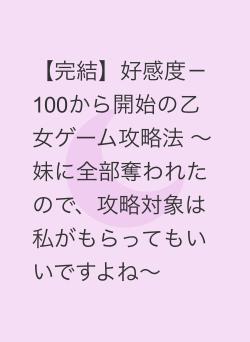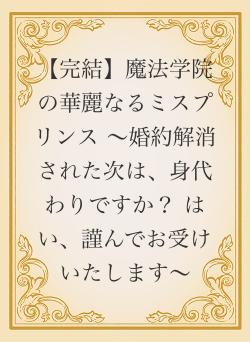目を覚ますと、どこか分からない小さな部屋に閉じ込められて横たわっていた。飾り気のない室内には、机と椅子、大量の紙と筆記用具があるだけで、他の家具はない。
ひとつだけある窓は、上から板が十字に張り付けられていて、開かないようになっている。
(ここはどこなの……?)
口に巻かれた布を手で解き、机の上に置く。庭園で本を読んでいたら、ロナウドとエリファレットに連れ去られたのは覚えているが、この場所には検討がつかない。ウェンディは額を手で押えた。
「こんなベタな展開ある……!?」
物語のヒロインが敵に攫われる展開は、作家が擦り尽くしてきた展開だ。ウェンディも幾度となく手段を尽くしてヒロインを誘拐させてきたが、まさか自分がこんな風に誘拐・監禁されるなんて。
急いで立ち上がり、脱出を試みようと扉のレバーハンドルに手をかける。しかし案の定鍵がかかっていて開かない。
ウェンディは机の後ろに置いてある椅子を取って、扉の前に行った。
「ふん……っ」
椅子の足で思い切り扉を叩きつけると、椅子の方が壊れた。
その直後、扉が解錠され、エリファレットが入ってきた。彼の後ろにはロナウドとひとりの下女が付き従ってきた。
エリファレットは壊れた椅子を見下ろして眉間を寄せる。
「なんて無謀な女だ。この重厚な扉を木の椅子で破れると思ったのか?」
「これは一体なんの真似ですか? あなたのしていることは立派な犯罪ですよ! ここから出してください!」
「黙れ」
彼は片膝をついて身をかがめ、ウェンディの顎を掴んで持ち上げた。今まで見せてきた穏和な表情は偽りだったのだと彼の鋭い目付きを見て理解し、ひゅっと喉の奥が鳴る。
「お前、自分の立場を理解しているのか? 命が惜しければ大人しく言うことを聞け」
「……あなたが王位を継ぐための小説を書け、とでも?」
「話が早くて助かる。だが少し違うな」
エリファレットはウェンディの顎から手を離した。掴み上げられていた反動で後ろに尻もちをつく。
「――イーサンの評判を落とすための小説を書け」
「な……んですって?」
妻であるウェンディに、夫を貶める文章を書けと言われて一瞬耳を疑う。イーサンはこの国の正統な王家の血を引いていた。散々『偽物』だと侮辱ルゼットの方が、王弟と隠れて愛し合い、国王の子ではないカーティスとエリファレットを授かっていたのだ。
今なら分かる。ルゼットがイーサンに向けていた憎悪は、正統な王位継承者に対する嫉妬、畏れからくるものだったのだと。
エリファレットはぎゅっと拳を固く握る。
「あの男、イーサンにだけは王座を渡すものか」
エリファレットもまた、ルゼットと同じようにイーサンに対して妬みや劣等感を抱き、自分の出生に負い目を感じたのではないかと思った。だからこそ彼は、長いこと極端にイーサンのことを邪険に扱ってきたのではないか。
それからエリファレットはウェンディに、作品についてこのような指示をした。
イーサンをモデルに悪者の主人公を作ること。
イーサンがいかに愚劣で醜く、王の器ではない人間かを描くこと。
この物語は勧善懲悪であり、最後に主人公は民衆に罰せられて追放されること。
作品を発表したあとで、エリファレットがこの作品のモデルがイーサンだと噂を流すつもりらしい。それを聞いたウェンディはふっと鼻で笑った。何がおかしいのかと尋ねてくる彼。
「プロパガンダ作品で人々のイーサン様への思想を誘導しようという考えは分かりました。でも、どうして私なんです? 私みたいないやしい大衆小説家に、大した宣伝効果はありませんよ」
すると、エリファレットは懐から白いハンカチを取り出して、ウェンディの目の前にかざした。蝶の刺繍が施されたそれは、ウェンディの作品に登場したのをきっかけに、今世間で大流行のデザインだった。
彼はいつも流行を生み出すウェンディの作品の力は、十分に宣伝戦略になるだろうと主張した。
「王太子の即位式まで1ヶ月。もう時間がない。すぐに書き始めろ」
「お断りします」
「…………は?」
要求をにべもなく断ると、彼は目を点にした。この状況でまだウェンディが歯向かうのは想定外だったらしい。
「命惜しさに、命令に従うと思いましたか? 私の大好きな小説で、私の大好きなファンを騙すくらいならいっそ死んだ方がマシです」
「〜〜〜〜!」
朗読会やサイン会に来てくれた読者の顔が脳裏をよぎる。『楽しかった』、『面白かった』と声をかけてくれた人たちの笑顔が。
ウェンディは誰かに楽しんでほしくて本を書いてきたのに、思想を統制しようとする政治の道具になんて絶対にしたくない。
エリファレットは眉間に縦じわを刻んでずかずかとこちらに歩み、ウェンディの襟を掴み上げて頬を殴った。
「生意気な奴め……! ロナウド、何としてもその女に本を書かせろ。……でないと……分かるな?」
「は、はい……! エリファレット殿下」
エリファレットは威圧的にロナウドに命じてから、部屋を出て行ったら、ウェンディはその場に座ったまま、殴られた頬を手で触れる。
(痛〜〜っ! ちょっとは手加減しなさいよ! 馬鹿王子!)
馬鹿王子ことエリファレットが出て行った扉を威嚇するように睨んでいると、ロナウドが怪我の具合を確かめるように手を伸ばしてきた。
「おい、口から血が――」
「触らないで!」
ぱしんとその手を振り払う。彼は気に入らなそうにため息を吐き、こちらに交渉してきた。
「どうしてお前はそう頑固なんだ? 命よりもいやしい趣味の方が大事な訳ないんだから。痛い目に遭いなくなければ大人しく言うことを聞くんだ。な?」
「……どの口がそれを言うのよ。ふざけないで。あなたが殿下の協力をしたのはお金のため? そっちこそ、お金のためなら犯罪にも手を染める人だったなんて、見損ないましたよぅ」
絶対に書くものかとべっと舌を出して、片目の下瞼を指で下げ、挑発する。
「お前、言わせておけば……っ!」
顔を真っ赤にして怒りをぶつけようとしたロナウドだが、はぁと息を吐いて、冷たい声音で言った。
「ああ、そうさ。金のために協力した。お前がくだらん意地を張れば、俺まで迷惑を被るんだ。お前だって、本当に殺されるかもしれないぞ。――ラティーシナ元第1王子妃みたいにな」
ロナウドは怖がらせるみたいにすぅと目を細め、そう吐き捨てたあと部屋を退出した。部屋の隅で控えていた下女に「さっさと手当してやれ」と命じて。
殴られた衝撃で口の中を切ったらしく、口内に鉄な味が広がる。唇から垂れた血を拭おうと袖を近づけると、下女に止められた。
無言でハンカチを差し出す彼女は、可憐な女性だった。長いまつ毛が影を落とす紫の瞳に、同色の髪を簡単に後ろで束ねている。
ウェンディがハンカチを受け取ると、彼女はペンと手帳を出して何かを書き出した。
『ご迷惑をおかけして申し訳ございません。でも、エリファレット様はあなたの命を奪ったりしないから、恨まないで差上げて』
困った顔をして、「ごめんなさい」の形で唇を動かした彼女を見て、尋ねる。
「あなた、声が出ないの……?」
彼女はこくんと小さく頷き、再び文字を書き始めた。ウェンディも手帳を覗き込み、彼女の文字を目で追う。
「……『私はラティーシナと申します。ここはエリファレット殿下が私を匿うために用意した郊外の隠れ家です』……って、ええっ!?」
声に出して読み、ウェンディは目を丸くした。ラティーシナは、死んだはずのエリファレットの元妃の名前だったから。
彼女は世間的には病死になっているが、エリファレットの横暴に耐えかねて自死したのではないかと一部では噂されていた。しかしそのどちらも事実ではなかったということだ。彼女は下女の格好をして自分の目の前にいるから。
「あなたは……数年前に亡くなったはずじゃ……」
ラティーシナは筆談でウェンディに真実を伝え始めた。
イーサンやエリファレットたち王子の出生の秘密を知ったせいで、王妃ルゼットの怒りを買い、殺されかけたのだと。
しかし、エリファレットがラティーシナの命を助け、世間で死んだことに見せかけて守ったというのだ。
「……あのひとを、たすけてください。ウェンディ先生」
彼女は舌を失っていた。そして、不明瞭な発音で、助けてとウェンディに訴えかけるのだった。