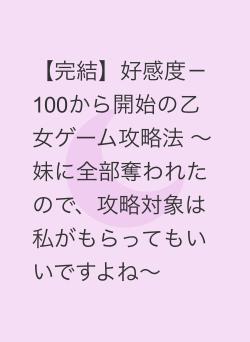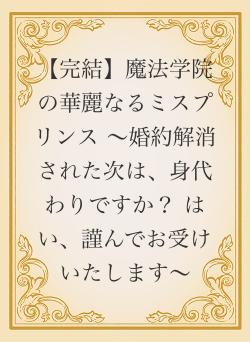ウェンディは書斎で、次に出版予定の小説の初校を確認していた。
誤字脱字や内容の矛盾の指摘を受けて、修正していく作業のことだ。
(あ……ここひどい誤字。恥ずかしい)
黙々と作業を進めていく。あまり楽しい作業ではなく、頬杖をつきながら原稿に視線を落としていると、窓から風が吹き込んで、紙がふわっと舞い上がった。入口近くまで飛んでいったのを見て立ち上がり、一旦窓を閉めた。
書斎の窓から、本宮が見える。1週間ほど前に、イーサンが他の王子と一緒に国王に呼ばれた。一体そこで何があったのか、離宮に戻ってきた彼は暗い顔をしていた。しかし、謁見の間での出来事を、ウェンディには頑なに話そうとしなかった。
(国王陛下は、イーサン様に何をおっしゃったの?)
今日もイーサンは謁見の間に向かっている。これまで彼は本宮に足を踏み入れることさえ嫌がられていたのに、こんなに頻繁に呼び出すなんて、国王にどんな心境の変化があったのだろうか。
イーサンが本宮に向かってから2時間ほど経った。そろそろ戻ってくるころだろうかと時計に視線をやったとき、書斎の入り口に人の気配がした。
「原稿、落ちてるよ」
やって来たのはイーサンで、彼は落ちていた原稿を拾い集めてくれた。優しい笑顔を浮かべてはいるものの、どこか陰りがある。
「ありがとうございます。……お戻りになったんですね、お疲れ様でした」
「仕事の邪魔をしたかな?」
「いえ! ちょうどひと段落ついたところです!」
本当はもう少し進めておきたいところだったが、彼が遠慮しないようにと嘘をつく。
紙を受け取りにイーサンの元に歩み寄ると、突然抱き締められた。手に握っていたペンが床に落ちて転がる。
「イーサン様!? 急にどうしたんですか!?」
「少しだけ、少しだけでいいから……こうさせてほしい」
彼から離れようと身じろぐが、上からぎゅっと抱き締めたまま、懇願するように囁かれ、抵抗しようという意思が封じ込まれてしまう。ウェンディは「少しだけですよ」と呟き、彼の背におずおずと腕を回した。背中を優しく撫でれば、彼は甘えるようにウェンディの肩に顔を乗せた。
「ウェンディ先生。……このままずっと僕の妃でいる気はない?」
「…………!」
寂しげに告げられた内容に、目を丸める。契約上の妃ではなく、本当の妃になれと言っているのだろうか。
「どうして突然、そんなことを……」
「僕はじきに、第3王子ではなくなる」
「第3王子ではなくなるって……賜姓降下されるってことですか?」
「……いいや、僕にとってとても不本意な形で。同時に、あなたを王宮に留めておく理由がなくなる。……けれど、あなたを手放すのが惜しくなってしまった。傍にいればいるほど、僕はあなたが……」
「イーサン様、何を……」
頭が混乱する中、イーサンは掠れた声を絞り出すようにして続けた。
「あなたの作品に風評被害を受けたというのはデタラメだ。そう言えば、あなたは僕の求婚を受けると思って嘘をついた」
「…………」
「僕は本当は、本当は……」
イーサンが嘘をついてまでウェンディに求婚したのは、第1王子から守るためだった。そのもっと深くに隠れる本心を、彼はまだ教えてくれていない。
しかし、その言葉の続きを彼は言わなかった。ウェンディを腕から解放して、困ったように笑う。
「――なんて。あなたはもう、第1王子に利用されることはなくなる。晴れて自由の身だ。……色々と迷惑をかけてすまなかった」
エリファレットがウェンディを利用する理由がなくなったと彼は説明する。どうしてかと聞くと、また彼は黙ってしまう。彼が肝心なことを言おうとしないので、状況を理解できない。
婚姻関係の解消をするための手続きを後でするからと一方的に告げられ、困惑するウェンディ。しかし、書斎を出ていく直前に言われた言葉で、全てを理解した。
「……僕が王位を継ぐことになった。だからもう、王位争いは終わるんだよ。王太子の即位式がまもなく行われる」
◇◇◇
ウェンディは婚姻を解消するための書面の前で、かれこれ2時間ほど静止して悩んでいた。
(この紙にサインしたら……イーサン様の妻ではなくなる)
最初はいやいや始めた契約だったが、この2ヶ月はずっと楽しかった。こんなに自由に執筆させてもらえたのは初めてだったし、イーサンは優しかった。彼といると、自分が自分らしくいられる。そして、一緒に過ごすうちに……いつの間にか好きになっていた。
ふいに、手に持っているペンに視線を落とす。イーサンとデートに行ったときに、彼がウェンディが欲しそうにしていたのに気づいて、わざわざ買ってくれたものだ。
イーサンは婚外子として忌み嫌われ、離宮で寂しく生きてきた。そんな彼を気の毒に思うようになり、同情はいつしか愛情に変わっていた。
(私……イーサン様のお傍にいたい)
一国の王妃なら、自分などではなくもっとふさわしい女性がいるだろう。ここでサインして身を引くのが、王になるイーサンのためなのかもしれない。それでも、離れたくないと寂しそうに言った彼のことが忘れられなかった。もしほんの少しでも自分を必要としてくれるのなら、まだここにいさせてほしい。
散々悩んだ挙句、ぎゅっとガラスペンを握ってから机に置く。
ウェンディが小さくため息を漏らした直後に、イーサンの騎士であるルイノが訪れた。
「……ルイノさん? 私に何かご用ですか?」
彼はつかつかとこちらに歩いてきて、ウェンディの手元の書面を見下ろして言った。
「それにサインをする前に、ひとつ見せしたいものがございます」
「……見せたいもの?」
「はい。少し着いてきてくださいますか?」
ウェンディはルイノと深く関わったことはなかったが、イーサンは彼のことを相当信頼して心を開いているらしく、いつも傍に置いていた。そんなルイノが、今になってウェンディに見せたいものはなんだろうと不思議に思う。
ルイノに言われるがまま着いていくと、案内されたのは――イーサンの執務室だった。
「あの……私、ここには『絶対に入るな』とイーサン様に言われてるんですけど……」
「全ての責任は私が取りますので、お気になさらず」
彼はそう言って執務室の扉を押し開く。初めて離宮に来たときから、口酸っぱく足を踏み入れるなと言われていたので、何かとてつもない武器なんかが隠れているのではないかと想像していたが、どこにでもある普通の部屋のように見えた。しかしすぐに、大きな本棚にウェンディがこれまで刊行した本が全て3冊ずつ収まっていることに気づいた。
(私の本……!)
そういえば以前イーサンが、好きな作家の本は読む用と保存用、布教用として3冊買うのだと言っていたのを覚えている。
まさか、その好きな作家とは、ウェンディのことだったというのか。ルイノがおもむろに1冊、本棚から1冊を引き抜いてこちらに差し出す。
「……ご覧ください」
それは、ウェンディが名誉毀損を訴えられて、イーサンと結婚することになった問題作『嫌われ者の王子様』だった。小説のほとんどのページに、線が引いてあったり書き込みがあったり、熱心に読み込んでいたことが分かる。
「…………!」
そして、本の表紙の裏に、ウェンディのサインが書かれていた。『ノーブルプリンスマン』が宛名の。
(私の唯一の男性ファン、ノーブルプリンスマンの正体は……)
「イーサン様……」
体に雷電が落ちたような衝撃が走る。あまりの驚きでふらふらとよろめいていると、ルイノが暗い色のローブと布のマスクを持ってきた。
「……殿下は、何年も前からウェンディ様々の熱心なファンでした。孤独な離宮での暮らしの中で、いつもあなたの作品を心の拠り所にし……あなた自身に深い恋心を寄せておいででした」
「!」
「それが、契約結婚と称してあなたを第1王子の思惑から守ろうとした――たったひとつの真実です」
ルイノは臆病なイーサンがあまりにも本音を言わないので、焦れったくなったのだと付け加えた。
彼が持ってきたローブとマスクは、つい先日会ったノーブルプリンスマンが身につけていたものだった。
あのときのイーサンのコーヒーのシミはやはり、ウェンディがノーブルプリンスマンに零してできたものだったと理解する。
「殿下はあなたが思うより、ずっと臆病で繊細な方です。秘めた恋心を知られて……軽蔑されるのを非常に恐れておりました」
驚きのあまり言葉をなくす。両手で口を押えたまま、一歩、二歩の後退する。次第に、イーサンのウェンディに対する計り知れない愛情を思い知って、目の奥が熱くなった。
「……私、本宮へ行きます。イーサン様のところに……っ」
「はい。行ってらっしゃいませ」
ウェンディは『嫌われ者の王子様』を手に持ったまま離宮を飛び出していた。国王との面会が終われば戻ってくるが、それまでとても待ちきれない。一分一秒でも早く、あの人に会いたい。
イーサンと国王の面会が終わるまで、謁見の間の外で待っていた。小一時間ほど待っていたら、衛兵が扉を開け、中からイーサンが出てきた。彼がこちらの姿に気づいて反応するより先に、ウェンディは人目もはばからず彼に抱きついていた。
「ウ、ウェンディ!?」
「ルイノさんに全部聞きました。イーサン様が……プリンスマンさんだって……」
「……っ!」
「どうしてそんな肝心なことを隠していたんですか……! 言ってくれたら、エリファレット殿下を意識したり、イーサン様のことを誤解したりしなかったのに……っ」
イーサンはウェンディのことをそっと引き剥がし、彼女が手に握っている本を見やった。ルイノが余計なことをしたなと苦言を呈してから、こちらを向く。
「……ずっとあなたに恋心を抱いていたと知られたら……引かれると思って」
「引いたりしません! だって、だって……私もプリンスマンさんのことが――好きだったから……っ」
彼の顔を見上げるウェンディの双眸から、大きな雫がぽろりと溢れ落ちる。彼は困ったように眉尻を下げて、その涙を指で拭った。
「知ってるよ。僕もまさか、ウェンディ先生に思ってもらえていたなんて夢にも思わなかったけど」
先日、もう会いに来ることはないと最後の挨拶をしに来たノーブルプリンスマンに、ずっと好きだったと伝えていたことを思い出す。
「……もう変装してあなたに会いに行くことはしないと決めていたんだ。恋心も、あなたのファンであることも、胸にしまうつもりで……」
「変装なんかしなくたって、イーサン様が望むならいくらでもお傍にいます……! 私なんかじゃ力不足だって分かってますけど……王妃にだってなります。だから、別れるなんて言わないで! 小説が書けなくなったっていいから……っ!」
「……! あなたが、そこまで……」
大好きな小説を諦めて筆を折ってもいいから傍にいたいのだと切々と懇願すると、彼は息を詰めた。
(私がいなくなったら……またイーサン様がひとりぼっちに……)
ウェンディが願うのはたったひとつ。イーサンが幸せで、笑顔でいてくれることだ。周りの顔色を伺って我慢したり、自分の気持ちに嘘をついたりせずに。
彼の服の袖を掴み、更に畳み掛ける。
「契約結婚をするとき、約束なさいましたよね。契約を果たせたら、なんでも言うことをひとつ聞くって……」
「……ああ、言ったよ」
「なら、今……見返りを要求します。私が対価としてほしいのは――イーサン様です。それ以外のものならいりません! だから、ご自分の心を偽らず、私の質問に答えてください」
ウェンディの真剣な表情に、ぐっと喉を鳴らす彼。ウェンディは震える声で尋ねた。
「イーサン様は本当に……婚姻を解消したいとお思いですか? もし私があなたにとって必要な存在なら……この本を受け取ってください。そしたら私はもう、イーサン様から離れません」
数歩後ろに下がって、ウェンディのサインが入った『嫌われ者の王子様』を両手で差し出す。受け取ってほしかった。いつもサイン会や販売会に来てくれるときと同じように。
試す真似をして悪いとは思いつつ、イーサンの本心が知りたかった。ウェンディに申し訳ないとかそういう気持ちは全部抜きにして。
どきどきと脈拍が加速し、本を持つ手が震える。受け取って、早く受けとって……と心の中で願いながら待っていると、イーサンは片手で本を奪うようにして取り上げ、そのままもう片手をウェンディの頬に添えて、こちらの唇を自身の口で塞いだ。
まるで壊れ物を扱うかのような、優しい口付け。甘くて、暖かくて、泣いてしまいそうになる。長い口付けのあとで、イーサンは熱を帯びた緑色の双眸でこちらを射抜いた。
「――僕の全部をあげるから、傍にいて」
何も持つことを許されなかった、空っぽで孤独な、王子様。そんな彼が唯一差し出せるものはきっと、ウェンディへの愛情で満たされた心なのだろう。
吐息が混じる声は甘く色香をまとっていて、苦しいくらいに胸を締め付ける。彼が自分に恋い焦がれ、求めているのだと目を見て分かった。
ウェンディはそっと瞳を閉じて、了承の意味を込めて自分から唇を重ねるのだった。