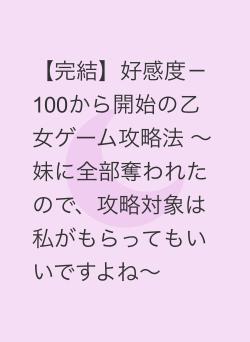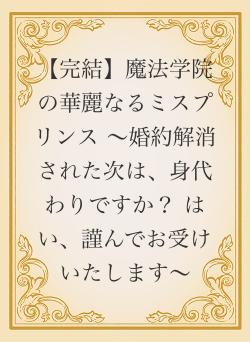婚約破棄騒動からまもない、とある昼。
街の中央の広場に、大勢の若い女性たちが集まっていた。そして、噴水の石造りの囲いの上に立ち、熱心に物語を語る女性がひとり。
休日になると、人気恋愛小説家ウェンディの物語を聞きに聴衆が集まってくるのだ。一般庶民の識字率はそう高くなく、文字が読めない女性たちは朗読を聞きに来るしか小説を楽しむことができないから。
「――嫌われ王子様はおっしゃいました。『一体そなたはどうしたら余の方を見てくれるのだ? そなたのことでどんなに余が想い悩み、眠れぬ夜を過ごしているか知る由もないのだろうな』」
ウェンディは切々とした表情で片手に本を持ち朗読を続ける。
「そして王子様は、夫人の頬に手を添え……強引に唇を重ねます」
「「きゃあああっ!」」
語られるラブシーンに、女性たちから悲鳴に近い歓声が上がった。
ウェンディの物語の中でも、特に人気なのは『嫌われ者の王子様』だ。
題名の通り、王子イザルは最低の嫌われ者だった。見た目だけは国一番と評判だったが、それ以外に取り立てて褒められるところはない。国民の血税で散財三昧、怠慢で努力を嫌い、性根も曲がっている。そして――大の女好き。
既婚者であろうと修道女であろうとお構いなしに取っかえ引っ変え。でも、その美貌ゆえに女性たちは彼を許し愛してしまう。対するイザルは、飽きたらばっさりと付き合いのある女性を切り捨てるので、恨みを買ってばかり。そんな女たらしで最低な美丈夫イザルが、ざまぁされて痛い目を見る話である。
文章を読み終わったウェンディは、ぱたんと本を閉じる。
「もう……イザル王子は本当にろくでもない男ね! ヒロインもこんな男に絶対絆されないで!」
「でも実際、国で一番綺麗な男に迫られたら好きになりそう……」
女性たちは『嫌われ者の王子様』の感想を言い合いながらきゃっきゃと騒いでいる。ウェンディも感想を聞きながら、今後の展開に活かそうと手帳にメモを取る。読者にとっても作者にとっても有意義な時間だ。
「ウェンディ先生! 今週もとっても面白かったです!」
「お楽しみいただけたようで嬉しいです……!」
この瞬間、この光景が大好きだ。自分が誰かの心を動かしたり、誰かの人生に影響を与えられるのは、ウェンディには創作以外には何もないから。『楽しかった』、『面白かった』の言葉がどんなにか励みになる。
(ロナウド様には『くだらん妄想』なんて言われちゃったけど、私にとっては生きがいみたいなものだし、それを楽しんでくれる人がいる)
……という訳で、物語を書くのをやめるつもりは一毛頭ない。ちなみに、人でなし元婚約者ロナウドが痛い目を見る小説は、現在鋭意制作中である。
「また来週も楽しみにしてますね!」
「はい、ぜひまたいらしてください……!」
女性たちは昼休憩を終えて、また家庭に戻っていく。ウェンディの読者は主婦が多いため、エプロンを着けたままの女性が家事を中断して朗読を聴きに来てくれるのだ。
男性は肩身が狭いのかこういう場にはなかなか集まらない。男性客は、ウェンディの記憶の限り――ひとりだけ。彼はウェンディの熱心なファンだ。
手を振って彼女たちを見送っていた次の瞬間――。
「ウェンディ・エイミスはいるか! お前か!?」
「ち、違いますっ」
「ではお前か!」
「あたしじゃないわよ! ウェンディ先生ならあっち!」
広場に王宮騎士団の制服を着た男たちがぞろぞろと押し寄せて来た。女性がこちらを指差し、ウェンディはびくっと肩を跳ねさせる。こちらを振り向いた騎士の男と視線がかち合う。
女性たちは彼らの存在感に圧倒され、逃げるように広場から離れていく。ぽつんとひとり、ウェンディだけが取り残される。
「――お前がウェンディ・エイミスか?」
一体何が起きているのか理解が追いつかず、ぽかんとするウェンディ。威圧的に睨まれて、萎縮しながら答える。
「……そう、ですけど」
自分がウェンディだと認めると、騎士のひとりがウェンディの手首に手錠をかけながら言った。
「お前に国家反逆罪の容疑が出ている。大人しく投降しろ!」
「こっかはんぎゃく!?」
思わず声が裏返る。なんだかとてつもないパワーワードが降ってきて、目を見開く。
(はぁぁぁぁ!? どういうことなのよーー!)
全くもって意味不明だ。今日この日まで盗みもせず、人の悪口も滅多に言わず、善良に生きてきた市民が――国家反逆罪? そんなはずはない。これは誤解だと騎士に訴えるが、彼らは頑としてウェンディに耳を傾けようとはしなかった。
引きずられるように広場から連れて行かれ、移送馬車に詰め込まれる。その様子を、人々は遠巻きに唖然と眺めていた。
◇◇◇
「終わった……私の人生、完全に詰んだ……」
移送馬車に揺られながらウェンディはひとり、ぼそぼそと呟く。手錠で拘束された手で頭を抱えた。
(国家反逆とか、ナイナイ。ありえないでしょ!)
捕まってからの二時間、生まれて自我が芽生えてからの今までの人生を振り返ってみた。
ウェンディだって人間だから、時には惰眠を貪ったり、仕事を後回しにしたり、お菓子を夕食の前につまみ食いしたり、ちょっとした悪いことはしてきた。――でも。国家反逆などという、一発で首が飛ぶような悪いことはした覚えがない。本当に、ウェンディの人生は部屋に閉じこもって本を読んだり書いたりするだけだったのに。
そんなことを考えてるいるうちに、馬車は到着した。留置所や裁判所ではなく、到着したのは――王宮。
訳も分からないまま、騎士に馬車を下ろされ連行される。ウェンディは恐怖でだらだらと汗を垂れ流していた。
「ど、どこに連れて行くつもりですか?」
「無駄口を効くな。黙って着いてこい」
「ひっ、はい分かりました! 黙ります! ただちに、至急、速やかに……!」
乾いた笑みを浮かべてそう返す。覚束ないあしどりのまま、荘厳豪華な王宮内を引っ張られ、放り込まれたのは広間だった。王族を含めた上流階級が社交の場に使うような贅沢な空間で、頭上に大きなシャンデリアが輝いている。
へたり込んで両手を床に着けると、白い大理石に自分の情けない表情が写っていた。
(……これから、どうなっちゃうんだろう)
きゅっと唇を引き結ぶ。たとえ冤罪だったとしても、国家反逆罪が確定したらまず命はない。下級貴族であるエイミス男爵家は一族もろとも根絶やしにされるのだ。
不安が込み上げてきて、じわりと目に涙が浮かんだ。そのとき、広間の奥から靴音が近づいて来た。
「ずっと会いたかったよ。――ウェンディ先生?」
身をかがめてこちらに囁いたのは、ウェンディが今まで見てきた中でとりわけ美しい青年だった。さらさらとした絹のような金髪に、完璧に整った顔立ち。緑色の瞳は、水分量が多いのかやけに光っているように見えた。年齢はウェンディよりは少し下だろうか。『ウェンディ先生』と呼ぶ声も、清涼水のように爽やかで綺麗だ。
(ずっと会いたかったってどういうこと……? それにこの声、どこかで聞いたことがあるような……)
懐かしいような、よく聞き慣れたような、そんな声。けれど、こんなに派手な見た目の人なら、一度でも会っていれば忘れないだろう。彼とは初対面のはず。
会いたかったとはどういうことですかと尋ねると、彼はこちらと目線を合わせるようにしゃがみ、ウェンディの顎を指で持ち上げた。
「ずっと顔を拝んでやりたかったんだ。この僕を――第3王子イーサン・ベルジュタムを侮辱した小説を書いたのがどんな人なのかね」
「侮辱する、小説……?」
イーサンは一見人好きのしそうな笑顔を浮かべているが、その瞳は全く笑っていない。ごくんと固唾を飲むウェンディ。彼は、顔を覗き込むように近づいてくる。
「とぼけても無駄さ。あなたの著作『嫌われ者の王子様』の主人公イザルは――勝手に僕をモデルにしているでしょ?」
想定外の疑いに、目を瞬かせた。
「いや……してませんけど」
これが、ウェンディの運命の出会いだった。彼女の物語のような恋が動き出しているのを、本人はまだ――全然気づかない。