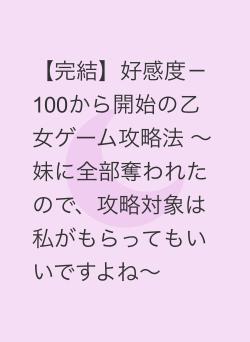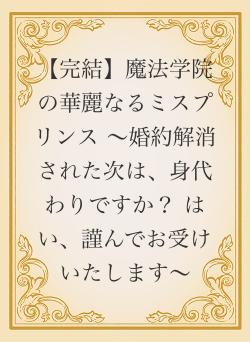ウェンディはある日、離宮の庭で物思いに耽っていた。手入れが行き届いた青々とした芝生の上に座り、ただぼんやりと景色を眺めて時を過ごす。
茂みが広場を囲っており、数本の落葉樹がぽつぽつと立っている。
ウェンディは木の根元で木漏れ日を浴びながら、本を読むのが好きだ。今日は膝に本を置いてはいるが、気が散って文章を読む気にならない。
(……どうしてイーサン様の服に……コーヒーのシミが)
先日、街でばったり会ったイーサンの服に、ノーブルプリンスマンと同じシミができていた。ウェンディは嫌われ者の王子イーサンと、熱心なファンノーブルプリンスマンの存在を初めて結びつけて考えるようになった。
もしイーサンがノーブルプリンスマンだったなら、ウェンディを助けようとしたことにも納得がいく。そして、ノーブルプリンスマンが最近結婚した愛する相手というのは……。
かっと顔が熱くなるのを感じて俯くと、上から声をかけられた。
「ここにいたか。ウェンディ」
「……! エリファレット殿下……」
エリファレットはごく自然にウェンディの隣に腰を下ろして、体を近づけてきた。ウェンディは警戒しながらそっと距離を取る。
「……もうこちらにはお越しにならないようにとお伝えしたはずですが」
「2人のときは敬語はやめろと言っただろう?」
「それを承諾した覚えはありません」
冷たく突き放すと、エリファレットは困ったように眉尻を下げた。彼はウェンディの輿入れのあと、イーサンの外出中のタイミングを狙って度々離宮を訪れるようになった。
最初は、困ったことがあれば力になると親切に声をかけてくれていたが、次第にイーサンの悪口を口にするようになり、自分とこっそり付き合わないかと誘ってくるようになった。
けれどウェンディは知っている。エリファレットがノーブルプリンスマンの名前を騙って近づき、ウェンディに取り入って自分の名誉を取り戻すための小説を書かせようとしていることを。ロナウドと破局するように仕向けた張本人がこの人であることも分かっている。
(……困ったなぁ)
エリファレットに言い寄られていることをイーサンに相談しようか悩んでいるところだった。しかし、イーサンはこの王宮内で立場が低く、この件で兄に強く言えないことは分かっている。だから、イーサンに迷惑をかけないようにするためには、自分が我慢している方がいいのではないかと思っていた。
「相変わらずつれない人だな。ウェンディは」
「…………」
優しくて親切な態度も、ウェンディの気を引くための嘘なのだ。
彼の言葉を無視して本を開き、読むふりをはじめると、彼はそれを取り上げた。本を適当に後ろに置いて、こちらの顔を覗き込む。
「そんなつまらない本より、もっと楽しいことを教えてやろうか」
「――つまらない本? 殿下は大衆小説がお嫌いなんですか?」
「ああ。嫌いだ。下々の者が楽しむいやしい書物だからな」
「私が書く本も大衆小説ですよ。プリンスマンさん」
大衆小説は、俗っぽいと高貴な階級からは軽視されている。しかしもしエリファレットがノーブルプリンスマンなら、絶対にこんなことは言わない。
「い、いや……お前の本はその……例外だ」
慌てて言い訳する彼に、冷ややかに告げる。
「あなたは――偽物ですよね。エリファレット第一王子殿下。ノーブルプリンスマンはあなたじゃない。私の本を政治利用しようとしているというのは、本当ですか?」
すると、それまで穏やかだった彼の表情が一気に変わる。底冷えするような眼差しに射抜かれた。
「誰に聞いた? イーサンか?」
「さぁ、内緒です」
「ああ……そうだ。お前の言う通りだ。お前に俺を賛美するプロパガンダ小説を書かせて、世間に宣伝するつもりだった。この国の王にふさわしいのは――この俺だと」
ウェンディはふっと乾いた笑いを零して、彼を挑発的に睨んだ。
「そんなずるいことをせずに、自分の力で努力すべきです。いくら私に取り入ろうとも、協力はしかねます。もうこちらにはいらっしゃらないでください。……イーサン様が不安になるので」
すっと立ち上がり、彼にはっきりと伝える。ここまで言えば彼も諦めるだろう。そう思って庭を離れるが、その後ろ姿をエリファレットは怖い顔をして見ていた。
「……お前もイーサンと同じことを言って俺を貶すのか」
エリファレットは怒りと焦りに拳を固く握り締め、立ち尽くした。
◇◇◇
「父上。どうか今一度お考え直しを……!」
「いいや、考えを変えるつもりはない。王位継承順位第1位は――イーサンに与える」
ウェンディにもう会いに来るなと言われた直後の、王宮の謁見の間。エリファレットは国王の前で跪き、頭を下げて懇願していた。
国王から告げられた言葉に、下唇を噛む。
(……ついにこの日が来たのか。クソっ……)
3人の王子は、イーサンが王太子になるという旨を伝えられた。イーサンはその意向に驚き、どうしてカーティスではなく自分なのかと目を見開いている。
問題を起こしたエリファレットから、第2王子に王位継承権を渡し、王太子に即位させるはずだった。しかし、国王は当初から、イーサンに王位を継がせる意思があったのだ。――なぜなら、イーサンこそ、この国で唯一の正統な王位継承者の血筋だから。
その事実はこの場で、国王とエリファレットしか知らない。
何も知らないカーティスが、なぜなのかと尋ねる。
「王妃を含め、そなたたちはイーサンを随分と軽んじて参ったな。……婚外子だからと」
「……ですが、国教において不貞は穢れとされます。イーサンが世に出るべきではなかったというのは……王家の総意です」
「では――世に出るべきではなかったのは、そなたたちの方ということになる。エリファレット、カーティス」
「……! 一体、それはどういう……」
国王は長い髭をしゃくりながら語った。なぜ国王が、周囲の反対を押し切ってまでイーサンを廃位せずに、王子としていたのか……。
「イーサンは不貞でできた子ではない。正統なこの国の王子だ。しかしそなたら2人は……私の子ではなく――死んだ王弟の子だ」
「ま、まさか、母上が不貞を犯したとでもおっしゃるのですか!?」
「ああ、そうだ」
国王と王妃ルゼットの間に、子どもができることはなかった。ルゼットには別の想い人がおり、国王を避けていたからだ。
その想い人、愛人が今は亡き王の弟だった。国王の子を産むのは拒んだのに、王弟の間に双子を授かった。それが、エリファレットとカーティスだった。
国王は、妃と弟が不義理を働いていたことを嘆いた。けれど、2人の名誉を守るために、双子を自分の子どもとして育てることにした。
しかし、ルゼットは悪びれもせずに長い間国王を避け続けた。正統な自分の血を引く世継ぎがほしかった国王は、ルゼットには言わずに第2妃を迎い入れた。第2妃はイーサンを授かったが、自分の子が王位を継ぐものと思っていたルゼットは、彼女が跡継ぎを授かったことに激昂した。
自分と王弟の子どもを王にしたいという野心があったルゼットは、第2妃に毒を盛って殺しかけた。しかし証拠が見つからず、ルゼットを処断することができなかったが、再び第2妃が狙われるかもしれないと危惧した国王は、第2妃を病死したことにして王宮の外に逃がして子を産ませた。
そして第2妃は、毒で体が弱っていたためか、イーサンを産んですぐに他界した。
「……では私は……娼婦の子ではなかったのですか」
「そうだ。そなたは……余と死んだ第2妃の子だ」
イーサンは隣で絶句している。
第2妃が死んだ数年後、イーサンは国王と娼婦の間にできた婚外子として王宮に連れ戻された。国王はルゼットからイーサンを守るために離宮に追いやり、ルゼットに息子が冷たく扱われることを黙認していた。
ルゼットは、イーサンが第2妃の子であることに気づいていた。しかし、王位継承順位1位は依然として自分の子どもにあったので油断し、殺さずに放任していたのだ。
エリファレットは固く拳を握り締めた。
(王位なんて誰が継ごうとどうでもいい。……俺はただ……あいつを守れたらそれで……)
エリファレットは何も知らないカーティスと違い、自分が半分偽物ということも、イーサンが正統な王位継承者ということも全て知っていた。だから、イーサンのことが気に食わなかったし、忌まわしい血を引く自分がのうのうと王座に据わることも嫌だった。
だから好き勝手生きて、自分以外の誰かに王位継承権が移ればいいと思っていた。
しかし、頭の中にラティーシナの姿が思い浮かんで、エリファレットは唇を引き結んだ。
◇◇◇
3人の王子がイーサンの即位の話を聞いたあとの、リューゼラ侯爵邸。
そこではウェンディの元婚約者ロナウドと妻のルリア、そして彼女の家族が暮らしている。
「よくも俺を騙してくれたな。こんな金額の借金、一体どうする気だ!?」
「ロ、ロナウド様がなんとかしてくださいまし……!」
「人任せな女だ。借金の話を知ってたら、結婚なんてしなかったのに」
「……! わたくしだって、エリファレット殿下に言われなければあなたなんかに近づいたりしなかったわ!」
広い屋敷の居間で、ロナウドはルリアと揉めていた。彼女はずっと実家に借金があることを隠してロナウドと交際していた。
ロナウドは彼女に惚れていたが、ルリアにはこちらへの愛情などはなく、借金返済のことしか頭になかったというのだ。
(おまけに彼女は厄介な癇癪持ちだった。つくづく俺は運がない)
今も彼女の甲高い怒鳴り声が鼓膜に響いてくる。ロナウドは手で頭を押さえて呟いた。
「またその名前か。――俺とあなたが結婚したら、どうして第1王子が借金を肩代わりしてくれることになるんだ?」
「分から……ないけど、確かにそうおっしゃったのよ!」
ルリアが好きでもないロナウドに略奪愛をしかけたのは、エリファレットにそそのかされたからだった。……なんでも、ロナウドを籠絡してウェンディから引き離すことができたなら、借金を完済してやると言ったとか。
公開婚約破棄までしたせいで、ロナウドは逃げ場をなくしているが、それすらエリファレットの意向だった。
(第1王子の目的はなんだ? ウェンディに惚れている? いや、まさか……)
第1王子といい、第3王子といい、高貴な王族がウェンディに固執する理由が見えてこない。
しかし、仮にルリアの言葉が事実だったとしても、エリファレットは約束を果たしていない。ルリアに条件をこなさせておいて裏切ったのだ。きっとルリアも藁にもすがるような思いだったのだろうが、いいように利用されただけ。
「それで? 第1王子は何かしてくださったか? 結局騙されたじゃないか」
「そ、れは……」
彼女が何も言い返せずに口を噤んだそのとき、居間の入り口から別の声がした。
「随分と楽しそうだな。新婚早々喧嘩か?」
「エリファレット殿下……!?」
「――例の約束、果たしに来てやったぞ」
後ろに騎士をつき従えたエリファレットは、無断で部屋に押し入って来た。茶化すように笑っているが、誰のせいでこんなことになっていると思うのだろうか。
苛立ちを隠しながら礼を執ると、彼はごく自然に中央のソファに腰を沈めた。
「ここは客人に対して茶も出ないのか?」
「気が利かずに申し訳ございません! ほら、すぐにご用意を!」
ルリアは大慌てで侍女に命令する。
「は、はい……! お嬢様」
侍女が大慌てで飲み物を用意しに部屋を出る傍らで、ロナウドは内心、勝手に屋敷に上がり込んでおいて謝罪のひと言もない彼のふてぶてしい態度に不満を抱いた。
(礼儀がなっていないのはどっちだよ)
エリファレットは茶を飲み、「ぬるい」と姑のような文句を口にしながら、ここに来た理由の詳細を話した。
「……つまり、本当に借金を返していただけるのですね」
ロナウドには、多額の借金を返していく甲斐性はなく、領地をうまく経営していくような腕もない。だが、王室の財産を使ってくれるなら、苦労せずとも一瞬で完済できるだろう。
「ただし、ひとつ条件がある。もう少しお前たちが頑張らなければ――この話はなしだ」
「「…………条件」」
ロナウドとルリアは顔を見合わせる。最初に提示してきた条件はすでにルリアが満たしているのに、追加て要求してくるのはずるいだろうと。しかし、2人は彼を頼るしかない弱い立場だった。
「――ウェンディ・エイミス誘拐に協力しろ」
固唾を飲んで言葉を待っている2人に、とんでもない内容が提示された。