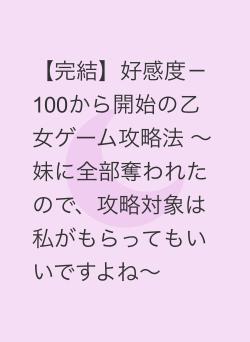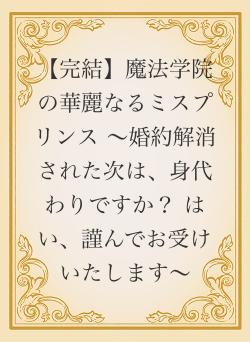ノーブルプリンスマンとの出会いからいくつも季節が巡り、いつの間にかウェンディは第3王子の妻になっていた。ウェンディが嫁いだ同時期に、不思議とノーブルプリンスマンがウェンディの元に通わなくなった。
(プリンスマンさん……どうしてるんだろう。元気にしてるかな?)
とある休日、ウェンディは街で世話になっている書店のサイン会に出かけていた。書店は女性読者たちで大行列ができていて、店の裏口から入ると、高齢の店主が満面の笑みで擦り寄ってきた。
「よく来てくれたねぇウェンディ先生。先生のおかげでうちは大繁盛だよ。いやぁ、先生が売れる前から縁を結んでおいたわしの目利きに間違いはなかった! 先生は他の作家とは違う……こう……煌めく才能を感じておったんじゃ!」
「まぁよく言う。私が何度も頭を下げてやっと本を並べてくれたじゃないですか」
「はは、そうだったかのぅ? 年寄りは物覚えが悪くてかなわんな」
「そういうときだけ年齢を出すのずるいですよもう。私、まだ根に持ってるんですからね。初めての販売会で、どうせ誰も来ないから諦めて帰れっておっしゃったの!」
その日のことは今もよく覚えている。大雨の日で、誰もいない閑散とした書店でひとりぽつんとお客さんが来るのを待っていたのを。あの日が、ノーブルプリンスマンとの出会いでもあった。
「でも結局、ひとりしか来なかったじゃないか」
「やっぱり結構覚えてるじゃないですか」
「さぁ〜都合の悪いことは全部忘れるようになっとるんじゃよ。最近ぼけも始まってねぇ」
店主は伸びた髭をしゃくりながら、とぼけた顔をした。憎らしさ据え置きの老人店主だが、長い付き合いがあり、ウェンディの本を置くための専用の棚も作ってもらっているので、感謝はしている。王都の中心に店を構え、立地がいいのでサイン会をするときは、いつもここを借りている。
店主はエプロンのポケットから栞やブックカバーといった、ウェンディの作品をイメージして特注で作ったグッズを取り出しにやにやと笑う。
「さ。今日もお嬢ちゃんの作品にあやかって稼がせてもらうとするかのぅ」
最近、彼の孫が学校に入学したとかで、費用をいくらか負担するつもりでいるらしい。
(何がぼけ始めてるよ。まだ頭はキレッキレのように見えるけど)
ほっほと笑いながら、彼はスタッフルームから店へと消えていった。
まもなく、店主が傍らでウェンディの本と特製グッズを売り捌く中、サイン会が始まる。
「いつも先生の本を読んでます!」
「わ……嬉しいです。ありがとうございます!」
「これからも頑張ってください! 応援してます!」
「はい! 頑張ります……!」
ウェンディのファンはほとんどが女性だ。中には男性のファンもいるだろうが、こういう交流の場に出てくることはない。女性たちばかりで気が引けるのだろう。ひとりの例外、ノーブルプリンスマンを除いて。
(やっぱり今日も来ない……。病気とかだったら……心配だな)
今まで、サイン会には欠かすことなく来てくれていたのに。
(それとももしかして……私の作品、飽きられちゃったのかな)
どんなに夢中になっていたものだって、飽きが来ることがある。仲が良かった恋人に冷めてしまい、別れることがあるように。
こればかりは理屈ではどうにもならないし、止める方法はない。もう自分の作品がノーブルプリンスマンが読まなくなって、二度と会いに来ないのではないかと想像すると、寂しさが胸に広がった。
「最後の方〜中へどうぞ」
店主に促され、ウェンディの前に現れたのは――待ち焦がれていたノーブルプリンスマンだった。
「お久しぶりです。ウェンディ先生」
「プリンスマンさん……! こんにちは」
全身をローブで覆いフードを被っており、口元も隠している。身分を隠していることを最初は疑問に思っていたが、何か事情があるのだと思って詮索はしてこなかった。今はもう慣れたものだが。
マスクで表情はよく見えないが、優しげな雰囲気が目元から伝わる。
(あれ……この目元、誰かに似ているような……)
一瞬そんな思いを巡らせていると、ノーブルプリンスマンの声に意識を引き戻される。
「しばらくお会いしてませんでしたが、元気でしたか?」
「はい! ありあまるくらい元気ですよ! まぁ……色々あったんですけど……。それよりプリンスマンさんは? 病気でもしたんじゃないかってすごく心配していたんです」
「僕も実は……色々あって」
『ノーブルプリンスマン』を宛名にサインを書き終えて渡すと、ちょうど持ち時間が終わり、彼が店主に下がるように促される。
「あの、ウェンディ先生!」
「……どうかしました?」
「この後少しお話しませんか? 報告したいことがあって」
彼はちょうど最後尾だったので、ウェンディの仕事はもうここで終わりだ。誘いを快く承諾すると、彼は「外で待っています」と言って書店を出て行った。
◇◇◇
急いで支度をして書店の外に行けば、彼は壁にもたれかかりながら、ぼんやりと空を見上げていた。憂いを帯びた眼差しが、やはり似ている。
(……こうして見ると、イーサン様にそっくりな目……)
ウェンディはそっと彼に声をかけた。
「お待たせしました! 近くに公園があるので、そこで話しましょうか」
「はい。お時間をとってしまいすみません」
「そんなそんな。お気になさらず」
2人で10分ほど歩き、湖畔にある公園に着いた。屋台で買ったホットコーヒーを片手に、ベンチに腰を下ろし、鳥たちの囀りを遠くに聞きながら話をする。
「報告したいことって……なんですか?」
「個人的なことなんですが、実は僕……結婚しまして」
「!」
彼から告げられた『結婚』というワードに戸惑い、カップを落とす。
「大丈夫ですか? 火傷は……」
「平気です。それよりプリンスマンさんのローブが汚れちゃいました。シミになっちゃう……」
「構いません。ウェンディ先生に怪我がなくてよかった」
ウェンディは慌てて濡れた場所をハンカチで拭きながら、謝罪した。それから、結婚の報告について詳しく聞く。ウェンディのところに今日こうして来たのは、妻を不安にさせないようにするために、女性作家であるウェンディの元にはもう通わないと伝えるためだった。サイン会も、朗読会も、販売会も、全て。
「……なるほど。報告ってそういうことだったんですね」
ウェンディはそっと胸に手を当てた。
(思ったより痛くない。――失恋の痛み。もっと苦しいものかと思ったのに)
ノーブルプリンスマンに密かに恋心を抱いていたときのことを思い出す。自分は作家で、彼はファンのひとり。彼にも生活があって、いつか誰かと結婚するのだろうと漠然と考えていが、当時は自分から彼が離れていってしまうのをどこかで恐れていた。
今、思ったよりもショックを受けていないのは、きっとイーサンの存在があるせいだ。
「とにもかくにも、ご結婚おめでとうございます。良かったですね」
「……ありがとうございます」
「どんな方なんですか? その……奥さんは」
彼は愛おしい存在を思い出すように目を細める。
「僕にはもったいない、素敵な人です。綺麗で、純粋で……。好きなことに夢中になって、きらきら輝かせる瞳が特に……魅力的です」
「へぇ……とても愛していらっしゃるんですね」
「はい……とても」
ウェンディはベンチから伸ばした脚を揺らしながら、「そっかぁ」と感慨深げに呟いた。
「……プリンスマンさんにお会いできなくなるのは寂しいですけど、幸せを願ってます。心から」
「僕もです。これからも本は絶対買いますし、応援しています」
ノーブルプリンスマンの結婚報告だったが、自分もつい最近結婚したのだと伝えると、彼は相手までよく知っていた。
「ご存知でしたか」
「有名な話ですから」
王族の婚姻は、国を上げての重大イベントだ。いくら婚外子とはいえ、イーサンは王族。結婚したことを知らない国民はいないだろう。
「……第3王子殿下は評判がよくないですし、先生が心配です」
「それは誤解です!」
ベンチからすっと立ち上がり、必死に擁護する。血筋のせいで世間では色々とひどいことを言われているけれど、イーサンは素敵な人なのだと。ウェンディの一生懸命な姿を、ノーブルプリンスマンは意外そうな顔で見ていた。
「……最近、ようやくイーサン様のことが分かってきたような気がするんです。最悪な出会いだったんですけど、今はなんていうか……あの方の力になりたいと思っていて……」
「そう……ですか」
そして、イーサンに対する恋愛感情が芽生え出している。そのことは口にはしなかった。
しばらく2人で取るに足らない話をしていたら、いつの間にか日が随分傾いていた。
2人は帰ることにし、名残惜しい気持ちを残しつつも、彼に微笑みかけた。
「……今まで応援してくださって、本当にありがとうございました。プリンスマンさんの存在は、私にとって大きな励みになっていました」
「それは……僕の方です。ずっと孤独で、つまらない毎日に、彩りを与えてくれたのは先生の本でした。あなたは最後まで……僕の正体をお聞きにならないんですね。こんな怪しい格好なのに」
ウェンディは小さく頷く。
「あなたは私の大切なファンです。あなたがたとえいじめっ子でも、犯罪者でも――嫌われ者でも構いません」
「嫌われ者でも?」
「はい。嫌われ者でも」
その刹那、彼の美しい緑の瞳の奥が揺れた気がした。
「ありがとう。それじゃ僕はもう行きます」
「待って!」
背を向けようとする彼の袖を摘み、引き止める。
「……最後だから、心残りがないように言わせてください。本当の名前も、身分も年齢も、何も分からないけど……私、ずっとプリンスマンさんのことが好きでした。――男の人として」
「…………っ!」
声が震える。彼の袖を掴んでいる指先も小刻みに震えていて、やけに冷たい。顔は沸騰するように熱くて、きっと赤くなっているだろう。
しかし、これで会うのが最後なら、伝えなくてはどこかで後悔してしまう気がしたのだ。
ノーブルプリンスマンは、驚いて目を大きく見開いた。……ウェンディが好意を寄せているなんて思わなかっただろう。
「でもそれもいい思い出です。今は……旦那様のことが好きだから。今日プリンスマンさんに会って、気づけました」
一歩二歩と俯いたまま後ろに下がり、「奥様とお幸せに。さようなら」と最後の挨拶をする。ぺこっとお辞儀し、背を向けて走り去るウェンディ。緊張しすぎて反応を確かめる余裕はなかったが、心はすっきりしていた。
――そして。
ノーブルプリンスマン改めイーサン・ベルジュダムは、ウェンディの後ろ姿を見送りながら呆然と立ち尽くしていた。震える手を伸ばして布マスクを外す。イーサンの陶器のような白い肌は、耳まで真っ赤になっていた。
今日、イーサンは二度告白されたことになる。一度は、ウェンディの熱心なファンノーブルプリンスマンとして。そして二度目は、仮の夫として。
「夢、みたいだ……」
その呟きは、公園の葉揺れの音に掻き消された。