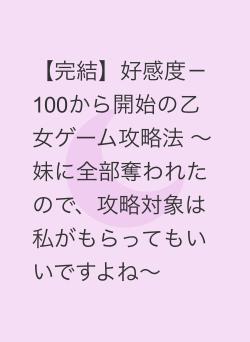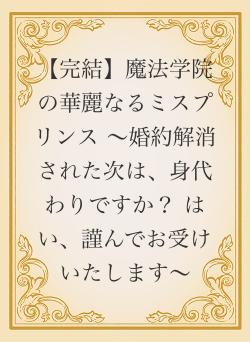離宮へ帰ろうと思い、扉を閉めようとしたが、扉の間に頭が挟まって――ごんっと鈍い音が響く。不注意な主人の様子に、ルイノが呆れて額に手を当てた。
「――誰だ!」
ルゼットの声とともに、室内の護衛騎士たちが警戒態勢に入る。このまま立ち去る訳にはいかなくなり、渋々サロンに顔を出すイーサン。
「イーサン様……! どうしてこちらに?」
笑顔を浮かべて駆け寄ってくるウェンディ。優しく向かい入れてくれたのは彼女ひとりで、ルゼットを含めた貴婦人たちは氷のように冷たい表情でこちらを見ていた。ルゼットはすっと椅子から立ち上がり、こちらに歩いてきた。
「なぜお前がここに来た。許可した覚えはないぞ」
「……妃が遅くになっても帰って来なかったので、心配になり参りました」
「はっ、その口ぶりではまるで私が信用ならないようではないか」
「け、決してそういう訳では……」
サロンの中に緊迫した空気が漂う。ルゼットは大きくため息を吐き、ウェンディの方を振り向いた。
「興が冷めた。話の続きはまた聞かせてくれ。今日は大変有意義な時間であった」
「恐悦至極にございます。お呼びいただければいつでも来ます」
ウェンディは恐縮した面持ちでお辞儀をする。するとルゼットはテーブルの水の入ったピッチャーを手に取り蓋を開けて、イーサンの頭上でそれを――ひっくり返す。水が降り注ぐ瞬間、ウェンディがイーサンを抱き締めて背中で庇った。
彼女の服は水でずぶ濡れになる。しかし、濡れたことはお構いなしで、王妃のことを悲しそうに見上げる。
「……なぜ、なぜイーサン様を忌み嫌うのですか……? どうして、そこまで……」
ウェンディの長くウェーブのかかったベージュの髪から、ぽたぽたと水が滴り落ちる。彼女に対して、ルゼットは地を這うような声で告げる。
「その者は――生まれてくるべきではなかった」
「…………!」
絶句するウェンディ。ルゼットはイーサンに視線を向けた。
「度胸があり才能に溢れる良い妃を娶ったな。お前ごときには到底不釣り合いに見える。早く出ていけ。私の部屋にお前がいるだけで虫唾が走るのだ!」
「……申し訳ございません。王妃様」
イーサンは茫然自失となっているウェンディの手を引き、王妃のサロンを後にした。
◇◇◇
王妃主催のお茶会に、イーサンが迎えに来てくれた。昼から夜まで立ちっぱなしで、必死に思考を巡らせて物語を考えたせいで疲れきっていたので、彼の顔を見た瞬間、心底安心した。
(イーサン様……私のことを心配して来てくださったんだ)
それと同時に、彼がルゼットに深く憎まれていることを再び思い知ることになった。イーサンを見つめる瞳は強烈な憎悪を孕んでいた。どれだけの罪を犯したら、人は人をあそこまで嫌いになれるのか疑問に思うほど。
「すまない。僕のせいでせっかくのドレスが濡れてしまった」
サロンを出てから、彼はハンカチでドレスを拭いてくれた。ハンカチ1枚では拭いきれないほど濡れてしまっており、せめて体を冷やさないようにと上着まで貸してくれた。
2人で広い王宮の庭を歩き、王宮へと向かう。
(う……足、痛い)
ずっと立ちっぱなしだったせいで足がひどく痛み、ウェンディの歩みは明らかに遅かった。よちよち歩きに気づいたイーサンは、近衛騎士のルイノを荷物を持たせて先に離宮に帰らせ、ウェンディの前に背を向けて身をかがめた。
「乗って」
「そ、そんな……! イーサン様におぶらせるなんてできません!」
「ずっと立っていて疲れてるんでしょ。その亀みたいな速さだと、離宮に着くまでに夜が明けるよ」
「でも……」
「僕がそうしたいんだ。ほら」
ウェンディはしばらくの逡巡の末、彼の言葉に甘えることにした。彼の背に体を預け、首に手を回す。イーサンはすらりとした体型に見えるけれど、意外としっかりしていて、ウェンディを軽々と背負った。
夜の風が優しく頬を撫でる。遠くの茂みから、夜虫が鳴く声が耳を掠めた。すると、不意に彼が言う。
「ありがとう、ウェンディ。僕なんかを庇ってくれて。味方になってくれて」
「僕なんかなんて……言わないで」
「……ウェンディ」
「あなたは生まれてくるべきじゃなかった存在ではありません。絶対に」
今もなお、ルゼットの言葉が耳に焼き付いていて、悔しくて目に涙が滲んだ。本当は、ほんの少しだけ期待していた。ルゼットや他の王族とイーサンが和解できる日が来るのではないかと。嫌われているというのは、イーサンの思い込みの部分があるのではないかと。
けれど、彼と王族の間にできている軋轢は、修復できるような段階ではないのだとよく分かった。分かってしまったから、どうしようもなくて、悲しい。
ウェンディは鼻をすすりながら、イーサンにぎゅっとしがみつく。泣いていることを察した彼は切なげに呟いた。
「またあなたを泣かせてしまった。……僕は夫失格だな」
「あなたが大切だから……涙が出るんです。イーサン様は私に誠実でいてくださっています」
「……いや、僕は不誠実なやり方であなたを妻にした。――沢山の嘘をついて」
「嘘……?」
思いに耽るように黙ってしまう彼。言葉の続きを待っていると、重々しく打ち明けられる。
「契約結婚は、僕が叙爵式を迎えるまでだと言ったけど……僕が爵位を与えられ賜姓降下する日は来ない。僕は一生離宮を出られないから。――それが、王家の意向だ」
「…………」
「僕はあなたを騙していた。……すまない」
契約結婚が始まってから、ずっと違和感を感じていた。賜姓降下の条件が妻帯者であること、というのが最初に彼から聞かされていた話だったが、ウェンディが輿入れしても一向に叙爵の話が出なかったから。
「僕のことは恨んでくれて構わないから」
「恨みません。……むしろ心配です。本心をどこかに隠して、おひとりで抱え込んでばっかりのあなたが」
イーサンは自分のことをほとんど話したがらないが、今までの付き合いで、この結婚には特別な事情が別にあるのではないかと考えていた。脅してまで籍を入れなければならないような……特別なワケが。
彼に背負われたまま言葉を紡ぐ。
「イーサン様は、謝るばかりで……肝心なことは話してくださいませんよね」
彼は不器用で、思っていることを誰かに伝えるのが苦手だ。周りから抑圧される環境で育ってきたのだから、無理もない。
「あの求婚には何か、事情があったのでしょう。大人しくひっそり生きてこられた優しいイーサン様が、権力を振りかざして脅してまで結婚するなんて変です」
「……!」
「言いたくないのなら言わなくていいです。ただ私が、イーサン様を信じていることだけは知っていてください」
そう言うとイーサンは立ち止まり、近くのベンチにウェンディを座らせた。こちらを見下ろしながら、彼は切なげに零す。
「今……言うよ。僕があなたに求婚した理由」
少し間を開けて、彼は言った。
「――あなたを守りたかったからだ」
そしてそれは、ウェンディを政治利用しようとするエリファレットからだった。
エリファレットはウェンディに自分を賞賛する小説を書かせて求心力を上げ、第2王子に渡ることになった王位継承順位1位を取り戻そうとしていた。それに気づいたイーサンは、ウェンディと籍を入れ、王子の妃という肩書きで庇護しようとしたのだ。
「どうして、イーサン様が見ず知らずの私のためにそこまで……」
ウェンディがイーサンに会ったのは、あの求婚の日が初めてだった。彼がそこまで心にかけてくれる理由が思いつかない。
イーサンは首を横に振った。
「……あなたに打ち明けられるのはここまでだ。全て話して……あなたに失望されたり軽蔑されるのが怖いから。ウェンディに嫌われるのは……僕にとって耐えがたいことだ。……臆病な僕を許してほしい」
そう呟く彼の唇は震えていた。
ウェンディを守るために、エリファレットより先に結婚した。それが分かっただけで今は十分だ。彼がウェンディを大切に思っていることが分かっただけで。
イーサンは勇気を振り絞って秘密を話してくれた。怯えながら心の内を打ち明けてくれた彼がいじらしく思えてくる。手を伸ばして彼の手を握った。
「……そんなに怖がらないで。私、イーサン様のことを嫌ったりしません。最初は身勝手な人なのかなと思っていたんですけど……今は好きですよ。あなたのこと」
「〜〜! ……僕のことをそんなに喜ばせて、一体どうする気だ?」
親指の腹で彼の滑らかな手を撫でたそのとき、イーサンの顔がぼんっと赤くなる。その様子がなんだかおかしくて、ウェンディはくすくすと笑った。