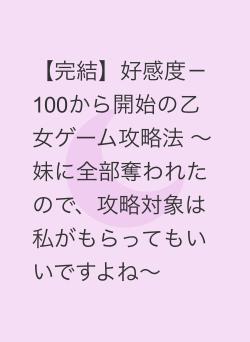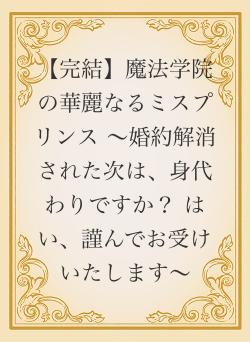「本日はお招きいただき、誠にありがとうございます」
本宮のサロンには、すでに大勢の貴婦人が集まっていた。大きな円卓を囲うように座っており、真ん中にルゼットがいた。彼女はウェンディを冷たく見据え、口の端だけ持ち上げた。
「よく参ったな。早く朗読を始めてくれ」
「は、はい。もちろんでございます」
ウェンディは頭を下げて、テーブルに向かう。けれど、どの椅子もすでに使われていてウェンディが座れる席が見つからない。すると、貴婦人たちはくすくすと嘲笑し始め、そのうちのひとりがサロンの壁際を指差した。
「あなたの席は――あっちよ、あっち」
「…………」
つまり、壁際に立ったまま物語を語れということだ。第3王子妃という地位が認められながら、座ることも許されないとは。けれど、ウェンディは不満を一切出さずににこりと微笑んだ。
「――分かりました」
言われた通りに壁際に立って、持ってきた本の朗読を開始する。しかし、誰ひとりとして、ウェンディの話に耳を傾ける者はいなかった。まるでウェンディがいないかのように無視している。
「それでね、うちの主人ったら――」
「へぇ……そうなの。大変ねぇ」
お茶を飲みお菓子を食べ、ウェンディを空気のように扱いながら自分たちだけで談話をたのしんでいる。3時間ほど経ち、とうとう一冊を読み終わってしまい、朗読を止める。すると、それまでウェンディのことを無視していたルゼットが紅茶のカップを片手にこちらを睨みつけた。
「まだやめてよいとは言っておらぬぞ」
「…………」
3時間も立ちっぱなしで足が痛む。口の中もからからなのに、水さえ飲ませてくれない。しかしここで逃げたら、根性がなく礼儀知らずな妃だと馬鹿にされるだけ。
(もう本は読み終わってしまった。……どうしよう)
しばらく悩んでから、出窓に視線を向けた。離宮が視界に入り、イーサンのことを思い出す。そっと本を出窓に置いてから顔を上け、疲れを感じさせない笑顔を湛えてテーブルに近づき、ひとりの女性に話しかける。
「ご夫人、あなたはどのような物語が好きですか?」
「え……私? 知らないわよ、そんなの」
「私実は、恋の話を作るのが得意なんです。それは、王女と奴隷の身分違いの恋でも、婚約者がいる幼馴染の非恋でも、それから遠国から嫁いできた姫君と冷酷な皇帝の初恋でも」
「…………」
すると彼女の瞳に好奇心が写った。先ほど朗読をしているとき、彼女は時折こちらに興味を示していた。彼女は少しだけ悩んだあと、唇を開く。
「別に興味ないけど、強いて言えば……騎士の話、とか?」
「騎士! 分かります! 冷徹な女主人と、忠義尽くす騎士。女主人は若くして家族を亡くし、家督を守るために主人になることを余儀なくされた。女だからと舐められないように振舞っているけど、それを騎士だけが見抜いていて……。彼女が唯一少女らしい一面を見せるのは騎士の前だけ。――ではそちらのあなた」
「わ、私?」
ウェンディはその隣に座る女性に視線を移す。彼女はいぶかしげな表情を浮かべた。
「ヒーローの騎士はどんな男性に設定しましょうか。どのような殿方を魅力的に思いますか? 身長は? 体格は? 目鼻立ちに口調、性格、……なんでも構いません」
「……うちの主人が若いとき、長い髪を後ろに束ねていたのだけれどそれがとても格好よかったわ」
「素敵です! 女性のような艶やかで絹のような髪……。妖艶な雰囲気の男性を思い浮かべました」
次々に女性たちに話しかけ、僅かな情報をメモしていき物語を作るヒントを得る。貴婦人たちは興味がないふりをしながらも、ウェンディのペースに飲み込まれていった。
ウェンディは頭の中で構成を練り、手帳を懐にしまって――パンッと手を叩く。
「それでは、皆様のためだけの特別なお話を語りましょう。冷徹な女主人と麗しい騎士の献身。――その数奇な運命を知るのは、ここにおられるあなた方だけです」
すると、貴婦人たちの目つきが変わった。
(私は何十回、何百回と物語を人に語ってきたプロなのよ。お客さんの気を引くすべは――よく知っている)
朗読会に人が全く集まらないということを何度も経験してきた。そんな中でどうしたら集客できるか、試行錯誤してきた経験が今も役立つはずだ。
ウェンディはその唇で、物語を紡ぎ始める。
◇◇◇
ウェンディが本宮から帰って来ない。お茶会に出かけたのが昼を食べてすぐのこと。イーサンが原稿を出版社に届けて帰宅し、夜になっても彼女は離宮に戻らなかった。
(茶会がこんなに長引くのは――おかしい)
イーサンはぎゅっと拳を握る。
もしかしたらウェンディは、ルゼットにひどい目に遭わされているかもしれない。心配でいてもたってもいられなくなり、近衛騎士ルイノを伴って本宮へ向かった。
「最初から行かせるべきではなかったんだ。僕の失態だ。……ウェンディ先生に何かあったら僕は生きていけない……!」
「落ち着いてください、イーサン様。さすがに考えすぎでは。王妃様も王族に危害を加えることはないはずです」
「……長らく彼女に迫害されてきた僕にそれを聞くのか?」
「…………」
廊下の途中で立ち止まり、ルイノを睨みつけると、彼は気まずそうに肩を竦めた。
お茶会が開催されているサロンに向かっていると、第1王子エリファレットが立ちはだかった。彼はこちらを見下すように見つめながら言った。
「おいおい、神聖な王宮に汚いねずみが1匹入ってきたかと思えばお前か。イーサン。半分偽物の分際で、俺の居住する場所に足を踏み入れるとはどういう了見だ?」
「――そこを退いてください。兄上」
こんな場所で足止めを食らっている暇はないのに。エリファレットは意地の悪い笑顔を浮かべながらこちらに近づいてきて、顎をしゃくりながら顔を覗き込む。
「今日は王妃様の茶会にお前の妃が招かれたらしいな。……それで気になってわざわざ来たという訳か。過保護な奴め」
「夜も遅いので彼女を迎えに行きます。そこを通していただけますか」
「断る」
冷静に振舞ってはいるが、とことんイーサンの足を引っ張ろうとするエリファレットの態度に怒りが湧いてくる。しかし、それ以上にウェンディのことが気がかりでならない。彼はイーサンのそんな心の内を見透かした上で、なおも行く手を阻む。
「夜まで続くということはよほど盛会なのだろう。ご友人たちとの親交の場に水を差す不届き者には、罰を与えなければな」
「……罰、ですって?」
「ああ。これでもまだ王妃様の元に行こうと言うなら、この場でみっともなく跪き額を床に付けさせる」
「…………」
イーサンは、なんのためらいもなく膝を床に着けた。軽い頭を下げるだけでここを通してくれるなら――安いものだ。イーサンは王族としてのプライドなど、はなから持ち合わせていない。
「お、おい……正気か? まさかそこまで恥がない奴とは……呆れるな」
イーサンの行為にぎょっとするエリファレットと、それを止めようとするルイノ。イーサンが床に手を付ける寸前に、上から別の声が降ってきた。
「そこまでにしなさい。イーサン」
「……兄上」
そこに立っていたのは、エリファレットの双子の弟である第2王子カーティスだった。艶のある長い銀髪をした、優しげな雰囲気の男。横暴で底意地の悪いエリファレットと違い、彼は優秀で慈悲深く、品行方正なため周りからの評価が高い。
「どんな侮辱を受けようと、お前は王族だ。王族としての矜恃を捨ててはならないよ。王族が簡単に頭を下げれば、王族の権威に傷がついてしまうからね」
「はい。……申し訳ございません」
カーティスに支えられながら立ち上がる。彼はイーサンに穏やかに微笑みかけ、そのままエリファレットのことを見据えた。優しげな笑顔に厳しさが乗る。鋭さを帯びた眼差しに射抜かれ、エリファレットはわずかにたじろぐ。
「恥知らずなのはあなたの方です。兄さん」
「なっ……!? お、俺は何も間違ったことはしていない。半分偽物の分際で身の程をわきまえないイーサンに教育しようとしただけだ……」
「……半分庶民の血が入っていても、国王陛下が王子として認めたんです。不満があっても我々はその意向に従うべきでしょう。兄さんがしているのは、国王陛下と国家への冒涜だ」
「そ……んな大袈裟な……」
カーティスはこちらを振り返り、「ここは私に任せて、行くところがあるなら行きなさい」と目で合図した。心の中で礼を言い、その場を後にする。エリファレットが話はまだ終わっていないと引き留めようとするが、カーティスが邪魔をする。
「ええ。話はこれからですよ、兄さん。だいたいあなたはいつもいつも、どうして自分勝手な行動ばかり――」
後ろでカーティスの説教が始まるのが聞こえた。彼は規律や礼儀に厳しく、エリファレットを唯一叱る人物だ。彼がいなければ、エリファレットはもっとろくでもない人間になっていたかもしれない。
しかしカーティスもまた、態度には出さないがイーサンのことをよくは思っていない。
足止めを食らってしまったが、ようやく王妃のサロンに到着した。扉の隙間から、サロンの中の明かりが漏れている。その隙間からそっと中を覗き見ると……。
「――騎士は女主人を抱き締めながら涙を流しました。『仕える身でありながら、このような気持ちを抱いてしまい申し訳ありません。あなたのことを、心からお慕い申しております。あなたのことを守って差し上げたいのです』――と。騎士は全て見抜いていました。女だからと軽視されないように、彼女があえて冷たく振る舞っていたこと。本当は繊細な心を持っていたことを……」
ウェンディは貴婦人たちの前に立ち、身振り手振りで物語を語っていた。それを聞く女性たちは、真剣な表情で夢中になって聞いている。そして、王妃ルゼットも涙ぐみながらウェンディの話を傾聴しているではないか。
(ああ……本当にすごいよ。ウェンディ先生の物語は、どんな人の心にも届くんだね。さすがだ。僕は誇らしいよ)
物語を語るウェンディの瞳は、きらきらと輝いている。イーサンが恋い焦がれ、眩しく感じてきたその表情だった。
どうやら自分は余計な心配をしていたらしい。彼女の物語りを邪魔しないように、そっとイーサンは扉を閉めた。