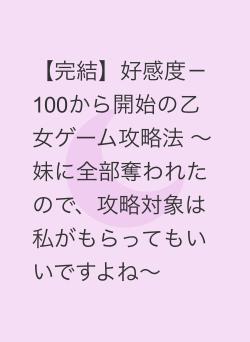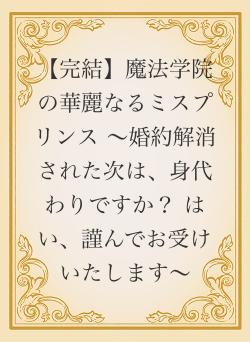夜会は盛会だった。参集者の年齢層は高めで、上流貴族家の家長と夫人が主に参加している。恐らく、王妃と親しい人たちが集められたのだろう。
広間に入ってすぐ、イーサンたちは注目を集めた。それは、良い意味ではなく、悪い意味で。くすくすと嘲笑する声が耳を掠め、あからさまな好奇の眼差しを送ってくる。
けれどイーサンは意に返さず、愛想のいい笑顔を湛えていて、彼の顔を見上げたウェンディは心が痛くなった。
(こんな状況に動じないのは――慣れてしまったからだ)
氷のように固くなった心が見えた気がして、隣に立っているだけでこらまで悲しくなる。
(……そんなに血統が大事? イーサン様は何にも悪いことしてないのに)
『忌み子』、『婚外子』という言葉が時折聞こえてくる。ウェンディは彼に促されるまま、広間の奥のルゼットの元まで歩んだ。1段高いところに高級なひとりがけソファが佇んでおり、そこに彼女は座って、夜会の様子を上から眺めていた。召使いたちが横から大きな扇子で彼女に風を送っている。
長い髪を後で結い、つり上がった瞳が特徴的な女性だった。見た目だけで威圧的な雰囲気がある。厚い唇を開いて真っ先にこちらに告げる。
「結婚おめでとう。イーサン」
「……お祝いのお言葉、ありがとうございます」
笑顔で礼を伝え、最敬礼を執るイーサン。ウェンディも彼に続き、不慣れなお辞儀をする。
「妻のことを紹介いたします。彼女はウェン――」
「待て。直接その娘から話が聞きたい」
「ですが……」
「随分と過保護だな。それともお前の伴侶は、夫を介さなければ挨拶もできぬ臆病者か?」
「…………」
ルゼットの煽りに、会場から馬鹿にしたような笑いが起こる。
彼女は手をかざしてイーサンが話すのをわざわざ制止し、こちらを挑発的に見据えた。彼女だけではなく、広間にいる人々全員が、ウェンディの一挙手一投足を注視している。――値踏みでもするかのように。
しかしウェンディは、人前で話すことには人一倍慣れている。イーサンの心配をよそに、落ち着いた態度で答えた。
「私はウェンディ・エイミスと申します。男爵家の出身です」
ざわり。ウェンディの名前に人々がざわめき始めた。男爵家という王族の妃にしては低すぎる身分に、先日の婚約破棄騒動。そして、国で一番の売れっ子恋愛作家であることで、話題性には事欠かないのだろう。
ルゼットは肘掛に肘を着き、見下したように鼻で笑う。
「そなたは大衆小説を書いていると聞いたが、まことか?」
「はい」
ウェンディは真っ直ぐ彼女を見上げる。次に何を言われるのかと身構えていると、彼女は続けた。
「そう警戒するでない。私はそなたを評価している。人の心を掴む作品を書けるというのは、そうそうない才能だ」
「……光栄に存じます」
「そこで、ぜひ次の茶会にそなたを招きたい。朗読を私の友人らの前で披露してみせよ」
「……!」
つまりそれは、イーサンを伴わずにたったひとりで、ルゼットの領域に飛び込まなければいけないということ。大衆小説を馬鹿にして笑った彼女が、ウェンディのことを歓迎してくれるとは思えない。あれこれと方法を尽くして嫌な思いをさせられることは予想できる。
しかしここで拒めば、第3王子妃は付き合いが悪いと不義理な印象を与えることになるだろう。
「王妃様。申し訳ございませんが、彼女はまだ王宮に来たばかりです。もう少し慣れて心が落ち着いてからに――」
「黙れ。お前に発言を許可した覚えはないぞ」
「……申し訳、ございません」
ルゼットは厳しい口調でイーサンの訴えを跳ね除けた。
「行きます。王妃様のお茶会に招いていただけるなんて、これ以上に光栄なことはありませんもの」
ウェンディはにこやかな笑顔で誘いを引き受けた。イーサンの立場を守るために。
「では、楽しみにしている」
「……はい」
結局、イーサンの方はろくに会話をさせてもらえず、結婚後初めての挨拶は終わった。イーサンにはひどく冷たい態度を取っていたのに、参加していた他の王女や王子には優しく接していた。明らかな対応の差に、ウェンディは心を曇らせる。
2人は人々の関心から逃れるようにバルコニーに出た。王妃に対面してから、彼は暗い顔をしていたが、夜風で体を冷やさないようにとジャケットをさりげなくかけてくれた。
「すまな――」
「さっきのことなら、私に悪いと思わないでください。王子妃として最低限の活動を行う契約ですから」
謝罪の言葉を遮って、気にしないでと伝えると、彼はあなたがそう言うなら分かったと言った。
イーサンが給仕からもらってきてくれた飲み物を受け取り、乾いた喉を潤す。半分減ったグラスを片手に、バルコニーの外を眺めた。広間から漏れ聞こえる食器の音と人々の声に混じって、夜虫の鳴く声が鼓膜を揺らす。
ふいに、ウェンディの目から涙が零れた。それを見たイーサンは驚いて慌てふためく。
「ウェンディ!? どうして急に泣いたりして……っ。やっぱり夜会は負担すぎたね。ごめん、気が利かなくて……」
「違います。違うの、そうじゃなくて……」
両目からぽろぽろと涙を溢れさせながら、彼のことを見上げる。
「私は平気です。ただ、あなたがあまりに気の毒で……。ずっと、こんな辛い目に遭ってきたというの? 今までずっと……」
「……!」
今も脳裏に、参集者たちの奇異の目が焼きついて離れない。イーサンはこれまで、ひとりでそれらを受け止めてきたのだろう。そう思うと、彼のことが不憫に思えて仕方がなかった。ぐすぐすと鼻を鳴らしながら泣く。
(辛いのは私じゃなくてイーサン様の方……。何の力にもなれないくて、泣くことしかできないなんて……情けない)
彼にかける慰めの言葉ひとつも見つからず、ただ泣き続けた。「辛かったですね」と囁きかければ、しばらく堪えていた彼もウェンディに釣られるようにそっと涙を流し、絞り出すような掠れた声で言う。
「……そうだよ。僕はずっと人に軽視され、罪人のように生きてきた」
「罪人なんかじゃないです! イーサン様に悪いところなんて何もありません」
すると、イーサンのしなやかな手が伸びてきて、頬に添えられる。優しい手つきで、ウェンディの涙を拭う。まるで壊れ物を扱うかのようにそっと、優しく輪郭を撫でられた。
「僕なんかのために泣いてくれてのは、あなたが初めてだよ。……ありがとう、ウェンディ」
「…………」
こんなに胸が痛むのはきっと、イーサンのことがウェンディにとって大切な存在になりつつあるからだ。
ウェンディは決心した。イーサンが蔑視されないように、肩身の狭い思いをせず堂々と生きていけるように、仮の妻としてやれるだけのことをやろうと。
(私にもできることを探そう。……私、イーサン様の力になって差し上げたい)