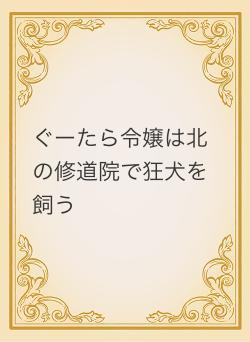「頼みたいことは一つだ」
カタルはシャルロッテから視線を外し、遠くを見つめた。しかし、その視線の先には何もない。
どこか憂いを感じるその横顔に、シャルロッテはただ黙って言葉を待つことしかできなかった。
「息子の相手を」
「息子さん……。えっと……、前妻の……」
「ああ。息子には母親が必要だ」
「はあ……」
出産後一ヶ月もせずに追い出されたという新聞記事を思いだしながら、曖昧に頷く。母親が必要ならば、前妻ではだめなのか。そんな質問を投げかけられる雰囲気ではない。
(人それぞれ事情はあるよね)
新聞記事がすべてではない。
おしどり夫婦と呼ばれた夫妻の関係が実は冷えていた――なんて話もあるものだ。
きっと、シャルロッテの知らない大人の事情があるのだろう。
「あの……。つかぬことをお伺いしますが、なぜ私なのでしょうか?」
「君を選ぶのはおかしいだろうか?」
「まあ、選択肢としては最後かなと。未婚の女性はたくさんいるでしょう? 難ありの私よりも、相応しい人はたくさんいるはずです」
大切な息子の世話を任せるのであれば、もっと他にもいそうなものだ。『冷酷悪魔』と呼ばれていても皇族の一人。彼と結婚すれば、皇族の一員になる。
それを魅力に感じる女性もいるだろう。
カタルはわずかに考えたのち、小さく言った。
「君が犬好きだからだ」
(意味がわからないわ)
息子の世話と犬好き。まったく繋がらない。
(もしかして、息子さんの手のつけられない子なのかしら?)
お手上げ状態で、結婚できなさそうなシャルロッテなら、と声を掛けたのかもしれない。
「人見知りで最初は少し、手が掛かるかもしれない」
カタルの言葉にシャルロッテは「やっぱり」と言いかけて口を噤んだ。
うまい話には裏がある。そういうことだ。
「動物を飼うのは、息子との生活に慣れてからにしてほしい」
「なるほど。成功報酬ということですね」
カタルはシャルロッテから視線を外し、遠くを見つめた。しかし、その視線の先には何もない。
どこか憂いを感じるその横顔に、シャルロッテはただ黙って言葉を待つことしかできなかった。
「息子の相手を」
「息子さん……。えっと……、前妻の……」
「ああ。息子には母親が必要だ」
「はあ……」
出産後一ヶ月もせずに追い出されたという新聞記事を思いだしながら、曖昧に頷く。母親が必要ならば、前妻ではだめなのか。そんな質問を投げかけられる雰囲気ではない。
(人それぞれ事情はあるよね)
新聞記事がすべてではない。
おしどり夫婦と呼ばれた夫妻の関係が実は冷えていた――なんて話もあるものだ。
きっと、シャルロッテの知らない大人の事情があるのだろう。
「あの……。つかぬことをお伺いしますが、なぜ私なのでしょうか?」
「君を選ぶのはおかしいだろうか?」
「まあ、選択肢としては最後かなと。未婚の女性はたくさんいるでしょう? 難ありの私よりも、相応しい人はたくさんいるはずです」
大切な息子の世話を任せるのであれば、もっと他にもいそうなものだ。『冷酷悪魔』と呼ばれていても皇族の一人。彼と結婚すれば、皇族の一員になる。
それを魅力に感じる女性もいるだろう。
カタルはわずかに考えたのち、小さく言った。
「君が犬好きだからだ」
(意味がわからないわ)
息子の世話と犬好き。まったく繋がらない。
(もしかして、息子さんの手のつけられない子なのかしら?)
お手上げ状態で、結婚できなさそうなシャルロッテなら、と声を掛けたのかもしれない。
「人見知りで最初は少し、手が掛かるかもしれない」
カタルの言葉にシャルロッテは「やっぱり」と言いかけて口を噤んだ。
うまい話には裏がある。そういうことだ。
「動物を飼うのは、息子との生活に慣れてからにしてほしい」
「なるほど。成功報酬ということですね」