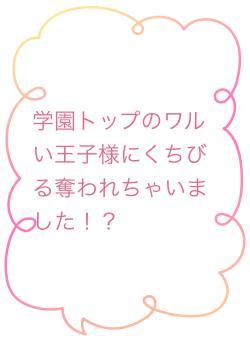メッセージアプリの着信音が鳴ったのは、帰りに立ち寄った書店を出て間もなく。
スマホを手にして目に飛び込んできたのは一ノ瀬くんの名前と、お洒落にモノクロで撮られた風景写真が切り抜かれた彼のアイコンだ。
『土曜の午後空いてる?』
思わず路地に立ち止まって、短いメッセージを眺めてしまう。
空いてなくても空けておくくらいには会いたい。
リップクリームのことだって、聞きたい。
一ノ瀬くんのことも、彼の夢のことも、もっと知りたい。
送りたいメッセージはいっぱいあった。
けれど『はい』とだけ返すと、『じゃあ十四時に』『あの店で』と一ノ瀬くんから飛んできたメッセージをまたしばし眺めて、もう一度『はい』と返すのが精一杯なほどには、男の子との距離感が今の私にはわからない。
もっと仲良くなれるだろうか。
私は一ノ瀬くんと会話を交わしてから、仲良くなりたいと思ってしまった。
私を信頼してくれたことも、自分の夢を教えてくれたことも、嬉しかったから。
せめてその気持ちをいつか彼に伝えられるようにはなりたい。
そんな思いをずっと抱えて、一ノ瀬くんのことばかり考えていたからだろう。
書店で手に取った本は恋愛小説ばかりだった。
スマホを手にして目に飛び込んできたのは一ノ瀬くんの名前と、お洒落にモノクロで撮られた風景写真が切り抜かれた彼のアイコンだ。
『土曜の午後空いてる?』
思わず路地に立ち止まって、短いメッセージを眺めてしまう。
空いてなくても空けておくくらいには会いたい。
リップクリームのことだって、聞きたい。
一ノ瀬くんのことも、彼の夢のことも、もっと知りたい。
送りたいメッセージはいっぱいあった。
けれど『はい』とだけ返すと、『じゃあ十四時に』『あの店で』と一ノ瀬くんから飛んできたメッセージをまたしばし眺めて、もう一度『はい』と返すのが精一杯なほどには、男の子との距離感が今の私にはわからない。
もっと仲良くなれるだろうか。
私は一ノ瀬くんと会話を交わしてから、仲良くなりたいと思ってしまった。
私を信頼してくれたことも、自分の夢を教えてくれたことも、嬉しかったから。
せめてその気持ちをいつか彼に伝えられるようにはなりたい。
そんな思いをずっと抱えて、一ノ瀬くんのことばかり考えていたからだろう。
書店で手に取った本は恋愛小説ばかりだった。