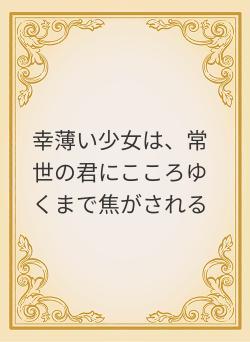「サヤカ、ちょっと保健室行くから、先生に言っといてくれる?」
「おっけ、いってら」
私はサヤカに声をかけた後、教室を出た。
廊下に出た時、ちょうど保健委員の山田さんとすれ違った。
ちょっとためらったけど振り返って声をかける。
「山田さん!」
突然声をかけられ、ビックリした様子で山田さんは振り返った。
「ん? どしたの? 水眞さん」
「体調悪くて、保健室行くから……」
「あ、うん」
「一応サヤカにも言ってあるけど……」
「ああ……わかったわかった」
何かを察したようにうなずく山田さん。
過去にサヤカに保健室に行ってくると伝えたのに、きちんと先生に伝わってなかったことがあった。
うっかり忘れていたと、本当に申し訳なさそうに手を合わせていたから、私はそれ以上何も言わなかったけど。
サヤカはそういう子だった。
山田さんもサヤカの性格をなんとなくわかっているのだろう。だから私が念のために伝えていったってことを察してくれたみたいだ。
たぶんクラスメイトは全員わかっている。サヤカのことを。サヤカの性格を。
わかった上で付き合わない。
私はその逆なだけ。
保健室に行くと、先生はいなかった。
利用名簿に名前を書く。
先に男の名前が書いてあった。奥のベッドを利用してるみたいだ。
私は手前の空いているベッドに横になり、お腹に両手を置いて目を閉じた。
どれくらい時間が経ったのかわからない。
いつの間にか寝てしまっていたようで、でもまだ私はまどろみの中にいた。
あまりの心地よさに目を開けることができない。
体はというと、なんとか落ち着いている。お腹のいたみも消えていた。
ふいに、気配を感じて目を開けると──。
目が合った。
えっと……おかしいな。
私は今保健室の、カーテンで仕切られたベッドで横になっているはずなのに。
なんで目の前に顔があるんだろ。
男の子、透き通るような肌の男の子。
一見してクールな瞳だけど、なにか力強い意志を感じさせる。
シュッとした雰囲気のイケメンだった。
不思議そうに私の目を見つめるその男の子は、ようやく口をひらいてくれた。
「お前、なに?」
お前こそ、何?
言ってやりたかったけど、緊張して口が開かない。
呼吸をすれば息がかかるような、こんな距離で男の子と接したことがない。
ていうかこの距離はもう犯罪スレスレだよね。
「名前は?」
耳触りのよい低い声で、気だるげに訊いてくる。
「──そ、そっちが先に名乗って」
私が声を振り絞ると、男の子はすこしギョッとして顔を離し、姿勢をただした。
ざまあみろ。
ようやくの思いでカウンターをいれてやった。
「俺は、西之谷琢磨」
「カホ」
「苗字は?」
「教えない」
「ふ、おもしれえ。カホね」
いきなり呼び捨て?
腹が立ったけど顔には出さない。
「なんだ、その強気な顔。休んでたわりにずいぶんと元気そうだな」
しっかりと顔に出てたようだ。
「ぁ、あの」
「あ?」
「あなたはなんで、ここに……」
「なんかうなされてたから、気になってさ」
「え……」
「ずっと寝言、言ってたぜ」
「なんて」
「さあ、とにかくうるさくて起こされたんだよ」
彼はそう言って隣のカーテンに目を向ける。
そっか。
隣のベッドで寝てるのが彼だったんだ。
「ご、ごめん。起こしちゃったんだね」
「そう、責任とって」
「責任?」
「うん、起こされて寝不足の分。寝かしつけてよ」
そう言いながら、その男の子は私の横にねころんでくる。
ああ、これ夢だ。夢だよね。
だって夢じゃなければ、ありえないんだもの。こんな現実。
隣を見ると、やけに整った顔立ちの男の子。
そんなのとカーテンの中で、二人きり。
「あの、西之谷くん?」
「タクマでいいよ。カホちゃん」
「……無理」
何がタクマでいいよ、だ。いいわけあるか。あと、呼び捨てにするのか、ちゃん付けするのか、ハッキリして。
その時、ガラガラと音を立てて入り口の扉が開いた。
「ごめんごめん、留守にしてて、えーっと……」
保健の先生が帰ってきて、名簿を確認しているらしい気配がする。
「えーと、一年三組の西之谷くんと、二年一組の水眞さんね」
は? 一年?
やられた。
ぜんっぜん見えない。
なんなら三年生だと思ったほどだ。
こいつ、と思って横を向くと、唇にやわらかいものが触れた。
西之谷くんは人差し指を私の口にあてていた。
いたずらっぽい笑みを浮かべて、しーっとささやいている。
「先生にバレちゃうよ? しばらくこのままね、カホちゃん」
小声で私につぶやくと、彼は目を閉じた。
カーテンの中で二人きり。
それからの数分間、私はぜんぜん眠ることなんてできなかった。
気が付いたら寝てたみたいで、目を覚ました時には彼はもういなかった。