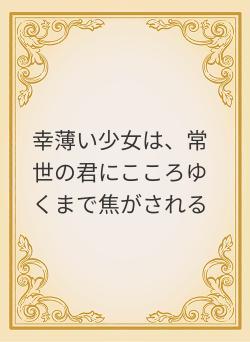ある日の放課後。
下駄箱に入っている手紙を取り出した。
手紙には『西之谷琢磨』と書いてある。
「サヤカ、これ見て!」
「んー? わ、ラブレター! また!?」
のぞき込むように顔を近づけたサヤカの目の色が変わる。
「うっそ! 西之谷くんじゃん! マジ!?」
「サヤカ、どうしよ……?」
「見よ! 読んで読んで!」
手紙の内容は、話があるから体育倉庫に来てほしいというものだった。
今はテスト期間で部活動が行われてない。なので体育館は無人のはずだ。
「えー、なんでカホばっか!」
サヤカがこぼした。
その顔は、うらやましそうでもあり、残念そうでもある。
彼女は本当に自分の感情に素直だ。
「もちろん行くんでしょ?」
「え、うーん。体育倉庫か。なんで体育倉庫なんだろ」
「さあ? バスケ部だからじゃない? 馴染みあるとか」
「まあ、そっか」
「行ってみようよ、カホ!」
それは、自分もいっしょに行くって意味で言ってるんだよね。
あの時もそうだったもんね。
サヤカは本当に友達思いのイイコだよ。
「じゃあ、サヤカ。いっしょに来て」
「もちろん!」
人のいない体育館は、すごく新鮮だった。
広々とした空間の中、ステージの横手にある体育倉庫へと向かう二人分の足音だけが反響していた。
体育倉庫の重い扉を開けて中へと入る。
中は薄暗くて、小さな小窓からの明かりがさしているだけだった。
すぐに違和感に気づいた。
人の気配。それも複数の。
後ろで重い扉が音を立てて閉まった。
閉じ込められた……?
私は緊張のあまり声が出ない。隣にいるサヤカも同じようだった。
「へっへっへ、待ってたぜ? まさか二人で来るとはなあ」
倉庫の奥で男の声がした。
扉を閉めた男が後ろに一人、左右にも一人ずつ。
合わせて四人の男が倉庫の中にいた。
全員三年生だ。
手紙の主であるはずの、タクマくんはもちろんいない。
男たちが何かを言う前に、私は口をひらく。
「サヤカ? これなに? ヤバくない?」
サヤカの顔はひたすらにこわばっている。
「うん……なにこれ……あっ」
彼女は男の顔を見て気がついたようだ。
奥にいる男の顔は、見たことがある顔だった。
サヤカがずっと前に付き合っていたハンド部の先輩だ。
たしか、飽きたとか言って適当にふったはず。
「先輩たち、何してるんですか……西之谷くんは?」
「は? 何言ってんだ? サヤカ。お前が俺たちのこと呼び出したんだろうが」
「なに……何言ってんの? こわっ」
「っけ、どうでもいいや。みんなでかわいがってやるから、今日は楽しもうや」
「二人でサービスしてくれるなんて、最高じゃん」
「だな、ギャハハ」
下卑た笑いが倉庫内に響く。耳にさわる下品な声。
「サヤカ……。どうしよう」
私はサヤカの腕をつかんで引っ張った。
彼女の顔はこわばっている。
私とサヤカは先輩たちの手によって、手を後ろで縛られてしまった。
これでもう身動きがとれない。
絶望的だ。
全身から嫌な汗が噴き出してくる。
「どっちからいただこうかなー」
「どっちもいいよね。俺サヤカちゃんじゃないほうが好みかな」
「へへ、俺たちを楽しませてくれよな」
物騒な会話を繰り広げながら、男たちがにじり寄ってくる。
サヤカを見ると、追い詰められた小動物のように、ふるえている。
私もコワクてふるえが止まらなかった。
その時──。