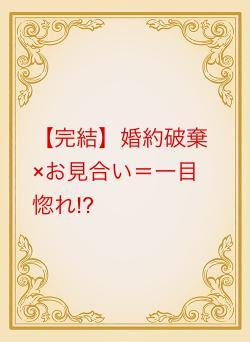そんな両親だったが、ラルフのことを愛しているのは伝わっていた。どんなにいそがしくても、ラルフを抱きしめたり置手紙を残したりと愛が伝わるように努力していた。お手伝いさんも良い人で、両親がどれだけ彼を愛しているのかを話してくれたので彼はさびしくなかったと口にする。
「――でも、本当はちょっとさびしかったのかも?」
右手の人差し指と親指を一センチくらい離して笑う姿に、アシュリンは「そっかぁ」とつぶやいた。
クラーク家では、行き場をなくした子どもたちのための支援をしていて、両親はその準備や自分の仕事に追われていた。いそがしく動き回る両親に迷惑をかけちゃダメだと、ラルフは自分のことは自分でできるように努力したとのこと。
十二歳の誕生日を機に、旅立つことを決めたのは……
「世界をこの目で見たかったのもあるけれど、両親がどんなことをしているのかも知りたかったんだ。話で聞くのと、実際見るのでは、印象が違うだろうから」
「そうなの?」
「うん。耳で聞く情報と、目で見る情報ってわりと違いがあるんだよ。ぼくは初めて、両親が支援している孤児院を見て驚いたんだ」
アシュリンと歩くペースを合わせているラルフは、ちらりとルプトゥムに視線を送る。ルプトゥムはそっと彼に近付いた。
「――でも、本当はちょっとさびしかったのかも?」
右手の人差し指と親指を一センチくらい離して笑う姿に、アシュリンは「そっかぁ」とつぶやいた。
クラーク家では、行き場をなくした子どもたちのための支援をしていて、両親はその準備や自分の仕事に追われていた。いそがしく動き回る両親に迷惑をかけちゃダメだと、ラルフは自分のことは自分でできるように努力したとのこと。
十二歳の誕生日を機に、旅立つことを決めたのは……
「世界をこの目で見たかったのもあるけれど、両親がどんなことをしているのかも知りたかったんだ。話で聞くのと、実際見るのでは、印象が違うだろうから」
「そうなの?」
「うん。耳で聞く情報と、目で見る情報ってわりと違いがあるんだよ。ぼくは初めて、両親が支援している孤児院を見て驚いたんだ」
アシュリンと歩くペースを合わせているラルフは、ちらりとルプトゥムに視線を送る。ルプトゥムはそっと彼に近付いた。