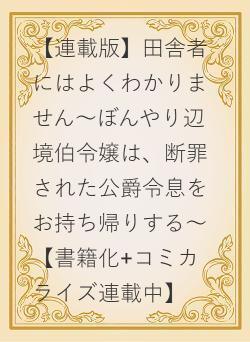私とシオン殿下は、テーブルを挟んでソファーに向かい合って座った。カードを混ぜる手を止めた殿下は、慣れた手つきで四十八枚のカードを伏せたままテーブルに横一列に広げる。
「リナリアは初めてだから、簡単な勝負にしようね。このカードの中から一枚ずつ選んで、より強いカードを引いたほうが勝ち」
「分かりました」
シオンは「お先にどうぞ」と私に先手を譲ってくれた。
この勝負は、運任せだから考えても仕方ない。
私が右端のカードを一枚めくると、カードには王冠をかぶった男性のイラストが描かれていて、その下には『キング(王)』と書かれていた。
やったわ! 強そうなカードが引けた。
シオン殿下を見ると、口元に手を当ててクスクスと笑っている。
「良いカードが引けたようだね」
「どうしてそれを⁉」
「だって、全部顔に出ているんだもの。リナリアは可愛いね」
お世辞だと分かっているのに頬が赤くなってしまう。こういう言葉がサラリと出てくるなんて、やっぱり『恋多き男』のウワサだけは本当だと思う。
シオン殿下は、優雅な手つきでテーブルの上に並べられたカードを一枚めくり、満面の笑みでそのカードを私に見せた。カードには、複数の民衆が描かれていて、イラストの下には『モブ(群衆)』と書かれている。
「リナリアは?」
シオン殿下にキングのカードを見せながら、私は「これって私の勝ちですよね?」と微笑んだ。
「そうだよ……って言ってあげたいけど残念。リナリアが引いたキングのカードは確かに強いカードだけど、キングは、唯一、モブには勝てないんだ」
「え? どうしてですか?」
「だって、モブがいないとキングは存在できないからね。一人で『私は王だ』って叫んでも王にはなれないでしょう?」
「そっか……そうですね」
「それに、革命を起こすのも群衆だからね」
シオン殿下の言う通りで、平和なこの国では考えられないけど、他国では酷い政治に対して反乱や革命が起こることもある。
「えっと、じゃあ、この勝負は私の負けですか?」
シオン殿下がコクリと頷いたのを見て、私は肩を落とした。
殿下の悪いウワサを消したかったのに……。
でも負けてしまったのだから仕方ない。
「罰ゲームを決めてください」
「うーん、リナリアにしてほしいことがたくさんありすぎて……」
「私が殿下にできることが、そんなにたくさんあるのですか?」
一つも思いつかない。
「もちろんだよ。でもそうだね、リナリアに嫌われたくないから、一番簡単なものにしよう。リナリア、私の恋人になって」
シオン殿下の言葉を理解するのに数十秒。たっぷり時間を空けてから私は叫んだ。
「ええっ⁉ な、何を⁉ そんなの無理です!」
「無理なの?」
悲しそうな瞳のシオン殿下に、心臓を鷲(わし)づかみにされながら私は首を左右に振る。
「無理に決まっています!」
「そう……」
シオン殿下は、人差し指を軽く自身のあごに添えながら少し考えるような素振りを見せた。
「……そっか、私の悪いウワサを消すために、リナリアに『恋人のふり』をしてほしかったんだけど、無理なんだね」
「え? 恋人のふり、ですか?」
「そう、ふり」
シオン殿下は笑顔で頷いた。
「ほら、リナリアは私の悪いウワサを消したいって言ってくれたでしょう? それなら、私の『恋多き男』というウワサも一緒に消してしまいたいんだ。このウワサは王子としては不名誉だからね。だから、リナリアが協力してくれたら嬉しいなって思ったんだけど……」
「あっ、そういう意味ですか! 私ったら勝手に勘違いして取り乱してすみません」
「良いんだよ。私の言い方が悪かったね」
「いえ」
自分に都合の良い想像をしてしまい、恥ずかしくてシオン殿下の顔が見られない。
私ったら、本当にもう!
熱を持つ頬を両手で押さえながら、私は「そういうことでしたら、ご協力させていただきます」となんとか答えた。
「ありがとう、リナリア。嬉しいよ」
そう言いながらソファーから立ち上がったシオン殿下は、なぜか私の隣に座る。
「殿下?」
シオン殿下は優しそうな笑みを浮かべながら、私の手に自分の両手を重ねた。
「じゃあ、今から私と恋人のふりをする練習をしようね。罰ゲームだから、もちろんリナリアに拒否権はないよ」
私はなぜか、一瞬だけ肉食獣に追い詰められたような恐怖を感じたけど、すぐに殿下の優しい微笑みにかき消された。
隣り合って座る私達の距離は、肩が触れ合ってしまいそうなくらい近い。シオン殿下からは、爽やかなのにどこか甘い香りが漂ってくる。
ああ、良い香り……。
私がうっとりしていると、シオン殿下は重ねていた手をするりと動かした。私の指の間に殿下の指が入り、お互いの指が絡み合うように手が握られている。
こ、これは、恋人繋ぎという繋ぎ方では?
戸惑いながらシオン殿下を見ると、ニッコリと微笑んでいる。
「リナリア」
「は、はい! 殿下!」
とたんにシオン殿下は悲しそうに瞳を伏せた。
「私のことは、シオンって呼んでって、何度もお願いしているのに……」
「でも、そんなっ」
「罰ゲーム」
言いわけをしようとした私に、シオン殿下は「これは罰ゲームだからね?」と幼い子どもに言い含めるように優しく繰り返す。
「誰にでも簡単にできることなら、罰ゲームにならないでしょう?」
「それもそうですね」
「リナリア。罰ゲームをきちんと実行しないと、お仕置きをされても文句は言えないよ?」
「お仕置き? えっと、はい」
シオン殿下の言う通り、勝負に負けたのだから、潔く罰ゲームを実行しないと。勝者が「シオンと呼んで」と言うのならそれに従わなければならない。
「その、あの……シオン」
シオン殿下はパァと表情を明るくしたあとに、なぜか距離を詰めてきた。元から至近距離にいたのに、さらに近づいたせいで、殿下の膝が私の膝にくっついてしまっている。
「あの、殿……じゃなくて、シオン。膝が、その当たって……」
私がさすがに、これはいけないと距離を取ろうとすると、シオン殿下は私にもたれ掛かってきた。背の高い殿下がもたれ掛かると、私の頭の上に殿下の頭がコツンと当たる。
わぁあああああ……え? これって今、どういう状況?
パニックになりすぎて感情が一回りし、私は逆に冷静になった。
「シオン。これが、恋人のふりの練習ですか?」
そう尋ねると、頭上から「そうだよ」と、どこかうっとりとしたようなシオン殿下の声が聞こえる。
ということは、シオン殿下は今までたくさんの女性とこういうことをしてきたってことね。こんなことをしていたら、確かに良くないウワサがたってしまうわ。
いくら学園内での婚約者探しが推奨されているからと言っても、好き勝手イチャイチャしていいわけではない。貴族として恥ずかしくない節度を持ったお付き合いというものがある。
そんなことを考えながら、私は頭の上にあるシオン殿下の顔を見上げた。金色の長いまつ毛が殿下の白い頬に影を作っている。
私の視線に気がついたシオンは、「なぁに?」と言いながら私の顔を覗き込んだ。美しいだけでなく、誘うような色気が漂うシオン殿下にこんなことをされたら、他の女性たちもクラクラしたに違いない。
「殿下……じゃなくて、シオン。これは良くないと思います」
シオン殿下は小さく首をかしげながら「良くないの?」と子どものように聞いてくる。
「はい、恋人のふりをするなら、もっと清く正しいお付き合いにしましょう」
「清く正しい?」
「そうです。例えば、朝に待ち合わせをして一緒の馬車で登校したり、一緒にお昼ご飯を食べたりとか。恋人のふりをするなら、身体のふれあいより、時間を共有していることを周囲にアピールしたほうが効果的だと思います」
「そっか、それは良い案だね。だけど……」
ニコニコと微笑んでいたシオン殿下の瞳がスゥと細くなった。
「リナリアは、どうして清く正しい男女のお付き合いに、そんなに詳しいのかな?」
恋人繋ぎをしている手にわずかに力が込められた。繋いでいないシオン殿下の左手が、私の頬に優しくふれる。
「もしかして、リナリアは、私以外の男と清く正しいお付き合いをしたことがあるのかな?」
グッと近づけられたシオン殿下の瞳の奥には、暗い炎のような感情が揺らめいていた。怖いというよりは、その危うい灯りに魅入られてしまいそうだ。
「リナリア、正直に言ってね。大丈夫、君には何もしないよ。君には、ね」
首筋に刃物を当てられているような不思議な緊張感の中、私は首を小さく左右に振った。
「いえ、私は誰ともお付き合いをしたことがありません。ノース伯爵家は他家との交流はほとんどありませんでしたし、学園に入学してからは、その、男の人が苦手で……」
学園に入学してすぐにケイトの兄サジェスに『モブ女』と貶(けな)されるようになったせいで、自分からシオン殿下以外の男性に関わりたいとは思わなくなった。
「清く正しい男女のお付き合いは、婚約者がいるクラスメイトたちから聞きました」
ちなみに私が教えてと言ったわけではなく、誰かに聞いてもらいたい彼女たちが勝手にいろいろと話してくれた。そのおかげで、私は付き合った経験がなくても学園内での交際の仕方を知っている。
私の頬にふれていたシオン殿下の左手は、私の長い髪を指ですきながら落ちていく。
「良かった……」
そう呟いたシオン殿下の声は驚くくらいか細かった。殿下は、恋人繋ぎをしている右手を軽く持ち上げる。
「じゃあ、こうやって手を繋ぐのも初めて?」
「はい」
「肩を寄せ合うのも?」
「初めてです。父以外の男の人とあまり話したことがなくって……。私はモテるような外見ではないですから」
自分で言っていて悲しくなるけど、友人のケイトは、学園内でよく見知らぬ男子生徒に声をかけられて「友達になってください!」と言われたり、手紙をもらったりして対応に困っている。美少女は大変なのだ。
シオン殿下は「そっか……」と呟くと、どこか恍惚(こうこつ)としたような表情を浮かべた。
「じゃあ、リナリアの初めてはすべて私のものだね」
「えっと? はい、そうですね! シオンが私の初めての恋人ですから」
そう言ったあとに私は「なーんて。ふり、ですけど」と言いながらシオン殿下に微笑みかけた。
シオン殿下はうつむきながら苦しそうに自身の左胸を押さえる。
「ああ……幸せ……」
微かに漏れ聞こえたシオン殿下の声は、喜んでいるようでもあり泣いているようにも聞こえた。
「リナリアは初めてだから、簡単な勝負にしようね。このカードの中から一枚ずつ選んで、より強いカードを引いたほうが勝ち」
「分かりました」
シオンは「お先にどうぞ」と私に先手を譲ってくれた。
この勝負は、運任せだから考えても仕方ない。
私が右端のカードを一枚めくると、カードには王冠をかぶった男性のイラストが描かれていて、その下には『キング(王)』と書かれていた。
やったわ! 強そうなカードが引けた。
シオン殿下を見ると、口元に手を当ててクスクスと笑っている。
「良いカードが引けたようだね」
「どうしてそれを⁉」
「だって、全部顔に出ているんだもの。リナリアは可愛いね」
お世辞だと分かっているのに頬が赤くなってしまう。こういう言葉がサラリと出てくるなんて、やっぱり『恋多き男』のウワサだけは本当だと思う。
シオン殿下は、優雅な手つきでテーブルの上に並べられたカードを一枚めくり、満面の笑みでそのカードを私に見せた。カードには、複数の民衆が描かれていて、イラストの下には『モブ(群衆)』と書かれている。
「リナリアは?」
シオン殿下にキングのカードを見せながら、私は「これって私の勝ちですよね?」と微笑んだ。
「そうだよ……って言ってあげたいけど残念。リナリアが引いたキングのカードは確かに強いカードだけど、キングは、唯一、モブには勝てないんだ」
「え? どうしてですか?」
「だって、モブがいないとキングは存在できないからね。一人で『私は王だ』って叫んでも王にはなれないでしょう?」
「そっか……そうですね」
「それに、革命を起こすのも群衆だからね」
シオン殿下の言う通りで、平和なこの国では考えられないけど、他国では酷い政治に対して反乱や革命が起こることもある。
「えっと、じゃあ、この勝負は私の負けですか?」
シオン殿下がコクリと頷いたのを見て、私は肩を落とした。
殿下の悪いウワサを消したかったのに……。
でも負けてしまったのだから仕方ない。
「罰ゲームを決めてください」
「うーん、リナリアにしてほしいことがたくさんありすぎて……」
「私が殿下にできることが、そんなにたくさんあるのですか?」
一つも思いつかない。
「もちろんだよ。でもそうだね、リナリアに嫌われたくないから、一番簡単なものにしよう。リナリア、私の恋人になって」
シオン殿下の言葉を理解するのに数十秒。たっぷり時間を空けてから私は叫んだ。
「ええっ⁉ な、何を⁉ そんなの無理です!」
「無理なの?」
悲しそうな瞳のシオン殿下に、心臓を鷲(わし)づかみにされながら私は首を左右に振る。
「無理に決まっています!」
「そう……」
シオン殿下は、人差し指を軽く自身のあごに添えながら少し考えるような素振りを見せた。
「……そっか、私の悪いウワサを消すために、リナリアに『恋人のふり』をしてほしかったんだけど、無理なんだね」
「え? 恋人のふり、ですか?」
「そう、ふり」
シオン殿下は笑顔で頷いた。
「ほら、リナリアは私の悪いウワサを消したいって言ってくれたでしょう? それなら、私の『恋多き男』というウワサも一緒に消してしまいたいんだ。このウワサは王子としては不名誉だからね。だから、リナリアが協力してくれたら嬉しいなって思ったんだけど……」
「あっ、そういう意味ですか! 私ったら勝手に勘違いして取り乱してすみません」
「良いんだよ。私の言い方が悪かったね」
「いえ」
自分に都合の良い想像をしてしまい、恥ずかしくてシオン殿下の顔が見られない。
私ったら、本当にもう!
熱を持つ頬を両手で押さえながら、私は「そういうことでしたら、ご協力させていただきます」となんとか答えた。
「ありがとう、リナリア。嬉しいよ」
そう言いながらソファーから立ち上がったシオン殿下は、なぜか私の隣に座る。
「殿下?」
シオン殿下は優しそうな笑みを浮かべながら、私の手に自分の両手を重ねた。
「じゃあ、今から私と恋人のふりをする練習をしようね。罰ゲームだから、もちろんリナリアに拒否権はないよ」
私はなぜか、一瞬だけ肉食獣に追い詰められたような恐怖を感じたけど、すぐに殿下の優しい微笑みにかき消された。
隣り合って座る私達の距離は、肩が触れ合ってしまいそうなくらい近い。シオン殿下からは、爽やかなのにどこか甘い香りが漂ってくる。
ああ、良い香り……。
私がうっとりしていると、シオン殿下は重ねていた手をするりと動かした。私の指の間に殿下の指が入り、お互いの指が絡み合うように手が握られている。
こ、これは、恋人繋ぎという繋ぎ方では?
戸惑いながらシオン殿下を見ると、ニッコリと微笑んでいる。
「リナリア」
「は、はい! 殿下!」
とたんにシオン殿下は悲しそうに瞳を伏せた。
「私のことは、シオンって呼んでって、何度もお願いしているのに……」
「でも、そんなっ」
「罰ゲーム」
言いわけをしようとした私に、シオン殿下は「これは罰ゲームだからね?」と幼い子どもに言い含めるように優しく繰り返す。
「誰にでも簡単にできることなら、罰ゲームにならないでしょう?」
「それもそうですね」
「リナリア。罰ゲームをきちんと実行しないと、お仕置きをされても文句は言えないよ?」
「お仕置き? えっと、はい」
シオン殿下の言う通り、勝負に負けたのだから、潔く罰ゲームを実行しないと。勝者が「シオンと呼んで」と言うのならそれに従わなければならない。
「その、あの……シオン」
シオン殿下はパァと表情を明るくしたあとに、なぜか距離を詰めてきた。元から至近距離にいたのに、さらに近づいたせいで、殿下の膝が私の膝にくっついてしまっている。
「あの、殿……じゃなくて、シオン。膝が、その当たって……」
私がさすがに、これはいけないと距離を取ろうとすると、シオン殿下は私にもたれ掛かってきた。背の高い殿下がもたれ掛かると、私の頭の上に殿下の頭がコツンと当たる。
わぁあああああ……え? これって今、どういう状況?
パニックになりすぎて感情が一回りし、私は逆に冷静になった。
「シオン。これが、恋人のふりの練習ですか?」
そう尋ねると、頭上から「そうだよ」と、どこかうっとりとしたようなシオン殿下の声が聞こえる。
ということは、シオン殿下は今までたくさんの女性とこういうことをしてきたってことね。こんなことをしていたら、確かに良くないウワサがたってしまうわ。
いくら学園内での婚約者探しが推奨されているからと言っても、好き勝手イチャイチャしていいわけではない。貴族として恥ずかしくない節度を持ったお付き合いというものがある。
そんなことを考えながら、私は頭の上にあるシオン殿下の顔を見上げた。金色の長いまつ毛が殿下の白い頬に影を作っている。
私の視線に気がついたシオンは、「なぁに?」と言いながら私の顔を覗き込んだ。美しいだけでなく、誘うような色気が漂うシオン殿下にこんなことをされたら、他の女性たちもクラクラしたに違いない。
「殿下……じゃなくて、シオン。これは良くないと思います」
シオン殿下は小さく首をかしげながら「良くないの?」と子どものように聞いてくる。
「はい、恋人のふりをするなら、もっと清く正しいお付き合いにしましょう」
「清く正しい?」
「そうです。例えば、朝に待ち合わせをして一緒の馬車で登校したり、一緒にお昼ご飯を食べたりとか。恋人のふりをするなら、身体のふれあいより、時間を共有していることを周囲にアピールしたほうが効果的だと思います」
「そっか、それは良い案だね。だけど……」
ニコニコと微笑んでいたシオン殿下の瞳がスゥと細くなった。
「リナリアは、どうして清く正しい男女のお付き合いに、そんなに詳しいのかな?」
恋人繋ぎをしている手にわずかに力が込められた。繋いでいないシオン殿下の左手が、私の頬に優しくふれる。
「もしかして、リナリアは、私以外の男と清く正しいお付き合いをしたことがあるのかな?」
グッと近づけられたシオン殿下の瞳の奥には、暗い炎のような感情が揺らめいていた。怖いというよりは、その危うい灯りに魅入られてしまいそうだ。
「リナリア、正直に言ってね。大丈夫、君には何もしないよ。君には、ね」
首筋に刃物を当てられているような不思議な緊張感の中、私は首を小さく左右に振った。
「いえ、私は誰ともお付き合いをしたことがありません。ノース伯爵家は他家との交流はほとんどありませんでしたし、学園に入学してからは、その、男の人が苦手で……」
学園に入学してすぐにケイトの兄サジェスに『モブ女』と貶(けな)されるようになったせいで、自分からシオン殿下以外の男性に関わりたいとは思わなくなった。
「清く正しい男女のお付き合いは、婚約者がいるクラスメイトたちから聞きました」
ちなみに私が教えてと言ったわけではなく、誰かに聞いてもらいたい彼女たちが勝手にいろいろと話してくれた。そのおかげで、私は付き合った経験がなくても学園内での交際の仕方を知っている。
私の頬にふれていたシオン殿下の左手は、私の長い髪を指ですきながら落ちていく。
「良かった……」
そう呟いたシオン殿下の声は驚くくらいか細かった。殿下は、恋人繋ぎをしている右手を軽く持ち上げる。
「じゃあ、こうやって手を繋ぐのも初めて?」
「はい」
「肩を寄せ合うのも?」
「初めてです。父以外の男の人とあまり話したことがなくって……。私はモテるような外見ではないですから」
自分で言っていて悲しくなるけど、友人のケイトは、学園内でよく見知らぬ男子生徒に声をかけられて「友達になってください!」と言われたり、手紙をもらったりして対応に困っている。美少女は大変なのだ。
シオン殿下は「そっか……」と呟くと、どこか恍惚(こうこつ)としたような表情を浮かべた。
「じゃあ、リナリアの初めてはすべて私のものだね」
「えっと? はい、そうですね! シオンが私の初めての恋人ですから」
そう言ったあとに私は「なーんて。ふり、ですけど」と言いながらシオン殿下に微笑みかけた。
シオン殿下はうつむきながら苦しそうに自身の左胸を押さえる。
「ああ……幸せ……」
微かに漏れ聞こえたシオン殿下の声は、喜んでいるようでもあり泣いているようにも聞こえた。