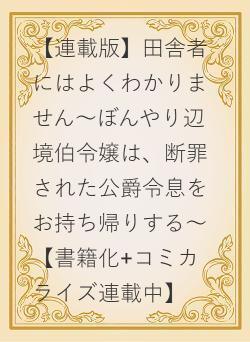この国の第二王子として生まれた私は、幼いころから兄ローレルとそっくりで、同じ服を着ると両親や乳母でさえも見分けがつかないほどだった。
ローレルは、幼いころから圧倒的なカリスマ性を持っていた。彼に会うと、誰もが惹きつけられ一瞬にして魅了されてしまう。
何をやっても優秀なローレルは、『初代国王の再来では?』と皆に期待されていた。初代国王は、各勢力が武力で争っている中、交渉だけで争いを終結させ、一つの国へとまとめあげた偉大な人物だ。
その血を引いているためか王族の中に、まれに突出して優秀な者が生まれることがあり、ローレルもその一人だった。
人々の期待に応え続けるローレルを皆が『完璧な王子様』と褒めたたえる。
でも、私からすれば、私の振りをして悪いことをして、罪をなすりつけてくる最悪な兄だった。
どれほど私が周囲に「私じゃない!」と訴えても、誰も信じてくれなかった。両親ですら、ローレルのウソを見抜けない。
気がつけば、良いことをして褒められるのはローレルで、悪いことをして怒られるのは私と決まっていた。
子どもの頃のリナリアに初めて会ったお茶会のときも、ローレルの乱暴を私のせいにされた。
あのときも私が「私じゃない」と言っても、いつもどおり誰も信じてくれない。
どうして、皆、私の話を信じてくれないんだ? 私はなんのために生きているの? もう死んでしまいたい。
そう思ったとき、「違うわ!」と声がした。顔を上げると、小さな女の子が「今、その子が転んだのは、シオン殿下のせいじゃないわ。私、見ていたもの」と言ってくれた。
周囲の大人たちが女の子に「どういうこと?」と質問するより早く、ローレルが女の子の腕をつかんだ。
痛いと嫌がる女の子をローレルは、無理やり引っ張っていく。周りの大人たちは誰も助けようとしない。ローレルがひどいことをするはずないと思っているから。
私が、あの子を助けないと!
そう思った瞬間、私は別の女の子たちに取り囲まれた。
「シオン殿下、足をかけて転ばしたことをこの子に謝ってください」
「私じゃない!」
周囲から「いくら殿下でもひどすぎます」とか「最低」とかも聞こえたが、そんなことはどうでもよかった。ローレルに連れて行かれた女の子を助けられるのは自分だけだ。
通せんぼする女の子たちを私は「どいて」と言って押しのけた。また「乱暴よ」と言われたがもう少しも気にならなかった。
必死に走って、ようやくローレルと女の子を見つけた。
ローレルは女の子を突き飛ばしたあと、女の子に顔を近づけて何か囁いていた。泣き出した女の子を残して、ローレルはこちらに歩いてくる。
「あれ? シオンも来たの? ちょうど良かった。いつものように、私の代わりに謝っておいてよ」
ニッコリと微笑むローレルを睨みつけてから私は女の子の元へ走った。
「だ、大丈夫?」
肩を震わせながら泣いている女の子に声をかけると、女の子はおずおずと顔を上げた。その頬は涙でぐっしょりと濡れている。
「あの、ごめんね……」
「どうしてあなたが謝るの? 悪いのは、あの子なのに」
ローレルに泣かされた幼い女の子が、そう言いながらローレルが去ったほうを指さしたとき、私は不覚にも泣いてしまった。
彼女だけが、私は悪くない、と言ってくれた。
嬉しくて涙が溢れた。彼女も泣いていたので、庭園の隅に隠れて二人で泣いたのはいい思い出だ。
彼女が帰ったあと、すぐに周囲の大人に彼女のことを聞いた。名前はリナリア。ノース伯爵家の令嬢だとそのときに知った。
「また、リナリアに会える?」
そう聞くと、大人たちは渋い顔をした。
「学園に入学したら会えますが……リナリア嬢は、ノース伯爵家の跡取りなのです」
「それが何か問題なの?」
「殿下がいくら気に入っても、跡取りでは婚約者にできません。まぁ、王家とノース伯爵家とは過去にいろいろありまして、そうでなくとも難しいと思いますよ」
そのあとは、公爵の娘が美しいとか、王子にお似合いの令嬢がいるなどという話になったが、私は少しも興味が持てなかった。
リナリアが私の婚約者になってくれたら良いのに……。
そんなことをずっと考えていた。
その後、将来婚約者になるかもしれない令嬢たちと今から仲良くしておくことも王子の立派な仕事だと言われ、ローレルと共に数人の令嬢に会ったが、誰もローレルと私を見分けることができなかった。
そして、その令嬢たちも、みごとにローレルに騙されて「ローレル殿下はお優しいのに、シオン殿下は乱暴だわ」と口々に言っていた。本当に乱暴なことをしているのはローレルなのに、私がどれほど訴えても誰も信じてくれなかった。
私が『やっぱり私のことを分かってくれるのは、リナリアしかいない』と決心するのは早かった。
それからは、自分の無実を他人に訴えるのをやめた。時間の無駄だから。
その代わりに、私はリナリアのことを調べ始めた。彼女のことだけではなく、王家とノース伯爵家の確執(かくしつ)についても調べた。リナリアに関することならすべて知りたかった。
すべてを知れば、もしかすると、リナリアを婚約者に迎える方法が見つかるかもしれない。
そんな期待を胸に抱いていた。でも、どれだけ調べても、どれだけ知識を増やしても『王族ではリナリアを婚約者にすることはできない』という結論を覆すことはできなかった。
私がどうしたら良いんだろうと悩んでいるころに天才剣士とよばれる兄弟が、ローレルと私の護衛に抜擢された。弟のゼダは私と同じ年だったこともあり、すぐに仲良くなった。
しかも、ゼダは「ローレル殿下とシオン殿下は、歩くときに体重移動の仕方が違います」という謎の理由で私を見分けることができた。だから、私にとってゼダは、リナリアの次に大切な人になった。
そんなゼダに「剣術を教えてほしい」と頼んだ。なんの力もない私だけど、せめて大切な人を守れるように強くなりたい、そう思ったから。
私が学園に入学する年になっても、ローレルとの関係は少しも変わらなかった。
ローレルのせいで、相変わらず私の評判は悪い。しかも、私が学園入学してからは、ローレルが私の振りをして女性と遊ぶようになったので、恋多き男のレッテルも貼られてしまった。
私はというとリナリア以外の女性に少しも興味がないので、その評判にはさすがに不満だった。不満でもローレルが相手だとどうすることもできないのが現状だ。
でも、一生このままでいるつもりはない。
私が学園に入学してから一年後にリナリアが入学してきた。その日から、私はどうしたらリナリアと親しくなれるか悩んだ。他の令嬢たちは、王子と少しでも親しくなろうと群がってくるのに、リナリアは私に近づこうとさえしない。
まぁ、リナリアがローレルにも近づかないのは良かったけど。
リナリアは、いずれは婿養子を取る身なので、王子たちに取り入る必要がない。なんなら王子と仲が良いなんてリナリアにとってはマイナスなことしかないのかもしれない。
ゼダには「シオン、これは護衛ではなく友人としての忠告だ。女性を四六時中、こそこそと付け回して監視するのは良くない」と言われたが「監視ではないよ。リナリアが危ない目に遭(あ)わないように見守っているんだ」と言い続けたらいつしか何も言わなくなった。
ただ、ときどき、ゼダはあきれているような憐れむような、なんとも言えない目を向けてくる。
そんなある日、例の『罰ゲーム』事件が起きた。
リナリアには伝えなかったが、同級生のサジェスが言い出した愚かな罰ゲームの存在を私は知っていた。
カードゲームには参加していなかったが、私は学園にいる間は、ずっとリナリアを見守っているのだから知らないはずがない。私が無理なときは、ゼダに頼んで密かにリナリアを護衛してもらっている。
なので、リナリアが罰ゲームのことを知って傷ついた瞬間すら私は知っていた。
だからこそ、このタイミングでリナリアに近づいた。王子たちに少しも興味がないリナリアに無理に近づくと避けられるのが分かっていたから。ずっと何かきっかけがほしかった。罰ゲームは、その良いきっかけになってくれた。
リナリアが『これは罰ゲームだ』と誤解するようにカードゲームをしていた場所を選んで呼び出した。
その時の私は、わざとローレルの学年のネクタイをつけていた。リナリアを呼びに行ったゼダにも『どちらの王子が呼んでいるか分からないようにしてくれ』と頼んでおいたので、リナリアは、どちらの王子が待っているか知らなかったはずだ。
護衛のゼダは、ゼダの兄と共に、ローレルと私の護衛を交互にしているので、ゼダが側にいることがどちらの王子かを見分ける材料にはならない。
普通の人なら、確実に自分のことをローレルと思ったはずだ。それなのに、リナリアは私だと言い当てた。そのとき、涙が出そうになるほど嬉しかったことを彼女は知らない。
罰ゲームとして、ウソで口説かれていると勘違いしたリナリアがどういう態度をとっても良かった。
怒っても、泣いても、例え叩かれたとしてもいい。怒るなら怒る彼女をなだめて、泣くなら泣く彼女をなぐさめて、叩かれたら叩いた彼女の手を取って、その傷ついた心の隙間に入り込もうと決めていた。
卑怯でもなんでも良い。とにかくリナリアの側にいたいと、初めて出会ったあの日からずっと願っている。
その結果、リナリアが怒りもせず泣きもせず、大人しく私に付き合ってくれるとは思っていなかったから驚いたけど。
予想外の幸せに、たがが外れてリナリアにいろいろとしてしまったが少しも後悔はしていない。むしろ、リナリアとはこれからもっと仲良くなっていくつもりだ。
何があっても、もう絶対に離さないよ。今度は必ず君をローレルから守ってみせる。
私は強く両手を握りしめた。
ローレルは、幼いころから圧倒的なカリスマ性を持っていた。彼に会うと、誰もが惹きつけられ一瞬にして魅了されてしまう。
何をやっても優秀なローレルは、『初代国王の再来では?』と皆に期待されていた。初代国王は、各勢力が武力で争っている中、交渉だけで争いを終結させ、一つの国へとまとめあげた偉大な人物だ。
その血を引いているためか王族の中に、まれに突出して優秀な者が生まれることがあり、ローレルもその一人だった。
人々の期待に応え続けるローレルを皆が『完璧な王子様』と褒めたたえる。
でも、私からすれば、私の振りをして悪いことをして、罪をなすりつけてくる最悪な兄だった。
どれほど私が周囲に「私じゃない!」と訴えても、誰も信じてくれなかった。両親ですら、ローレルのウソを見抜けない。
気がつけば、良いことをして褒められるのはローレルで、悪いことをして怒られるのは私と決まっていた。
子どもの頃のリナリアに初めて会ったお茶会のときも、ローレルの乱暴を私のせいにされた。
あのときも私が「私じゃない」と言っても、いつもどおり誰も信じてくれない。
どうして、皆、私の話を信じてくれないんだ? 私はなんのために生きているの? もう死んでしまいたい。
そう思ったとき、「違うわ!」と声がした。顔を上げると、小さな女の子が「今、その子が転んだのは、シオン殿下のせいじゃないわ。私、見ていたもの」と言ってくれた。
周囲の大人たちが女の子に「どういうこと?」と質問するより早く、ローレルが女の子の腕をつかんだ。
痛いと嫌がる女の子をローレルは、無理やり引っ張っていく。周りの大人たちは誰も助けようとしない。ローレルがひどいことをするはずないと思っているから。
私が、あの子を助けないと!
そう思った瞬間、私は別の女の子たちに取り囲まれた。
「シオン殿下、足をかけて転ばしたことをこの子に謝ってください」
「私じゃない!」
周囲から「いくら殿下でもひどすぎます」とか「最低」とかも聞こえたが、そんなことはどうでもよかった。ローレルに連れて行かれた女の子を助けられるのは自分だけだ。
通せんぼする女の子たちを私は「どいて」と言って押しのけた。また「乱暴よ」と言われたがもう少しも気にならなかった。
必死に走って、ようやくローレルと女の子を見つけた。
ローレルは女の子を突き飛ばしたあと、女の子に顔を近づけて何か囁いていた。泣き出した女の子を残して、ローレルはこちらに歩いてくる。
「あれ? シオンも来たの? ちょうど良かった。いつものように、私の代わりに謝っておいてよ」
ニッコリと微笑むローレルを睨みつけてから私は女の子の元へ走った。
「だ、大丈夫?」
肩を震わせながら泣いている女の子に声をかけると、女の子はおずおずと顔を上げた。その頬は涙でぐっしょりと濡れている。
「あの、ごめんね……」
「どうしてあなたが謝るの? 悪いのは、あの子なのに」
ローレルに泣かされた幼い女の子が、そう言いながらローレルが去ったほうを指さしたとき、私は不覚にも泣いてしまった。
彼女だけが、私は悪くない、と言ってくれた。
嬉しくて涙が溢れた。彼女も泣いていたので、庭園の隅に隠れて二人で泣いたのはいい思い出だ。
彼女が帰ったあと、すぐに周囲の大人に彼女のことを聞いた。名前はリナリア。ノース伯爵家の令嬢だとそのときに知った。
「また、リナリアに会える?」
そう聞くと、大人たちは渋い顔をした。
「学園に入学したら会えますが……リナリア嬢は、ノース伯爵家の跡取りなのです」
「それが何か問題なの?」
「殿下がいくら気に入っても、跡取りでは婚約者にできません。まぁ、王家とノース伯爵家とは過去にいろいろありまして、そうでなくとも難しいと思いますよ」
そのあとは、公爵の娘が美しいとか、王子にお似合いの令嬢がいるなどという話になったが、私は少しも興味が持てなかった。
リナリアが私の婚約者になってくれたら良いのに……。
そんなことをずっと考えていた。
その後、将来婚約者になるかもしれない令嬢たちと今から仲良くしておくことも王子の立派な仕事だと言われ、ローレルと共に数人の令嬢に会ったが、誰もローレルと私を見分けることができなかった。
そして、その令嬢たちも、みごとにローレルに騙されて「ローレル殿下はお優しいのに、シオン殿下は乱暴だわ」と口々に言っていた。本当に乱暴なことをしているのはローレルなのに、私がどれほど訴えても誰も信じてくれなかった。
私が『やっぱり私のことを分かってくれるのは、リナリアしかいない』と決心するのは早かった。
それからは、自分の無実を他人に訴えるのをやめた。時間の無駄だから。
その代わりに、私はリナリアのことを調べ始めた。彼女のことだけではなく、王家とノース伯爵家の確執(かくしつ)についても調べた。リナリアに関することならすべて知りたかった。
すべてを知れば、もしかすると、リナリアを婚約者に迎える方法が見つかるかもしれない。
そんな期待を胸に抱いていた。でも、どれだけ調べても、どれだけ知識を増やしても『王族ではリナリアを婚約者にすることはできない』という結論を覆すことはできなかった。
私がどうしたら良いんだろうと悩んでいるころに天才剣士とよばれる兄弟が、ローレルと私の護衛に抜擢された。弟のゼダは私と同じ年だったこともあり、すぐに仲良くなった。
しかも、ゼダは「ローレル殿下とシオン殿下は、歩くときに体重移動の仕方が違います」という謎の理由で私を見分けることができた。だから、私にとってゼダは、リナリアの次に大切な人になった。
そんなゼダに「剣術を教えてほしい」と頼んだ。なんの力もない私だけど、せめて大切な人を守れるように強くなりたい、そう思ったから。
私が学園に入学する年になっても、ローレルとの関係は少しも変わらなかった。
ローレルのせいで、相変わらず私の評判は悪い。しかも、私が学園入学してからは、ローレルが私の振りをして女性と遊ぶようになったので、恋多き男のレッテルも貼られてしまった。
私はというとリナリア以外の女性に少しも興味がないので、その評判にはさすがに不満だった。不満でもローレルが相手だとどうすることもできないのが現状だ。
でも、一生このままでいるつもりはない。
私が学園に入学してから一年後にリナリアが入学してきた。その日から、私はどうしたらリナリアと親しくなれるか悩んだ。他の令嬢たちは、王子と少しでも親しくなろうと群がってくるのに、リナリアは私に近づこうとさえしない。
まぁ、リナリアがローレルにも近づかないのは良かったけど。
リナリアは、いずれは婿養子を取る身なので、王子たちに取り入る必要がない。なんなら王子と仲が良いなんてリナリアにとってはマイナスなことしかないのかもしれない。
ゼダには「シオン、これは護衛ではなく友人としての忠告だ。女性を四六時中、こそこそと付け回して監視するのは良くない」と言われたが「監視ではないよ。リナリアが危ない目に遭(あ)わないように見守っているんだ」と言い続けたらいつしか何も言わなくなった。
ただ、ときどき、ゼダはあきれているような憐れむような、なんとも言えない目を向けてくる。
そんなある日、例の『罰ゲーム』事件が起きた。
リナリアには伝えなかったが、同級生のサジェスが言い出した愚かな罰ゲームの存在を私は知っていた。
カードゲームには参加していなかったが、私は学園にいる間は、ずっとリナリアを見守っているのだから知らないはずがない。私が無理なときは、ゼダに頼んで密かにリナリアを護衛してもらっている。
なので、リナリアが罰ゲームのことを知って傷ついた瞬間すら私は知っていた。
だからこそ、このタイミングでリナリアに近づいた。王子たちに少しも興味がないリナリアに無理に近づくと避けられるのが分かっていたから。ずっと何かきっかけがほしかった。罰ゲームは、その良いきっかけになってくれた。
リナリアが『これは罰ゲームだ』と誤解するようにカードゲームをしていた場所を選んで呼び出した。
その時の私は、わざとローレルの学年のネクタイをつけていた。リナリアを呼びに行ったゼダにも『どちらの王子が呼んでいるか分からないようにしてくれ』と頼んでおいたので、リナリアは、どちらの王子が待っているか知らなかったはずだ。
護衛のゼダは、ゼダの兄と共に、ローレルと私の護衛を交互にしているので、ゼダが側にいることがどちらの王子かを見分ける材料にはならない。
普通の人なら、確実に自分のことをローレルと思ったはずだ。それなのに、リナリアは私だと言い当てた。そのとき、涙が出そうになるほど嬉しかったことを彼女は知らない。
罰ゲームとして、ウソで口説かれていると勘違いしたリナリアがどういう態度をとっても良かった。
怒っても、泣いても、例え叩かれたとしてもいい。怒るなら怒る彼女をなだめて、泣くなら泣く彼女をなぐさめて、叩かれたら叩いた彼女の手を取って、その傷ついた心の隙間に入り込もうと決めていた。
卑怯でもなんでも良い。とにかくリナリアの側にいたいと、初めて出会ったあの日からずっと願っている。
その結果、リナリアが怒りもせず泣きもせず、大人しく私に付き合ってくれるとは思っていなかったから驚いたけど。
予想外の幸せに、たがが外れてリナリアにいろいろとしてしまったが少しも後悔はしていない。むしろ、リナリアとはこれからもっと仲良くなっていくつもりだ。
何があっても、もう絶対に離さないよ。今度は必ず君をローレルから守ってみせる。
私は強く両手を握りしめた。