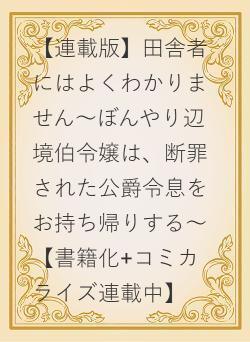馬車の待合室に、顔見知りはいなかった。私を迎えに来たノース伯爵家の紋章がついた馬車に近づくと、なぜか馬車の御者が慌てていた。
「リナリアお嬢様!」
「何かあったの?」
御者は「それが……」と言いながら馬車を見た。誰も乗っていないはずの馬車には、なぜか内側にカーテンがかかっている。
「誰か乗っているの?」
「は、はい。中でお嬢様をお待ちの方が……」
伯爵家の馬車に勝手に乗り込むなんて失礼にもほどがある。でも、もしかすると、それができてしまうほど、相手は高位の貴族なのかもしれない。
「分かったわ。あとは任せて」
御者は馬車の扉をノックしたあと戸惑いながら扉を開けてくれた。カーテンのせいで顔は見えないが確かに誰かが乗っている。
いったいなんなのよ、今日は……。
私は覚悟を決めて馬車に乗り込んだ。
馬車の中で待っていた人物を見て、私は目を疑った。
「……シオン殿下?」
そこには先ほどサロンで別れたシオン殿下が座っている。殿下はニッコリと微笑んだけど、その瞳はなぜか笑っていないように見えた。
「待っていたよ、リナリア」
シオン殿下は「馬車が動くと危ないから、とりあえず座って」と向かいの席に座るように勧める。私は言われるままに座ったあとに、もう一度シオン殿下を見た。
「殿下、どうしてここに?」
その言葉に、シオン殿下は悲しそうに眉を下げる。
「どうしてって、君に会いたいからだよ。必ず会える場所でこうして待っていたんだ」
そう言いながら、まるで恋人に向けるような切なそうな視線を私に向けた。
「殿下、もう演技はやめてください。私は全て知っています。知らない振りをしていたのは謝ります。だからもう、これ以上は……」
これまでは夢見心地で楽しんでいたけど、今は自分がみじめで仕方ない。
シオン殿下は「ごめんね。まさかリナリアに知られているなんて思わなくて」と言いながらため息をついた。
「いつ知ったの?」
「初めから知っていました。偶然、聞いてしまって……」
サジェスたちがカードゲームをしている場に出くわしたのは本当に偶然だった。そのときに罰ゲームのことを知った。
「驚いたよね?」
「まぁ、それはそうですね」
シオン殿下はまた深いため息をついた。
「本当にごめん」
「もういいです」
「ダメだよ。だって、君が入学してからずっと私に見守られていたなんて驚いたでしょう?」
……ん? 見守る?
シオン殿下の口から出た予想外の言葉に私が驚いていると、殿下はさらに言葉を続ける。
「見守ると言っても、もちろんリナリアのプライベートは覗いていないよ。ただ、学園での君の生活が気になってね。君は可愛らしい上に社交的だから、私以外の男とも話すことがあるでしょう? それがどうしても……気になって気になって気になり過ぎて仕方なかったんだ」
何度も『気になって』を繰り返すシオン殿下はどこか危ない雰囲気を漂わせている。
「私はリナリアに会ったときから、ずっと君だけを愛しているのに、君は伯爵家の跡取りで王族の婚約者になれないし、なる気すらないんだもの。そのせいか一緒の学園にいるのに、近づいてきてさえくれない。私が今までどれほど焦(じ)らされていたか」
シオンは自身の胸元を握りしめると、苦しそうにハァと熱い息を吐く。
「こんなに君に恋焦がれて苦しむ私を知りながら、今まで知らないふりをしていたなんて……君は悪いこだね」
頬を赤く染めてうっとりと囁くシオン殿下を見て、私は頭が真っ白になった。
「あの……殿下」
「何?」
「殿下。そ、それは、知りませんでした」
きょとんとしたシオン殿下は「え?」と呟く。
「あの、私が言ったことは、殿下がカードゲームに負けてその罰ゲームとして私をウソで口説いていると知っている、ということだけです。だから、殿下が私を見守っていたとか、殿下が私のことをずっと好きだとか……えっ? 殿下って私のこと、好きなんですか?」
私が自分自身で言った言葉に驚きながら尋ねると、シオン殿下の白い頬に赤みがさす。
「ウ、ウソですよね?」
「ウソじゃないよ」
「そんな……いつの間に?」
シオン殿下は赤面したまま、「子どものころ、初めてお茶会で会ったときから、今までずっと」と教えてくれる。
「あ、私もあの時から殿下の大ファンです」
「ファン?」
スウッとシオン殿下の瞳が細くなった。
「リナリアは、私の、ただのファン?」
「はい、だって私なんかが、殿下とお近づきになるなんておこがましいですから。だから、罰ゲームとはいえ、今まで良い夢を見せてもらいました。ありがとうございました」
私が頭を下げてから顔を上げると、目の前にシオン殿下の顔があった。小さく悲鳴をあげて後ろに下がろうとしたが狭い馬車の中では逃げる場所がない。
「ねぇリナリア。これは罰ゲームじゃないよ」
信じられないその言葉に、私は美しいシオン殿下の顔をマジマジと見つめた。
「殿下は、カードゲームで負けたから、罰ゲームで私を口説いていたのですよね?」
「そんな愚かなことを大切なリナリアにするわけがないよ」
「でも、今までのことが罰ゲームではなかったとしたら、タイミングがよすぎます。殿下に呼び出された場所もカードゲームをしていたところと同じでした」
シオンは「偶然が重なったようだね」と微笑んでいる。
「全て偶然? 私の勘違い……じゃあ、今までのことは?」
思い返してみれば、手の甲へのキスから始まり、手のひらや髪へのキス。壁ドンから愛の告白までいろいろあった。
「もちろん、私の素直な気持ちだよ。そっか、リナリアは、今までのことは全て罰ゲームだと思っていたんだね。……ふーん、よく分かったよ」
「えっと、あの、その」
「私の愛は少しも伝わっていなかったようだから、明日からはもっと頑張らないとね」
シオン殿下は優しく微笑んでいるはずなのに、私はなぜかゾクッと寒気がした。
私とシオン殿下を乗せた馬車が、ようやくノース伯爵家についた。私が馬車から降りようとすると殿下に笑顔で制止される。
「エスコートさせてほしい」
そう言いながら私に向かって右手を差し出した。
本当に演技じゃないの? シオン殿下が私のことを好きだなんてすぐには信じられない。
私がシオン殿下の手を取るのをためらっていると殿下が「抱きかかえて降ろしてあげようか?」と微笑んだので、慌てて殿下の手に自分の手を重ねる。
シオン殿下にエスコートされ馬車から降りると、まるでお姫様になったような気がした。
「あ、ありがとうございます」
私がぎこちなくお礼を言うと、シオン殿下はニッコリと微笑む。
「また明日ね」
そう言われても、返事はできない。今までのようにシオン殿下と密会するわけにはいかない。
なぜなら、私は決して二人の王子殿下に近づいてはいけないから。だから、憧れているシオン殿下にも近づかずいつも遠くから眺めていた。
……あれ? でも、別にファンとして近づくくらいなら良かったよね?
婚約者になるわけでもないし、他の女生徒たちがお近づきになるためにローレル殿下やシオン殿下を取り囲んでいる場面を見たこともある。その中に、私が交ざってもよかったはずだ。
どうして今までそうしなかったのか分からない。何か大切なことを忘れているような気がする。
「リナリア?」
シオン殿下に名前を呼ばれて、私は我に返った。
なんて言っていいのか分からず「失礼します」と伝えると、なんだか他人行儀になってしまった。殿下の表情は、どこか寂しそうに見える。
シオン殿下を乗せた馬車は、学園に戻るために走り出した。私は、その馬車が見えなくなるまで見送っていた。
一人になると、深いため息が出る。
今日は、いろんなことがありすぎて頭が痛いわ。
出迎えてくれたメイドが「お嬢様、大丈夫ですか⁉」と心配してくれている。
「少し頭が痛くて」
メイドは「風邪ですかねぇ?」と言いながら今日は早く寝るように勧めてくれた。
早めにベッドに入った私は、子どものころの夢を見た。
「リナリアお嬢様!」
「何かあったの?」
御者は「それが……」と言いながら馬車を見た。誰も乗っていないはずの馬車には、なぜか内側にカーテンがかかっている。
「誰か乗っているの?」
「は、はい。中でお嬢様をお待ちの方が……」
伯爵家の馬車に勝手に乗り込むなんて失礼にもほどがある。でも、もしかすると、それができてしまうほど、相手は高位の貴族なのかもしれない。
「分かったわ。あとは任せて」
御者は馬車の扉をノックしたあと戸惑いながら扉を開けてくれた。カーテンのせいで顔は見えないが確かに誰かが乗っている。
いったいなんなのよ、今日は……。
私は覚悟を決めて馬車に乗り込んだ。
馬車の中で待っていた人物を見て、私は目を疑った。
「……シオン殿下?」
そこには先ほどサロンで別れたシオン殿下が座っている。殿下はニッコリと微笑んだけど、その瞳はなぜか笑っていないように見えた。
「待っていたよ、リナリア」
シオン殿下は「馬車が動くと危ないから、とりあえず座って」と向かいの席に座るように勧める。私は言われるままに座ったあとに、もう一度シオン殿下を見た。
「殿下、どうしてここに?」
その言葉に、シオン殿下は悲しそうに眉を下げる。
「どうしてって、君に会いたいからだよ。必ず会える場所でこうして待っていたんだ」
そう言いながら、まるで恋人に向けるような切なそうな視線を私に向けた。
「殿下、もう演技はやめてください。私は全て知っています。知らない振りをしていたのは謝ります。だからもう、これ以上は……」
これまでは夢見心地で楽しんでいたけど、今は自分がみじめで仕方ない。
シオン殿下は「ごめんね。まさかリナリアに知られているなんて思わなくて」と言いながらため息をついた。
「いつ知ったの?」
「初めから知っていました。偶然、聞いてしまって……」
サジェスたちがカードゲームをしている場に出くわしたのは本当に偶然だった。そのときに罰ゲームのことを知った。
「驚いたよね?」
「まぁ、それはそうですね」
シオン殿下はまた深いため息をついた。
「本当にごめん」
「もういいです」
「ダメだよ。だって、君が入学してからずっと私に見守られていたなんて驚いたでしょう?」
……ん? 見守る?
シオン殿下の口から出た予想外の言葉に私が驚いていると、殿下はさらに言葉を続ける。
「見守ると言っても、もちろんリナリアのプライベートは覗いていないよ。ただ、学園での君の生活が気になってね。君は可愛らしい上に社交的だから、私以外の男とも話すことがあるでしょう? それがどうしても……気になって気になって気になり過ぎて仕方なかったんだ」
何度も『気になって』を繰り返すシオン殿下はどこか危ない雰囲気を漂わせている。
「私はリナリアに会ったときから、ずっと君だけを愛しているのに、君は伯爵家の跡取りで王族の婚約者になれないし、なる気すらないんだもの。そのせいか一緒の学園にいるのに、近づいてきてさえくれない。私が今までどれほど焦(じ)らされていたか」
シオンは自身の胸元を握りしめると、苦しそうにハァと熱い息を吐く。
「こんなに君に恋焦がれて苦しむ私を知りながら、今まで知らないふりをしていたなんて……君は悪いこだね」
頬を赤く染めてうっとりと囁くシオン殿下を見て、私は頭が真っ白になった。
「あの……殿下」
「何?」
「殿下。そ、それは、知りませんでした」
きょとんとしたシオン殿下は「え?」と呟く。
「あの、私が言ったことは、殿下がカードゲームに負けてその罰ゲームとして私をウソで口説いていると知っている、ということだけです。だから、殿下が私を見守っていたとか、殿下が私のことをずっと好きだとか……えっ? 殿下って私のこと、好きなんですか?」
私が自分自身で言った言葉に驚きながら尋ねると、シオン殿下の白い頬に赤みがさす。
「ウ、ウソですよね?」
「ウソじゃないよ」
「そんな……いつの間に?」
シオン殿下は赤面したまま、「子どものころ、初めてお茶会で会ったときから、今までずっと」と教えてくれる。
「あ、私もあの時から殿下の大ファンです」
「ファン?」
スウッとシオン殿下の瞳が細くなった。
「リナリアは、私の、ただのファン?」
「はい、だって私なんかが、殿下とお近づきになるなんておこがましいですから。だから、罰ゲームとはいえ、今まで良い夢を見せてもらいました。ありがとうございました」
私が頭を下げてから顔を上げると、目の前にシオン殿下の顔があった。小さく悲鳴をあげて後ろに下がろうとしたが狭い馬車の中では逃げる場所がない。
「ねぇリナリア。これは罰ゲームじゃないよ」
信じられないその言葉に、私は美しいシオン殿下の顔をマジマジと見つめた。
「殿下は、カードゲームで負けたから、罰ゲームで私を口説いていたのですよね?」
「そんな愚かなことを大切なリナリアにするわけがないよ」
「でも、今までのことが罰ゲームではなかったとしたら、タイミングがよすぎます。殿下に呼び出された場所もカードゲームをしていたところと同じでした」
シオンは「偶然が重なったようだね」と微笑んでいる。
「全て偶然? 私の勘違い……じゃあ、今までのことは?」
思い返してみれば、手の甲へのキスから始まり、手のひらや髪へのキス。壁ドンから愛の告白までいろいろあった。
「もちろん、私の素直な気持ちだよ。そっか、リナリアは、今までのことは全て罰ゲームだと思っていたんだね。……ふーん、よく分かったよ」
「えっと、あの、その」
「私の愛は少しも伝わっていなかったようだから、明日からはもっと頑張らないとね」
シオン殿下は優しく微笑んでいるはずなのに、私はなぜかゾクッと寒気がした。
私とシオン殿下を乗せた馬車が、ようやくノース伯爵家についた。私が馬車から降りようとすると殿下に笑顔で制止される。
「エスコートさせてほしい」
そう言いながら私に向かって右手を差し出した。
本当に演技じゃないの? シオン殿下が私のことを好きだなんてすぐには信じられない。
私がシオン殿下の手を取るのをためらっていると殿下が「抱きかかえて降ろしてあげようか?」と微笑んだので、慌てて殿下の手に自分の手を重ねる。
シオン殿下にエスコートされ馬車から降りると、まるでお姫様になったような気がした。
「あ、ありがとうございます」
私がぎこちなくお礼を言うと、シオン殿下はニッコリと微笑む。
「また明日ね」
そう言われても、返事はできない。今までのようにシオン殿下と密会するわけにはいかない。
なぜなら、私は決して二人の王子殿下に近づいてはいけないから。だから、憧れているシオン殿下にも近づかずいつも遠くから眺めていた。
……あれ? でも、別にファンとして近づくくらいなら良かったよね?
婚約者になるわけでもないし、他の女生徒たちがお近づきになるためにローレル殿下やシオン殿下を取り囲んでいる場面を見たこともある。その中に、私が交ざってもよかったはずだ。
どうして今までそうしなかったのか分からない。何か大切なことを忘れているような気がする。
「リナリア?」
シオン殿下に名前を呼ばれて、私は我に返った。
なんて言っていいのか分からず「失礼します」と伝えると、なんだか他人行儀になってしまった。殿下の表情は、どこか寂しそうに見える。
シオン殿下を乗せた馬車は、学園に戻るために走り出した。私は、その馬車が見えなくなるまで見送っていた。
一人になると、深いため息が出る。
今日は、いろんなことがありすぎて頭が痛いわ。
出迎えてくれたメイドが「お嬢様、大丈夫ですか⁉」と心配してくれている。
「少し頭が痛くて」
メイドは「風邪ですかねぇ?」と言いながら今日は早く寝るように勧めてくれた。
早めにベッドに入った私は、子どものころの夢を見た。