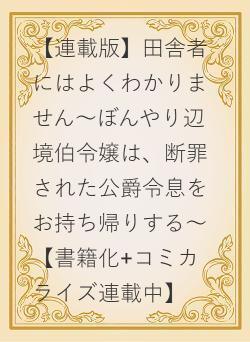メニュー
この作家の他の作品
表紙を見る
第一王子の婚約者ヴィオラを断罪の真っ最中に、聖女セアラは転生前の記憶を思い出した。
(あ、これ、私、今から断罪返しされるんじゃ……?)
断罪返しされたヒロインの末路は、死罪や娼館行きなど悲惨。
「い、いやぁあああああ!?」
生き残るためにセアラが必死にあがいた結果、なんとか生き残ることに成功。
その後、自分が痛いヒロインだと自覚したセアラは、神殿に入り大人しく過ごしていたが、セアラの世話役の神官もまた乙女ゲームの攻略対象者で……。
※だいぶ前に書いた短編の設定を変えて、恋愛要素を足して書き直したものです。
表紙を見る
私は『邪気を体内に取り込んで浄化する』という力を持つ聖女だった。でも、そのせいで体中に黒い文様が浮かび『邪気食い聖女』と嫌悪されている。
だから、新しい聖女が現れたとたんに、婚約者の第三王子に婚約破棄され神殿から追い出されてしまった。
「婚約破棄はいいけれど、お金がないと実家が困るわ……」
私の大好きな家族は貧乏男爵家。これから、弟のアカデミー入学も、妹のデビュタントも控えているのに。困った私に、元婚約者は次の働き先を紹介してくれた。
「お前に似合いの醜い男がいる」
『血まみれ公爵』と呼ばれる方の元で下働きとして働くはずが、ある理由から私は公爵様と仲良くなり……?
一方そのころ、聖女を追い出した元婚約者は大変な目にあっていた。
表紙を見る
田舎から出てきた私は、結婚相手を探すために王都の夜会に参加していました。
そんな中、とつじょと行われた王女殿下による婚約破棄。
婚約破棄をつきつけられた公爵令息テオドール様を助ける人はだれもいません。
ちょっと、だれか彼を助けてあげてくださいよ!
仕方がないので勇気をふりしぼって私が助けることに。テオドール様から話を聞けば、公爵家でも冷遇されているそうで。
あのえっと、もしよければ、一緒に私の田舎に来ますか? 何もないところですが……。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
【改稿版】罰ゲームで私はウソの告白をされるそうです~モブ令嬢なのに初恋をこじらせているヤンデレ王子に溺愛されています~【電子書籍化進行中】
を読み込んでいます