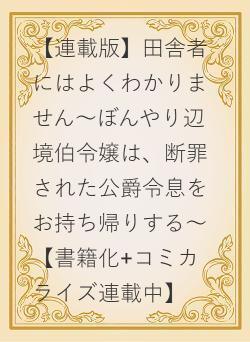馬車の待合室に入ると、ピンク色の髪が見えた。珍しいストロベリーブロンドの髪を持っているのは、この学園内では私の友人ケイトだけだ。
私に気がついたケイトは、笑顔で手を振ってくれる。他の生徒達はもう帰ったようで、待合室には私達しか残っていない。
「お帰り、リナリア。ゼダ様とのデートは楽しかった?」
「う、うん、それなんだけど……」
ケイトは、私とゼダ様が付き合っていると勘違いしている。でも、明日からはシオン殿下の恋人のふりをすることになっているので、今ここで誤解を解かないとややこしいことになってしまう。
ケイトは「ゼダ様って、殿下達の護衛だよね? 真面目そうだし素敵だわ」とうっとりしている。
「ケイトは、ゼダ様みたいな方が好きなの?」
「好きっていうか、ああいう人となら幸せになれそうって思う」
誰もが振り返る美少女ケイトが、ゼダ様をほめるのは意外だった。
確かにゼダ様は真面目そうな好青年だけど、髪色も瞳の色もブラウンで、どちらかというと私と同じで『モブ』と呼ばれるような外見だ。
それがダメだというわけではないけど、ケイトにはもっと華やかな男性が似合うのにと思ってしまう。
ということは、私とシオン殿下が一緒にいるところを見た人も、『シオン殿下にはもっと華やかな女性が似合うのに』と絶対に思うわね。
だからこそ、ケイトの兄サジェスも『どうしてこんなモブ女が妹の友達なんだ?』と怒っている。
そんなことを言われても、仲良くなった友達がたまたま美少女だったんだから仕方ないじゃない。
そして、初めて好きになった人がたまたまこの国の王子様でとんでもない美形に成長してしまったのだから仕方ない。
私ってもしかして、美形好き? いやいや、いくら顔が良くてもサジェスとかローレル殿下みたいな人は絶対に嫌だもの。やっぱり人は中身が大切よ。
そんなことを考えていると、ケイトは自分の頬に手をそえてフゥとため息をついた。
「私ね、昔から変な人にからまれることが多くて……。だから、人を見る目だけはしっかりしているという自信があるの。リナリアとゼダ様はとても良い人よ。これは断言できるわ」
「ありがとう……と言いたいところだけど、実は私、そんなに良い人でもないの」
純粋に信じてくれているケイトに罪悪感を覚えながら、私は「ゼダ様とはお付き合いしていないわ。私、本当はシオン殿下とお付き合いしているの」とウソを重ねた。
恋人のふりだけど、それは言えない……。ごめんね、ケイト。
どこから秘密が漏れるか分からない。作戦を成功させるためには、友達にも真実を黙っていたほうがいい。
ケイトは大きな瞳をさらに大きく見開きながら「シオン殿下?」と呟いた。
「シオン殿下ってあのシオン殿下⁉ それって大丈夫なの⁉」
シオン殿下の悪いウワサを知っている人なら心配して当然だ。
「大丈夫よ。シオン殿下は、すごくお優しいわ」
「そ、そう?」
ケイトは何か言いたそうだったけど、それ以上何も言わなかった。気まずくなった私が視線をそらすと、ケイトのお迎えの馬車が見えた。
「……あれ? ケイト。お迎えの馬車、もう来ているわよ」
「あ、うん、今日はあなたが来るのを待っていたの。……これ」
ケイトは、戸惑いながら白い封筒を出した。
「これ、サジェスお兄様がどうしてもあなたに渡してほしいって。何度も断ったんだけど、しつこくて……」
大嫌いなサジェスの名前を聞いたとたんに、私のは頬が引きつってしまう。
「お兄様に『ひどいことは書いていないよね?』って何度も確認したから、大丈夫だと思うけど」
ケイトは琥珀色の綺麗な瞳でこちらを見つめながら「やっぱり、捨てたほうが良かった?」と聞いてくれた。
「ううん、一応読むわ」
封筒を見る限りおかしなものは入っていなさそうだけど、封を切ったら中にカミソリが入っていて、私の指が切れるとかないわよね?
私が慎重に封筒を開けると、中には一枚だけ紙が入っていた。そこには荒々しい字で『学園内の庭園噴水前にて待つ。必ず一人で来い』とだけ書かれている。
横から手紙を覗いていたケイトが「何これ、果たし状?」と怒りで声を震わせた。
「お兄様の手紙なんて、受け取らなければ良かった!」
ケイトは私から手紙を取り上げ、グシャグシャに丸めて待合室の角に置かれているゴミ箱に投げ入れた。
「リナリア、行かなくていいからね! お兄様なんて、ずっと一人で待っていたらいいのよ!」
ケイトの瞳には涙が浮かんでいる。
「ご、ごめ、リナリア、いつもお兄様が失礼なことをしてごめんなさい。私と友達、やめないで……」
「やめるわけないでしょう? サジェスは大嫌いだけど、あなたのことは大好きよ。それに、私のほうこそシオン殿下とのことを今まで黙っていてごめんなさい」
そう伝えると、ケイトは涙を指でぬぐいながら「それはいいの、本当のことを言ってくれて嬉しかったから。気にしないで」と笑ってくれた。
「ありがとう。私もサジェスのことは気にしていないわ。だから、ケイトも気にしないでね。また明日」
「うん、また明日」
私は馬車に乗り込むケイトに手を振った。
私は一人っ子だからずっと兄弟に憧れていた。でも、サジェスの行動に困っているケイトを見ていると、兄弟がいたらいたで大変なのねと思ってしまう。
「さてと」
私はゴミ箱の中から、ケイトが捨てたサジェスからの手紙を拾いシワを伸ばした。
「学園内の庭園噴水前、ね」
あのサジェスのことだから無視して帰ると、明日以降、何をされるか分からない。明日からは『シオンの恋人のふりをする』という重大任務が待っているので、それをサジェスに邪魔されるわけにはいかない。
なんの用だか知らないけど、話だけは聞いてあげるわ。
私に気がついたケイトは、笑顔で手を振ってくれる。他の生徒達はもう帰ったようで、待合室には私達しか残っていない。
「お帰り、リナリア。ゼダ様とのデートは楽しかった?」
「う、うん、それなんだけど……」
ケイトは、私とゼダ様が付き合っていると勘違いしている。でも、明日からはシオン殿下の恋人のふりをすることになっているので、今ここで誤解を解かないとややこしいことになってしまう。
ケイトは「ゼダ様って、殿下達の護衛だよね? 真面目そうだし素敵だわ」とうっとりしている。
「ケイトは、ゼダ様みたいな方が好きなの?」
「好きっていうか、ああいう人となら幸せになれそうって思う」
誰もが振り返る美少女ケイトが、ゼダ様をほめるのは意外だった。
確かにゼダ様は真面目そうな好青年だけど、髪色も瞳の色もブラウンで、どちらかというと私と同じで『モブ』と呼ばれるような外見だ。
それがダメだというわけではないけど、ケイトにはもっと華やかな男性が似合うのにと思ってしまう。
ということは、私とシオン殿下が一緒にいるところを見た人も、『シオン殿下にはもっと華やかな女性が似合うのに』と絶対に思うわね。
だからこそ、ケイトの兄サジェスも『どうしてこんなモブ女が妹の友達なんだ?』と怒っている。
そんなことを言われても、仲良くなった友達がたまたま美少女だったんだから仕方ないじゃない。
そして、初めて好きになった人がたまたまこの国の王子様でとんでもない美形に成長してしまったのだから仕方ない。
私ってもしかして、美形好き? いやいや、いくら顔が良くてもサジェスとかローレル殿下みたいな人は絶対に嫌だもの。やっぱり人は中身が大切よ。
そんなことを考えていると、ケイトは自分の頬に手をそえてフゥとため息をついた。
「私ね、昔から変な人にからまれることが多くて……。だから、人を見る目だけはしっかりしているという自信があるの。リナリアとゼダ様はとても良い人よ。これは断言できるわ」
「ありがとう……と言いたいところだけど、実は私、そんなに良い人でもないの」
純粋に信じてくれているケイトに罪悪感を覚えながら、私は「ゼダ様とはお付き合いしていないわ。私、本当はシオン殿下とお付き合いしているの」とウソを重ねた。
恋人のふりだけど、それは言えない……。ごめんね、ケイト。
どこから秘密が漏れるか分からない。作戦を成功させるためには、友達にも真実を黙っていたほうがいい。
ケイトは大きな瞳をさらに大きく見開きながら「シオン殿下?」と呟いた。
「シオン殿下ってあのシオン殿下⁉ それって大丈夫なの⁉」
シオン殿下の悪いウワサを知っている人なら心配して当然だ。
「大丈夫よ。シオン殿下は、すごくお優しいわ」
「そ、そう?」
ケイトは何か言いたそうだったけど、それ以上何も言わなかった。気まずくなった私が視線をそらすと、ケイトのお迎えの馬車が見えた。
「……あれ? ケイト。お迎えの馬車、もう来ているわよ」
「あ、うん、今日はあなたが来るのを待っていたの。……これ」
ケイトは、戸惑いながら白い封筒を出した。
「これ、サジェスお兄様がどうしてもあなたに渡してほしいって。何度も断ったんだけど、しつこくて……」
大嫌いなサジェスの名前を聞いたとたんに、私のは頬が引きつってしまう。
「お兄様に『ひどいことは書いていないよね?』って何度も確認したから、大丈夫だと思うけど」
ケイトは琥珀色の綺麗な瞳でこちらを見つめながら「やっぱり、捨てたほうが良かった?」と聞いてくれた。
「ううん、一応読むわ」
封筒を見る限りおかしなものは入っていなさそうだけど、封を切ったら中にカミソリが入っていて、私の指が切れるとかないわよね?
私が慎重に封筒を開けると、中には一枚だけ紙が入っていた。そこには荒々しい字で『学園内の庭園噴水前にて待つ。必ず一人で来い』とだけ書かれている。
横から手紙を覗いていたケイトが「何これ、果たし状?」と怒りで声を震わせた。
「お兄様の手紙なんて、受け取らなければ良かった!」
ケイトは私から手紙を取り上げ、グシャグシャに丸めて待合室の角に置かれているゴミ箱に投げ入れた。
「リナリア、行かなくていいからね! お兄様なんて、ずっと一人で待っていたらいいのよ!」
ケイトの瞳には涙が浮かんでいる。
「ご、ごめ、リナリア、いつもお兄様が失礼なことをしてごめんなさい。私と友達、やめないで……」
「やめるわけないでしょう? サジェスは大嫌いだけど、あなたのことは大好きよ。それに、私のほうこそシオン殿下とのことを今まで黙っていてごめんなさい」
そう伝えると、ケイトは涙を指でぬぐいながら「それはいいの、本当のことを言ってくれて嬉しかったから。気にしないで」と笑ってくれた。
「ありがとう。私もサジェスのことは気にしていないわ。だから、ケイトも気にしないでね。また明日」
「うん、また明日」
私は馬車に乗り込むケイトに手を振った。
私は一人っ子だからずっと兄弟に憧れていた。でも、サジェスの行動に困っているケイトを見ていると、兄弟がいたらいたで大変なのねと思ってしまう。
「さてと」
私はゴミ箱の中から、ケイトが捨てたサジェスからの手紙を拾いシワを伸ばした。
「学園内の庭園噴水前、ね」
あのサジェスのことだから無視して帰ると、明日以降、何をされるか分からない。明日からは『シオンの恋人のふりをする』という重大任務が待っているので、それをサジェスに邪魔されるわけにはいかない。
なんの用だか知らないけど、話だけは聞いてあげるわ。