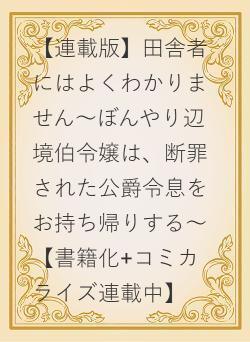信じられないことに、私はシオン殿下と清く正しいお付き合いをしている。もちろん『お付き合いをしているふり』だけど。
シオン殿下が言うには、「恋多き男のウワサをなくすには、付き合う女性を一人に絞ればいいと思うんだ。そうすれば、自然とウワサも消えるはず」とのこと。
「なるほど。それにシオンが恋人に親切にしている姿を皆に見せれば、乱暴や性格が悪いというウワサのイメージも薄れるかもしれません」
「そうだね」
同意しながらも、シオン殿下の紫色の瞳が不安そうに揺れている。
「でも、そうなると、私だけのリナリアが学園内で有名になってしまう」
「そうですねぇ」
あの第二王子シオン殿下の新恋人が、こんなモブ女だと分かれば学園中が驚くでしょうね。
それに、シオン殿下におかしなウワサが流れている今でも、第二王子の婚約者の座を狙っている女生徒はたくさんいる。そんな殿下を独り占めするのだから、他の女生徒たちからのイジメや嫌がらせも覚悟しておかないと。
「殿下……じゃなくて、シオンの悪いウワサが消えるなら、私はなんでもします」
私の忠誠心が伝わったようで、シオン殿下は「なんでも、か。うん、良い言葉だね」と満足そうだ。
「それに、シオンの恋人の役は私にしかできませんから」
「リナリア……。やっと私の気持ちに気がついて……もちろん、そうだよ」
感極まっているシオン殿下に、私は微笑みかけた。
「やっぱりそうですよね! だって、私はシオンとは結婚できないので、ウワサが消えて別れるときに都合が良いですもんね。さすがシオン殿下(・・)、先のことまで考えていらっしゃる」
満面の笑みで私が拍手を送ると、シオン殿下はあの凄みのある笑みを浮かべた。
「リナリア……うん。そうだね、君はそういう人だよ」
フッフッフッと怪しく笑いながら「やっぱり君にはお仕置きが必要だね」と言ったシオン殿下の瞳は少しも笑っていない。
「え? どうしてですか?」
「それは……今、私を『シオン殿下』と呼んだから、かな?」
なんだか、はぐらかされているような気がするけど、確かにうっかり『シオン殿下』と呼んでしまった。
「お仕置きは、なんですか?」
優しいシオン殿下の考えるお仕置きは、どんなものだろうかと少し興味が湧いた。正直に言うと、前回、殿下の考えた罰ゲームは、私には罰ゲームになっていない。だって、恋人のふりだなんて、私にはただのご褒美だから。
未だに手を恋人繋ぎしているシオン殿下は、ニッコリと微笑んだ。
「じゃあ、リナリアが私を『殿下』と呼んだから、お仕置きで私にキスしてもらおうかな」
私ったら、殿下の魅力に脳がやられて、また都合の良い幻聴が聞こえているわ。
そんな自分にあきれながらも「それはどういう意味ですか?」と冷静に聞き返した。
「そのままの意味だけど?」
「そのままって、じゃあ、私が間違えて『殿下』と呼んでしまったら、シオンにキスして良いことになりますけど?」
自分で言っていて意味が分からない。
「そうだよ。はい、どうぞ」
そう言ったシオン殿下は好きにしてくれと言わんばかりに目を瞑る。紫水晶のような瞳が閉じられると、そこには無防備な顔があった。
何これ……? 控えめに言って神々が創った芸術品だわ。
そう思ってしまうほどシオン殿下の顔は整っている。
もしかして、殿下って『罰ゲーム』とか『お仕置き』の正しい意味が分かっていないのかしら?
生まれも育ちも高貴なシオン殿下には、関わりのない言葉なのかもしれない。もしくは、いろんな女性と軽々しくキスすることが当たり前の人生なのかしら? 後者だと思うと、少しだけ胸が痛む。
いつまでたっても目を開かないシオン殿下を見る限り『キスして』発言は本気のようだ。
私は困った末に、恋人繋ぎをしているシオン殿下の手を持ち上げ、その手の甲にほんの少しだけ唇を押し当てた。
すっごく恥ずかしい……。
私が赤面しながらうつむいていると、「うーん、これはキスする場所を指定しなかった私が悪いね」というシオン殿下の呟きが聞こえてきた。
私の顔を覗き込んだシオン殿下の顔には、悪戯っこのような笑みが浮かんでいる。
「仕方がないから、今日はこれで許してあげる。もう時間だね」
気がつけば、お迎えの馬車が来る時間になってしまっている。
シオン殿下は先に立ち上がると、私の手を優しく引いて立たせてくれた。サロンの入口までの短い距離なのに、私達の手はしっかりと恋人繋ぎになっている。
「またね。リナリア」
シオン殿下の温かさを感じられなくなった手のひらは、なんだか物足りない。礼儀正しく頭を下げたあと、私はサロンから出た。ふと見ると、扉のすぐ側にゼダ様が姿勢よく立っている。
あ、そうだわ。シオン殿下に明日の朝、本当に一緒に登校するのか聞かないと!
私が慌てて振り返ると、サロンの扉の隙間からシオン殿下の姿が見えた。殿下はなぜか自身の右手をジッと見つめている。そして、その右手がとても大切なものであるかのように胸に抱え込んだ。
えっと、シオン殿下は何をしているのかしら?
しばらくそうしていたかと思うとシオン殿下は、うっとりとした表情を浮かべながら自身の右手の甲にゆっくりと顔を近づけていった。そこは、先ほど私がキスした場所で……。
急に私の目の前で扉が閉まり、シオン殿下が見えなくなった。ゼダ様が不自然な咳払いをしながら扉を押さえている。
「ゼダ様?」
ゼダ様は、苦悩するような表情を浮かべながら「リナリア嬢は、シオン殿下のことをどうお思いですか?」と聞いてきた。
「シオン殿下は、とてもお優しく美しくて、私のような者にも丁寧に接してくださる素敵な方です」
私が淀みなくスラスラとシオン殿下を褒め称えている間に、ゼダ様の顔色がどんどん悪くなっていく。
「リナリア嬢」
「はい」
「もし、もしですよ? 殿下がそのような方ではなかったらどうしますか?」
「どうって……?」
私が戸惑っていると、ゼダ様はサロンの扉に背を向けて歩き出した。いつものように馬車の待合室の付近まで、私を送ってくれるようだ。
「ゼダ様、先ほどのお話ですが……」と私が声をかけると、ゼダ様は重いため息をついた。
「シオン殿下は、あなたがおっしゃるとおり、とても聡明でお優しい方です。私としても、お仕えできて光栄です」
「はい、そうですよね!」
ゼダ様がシオン殿下の悪いウワサを信じていないことが分かって、私は嬉しくなった。でも、ゼダ様の顔は青いままだ。
「リナリア嬢……。例えばですよ、シオン殿下が一人の女性を執拗に付け回したり、その女性に執着しすぎたりして、その方に関することになると道徳的な考えすらも吹き飛んでしまうような危ない一面があった場合、あなたはシオン殿下のことをどう思いますか?」
ゼダ様があまりに深刻な顔をしているので驚いて何も言えずにいると、ゼダ様は急に私の背後に鋭い視線を向けた。
「リナリア嬢、お話の続きはまた今度!」
そう小声で囁くとゼダ様は風のように走り去った。
いったい何が?
私が背後を振り返ると、遠目でも分かるくらいの輝く金髪を持った男子生徒が、こちらに歩いて来ているところだった。
この学園内で、あれほど美しい金髪を持っているのは王子様たちだけだ。
まっすぐ私に近づいてきた王子様は、シオン殿下の学年がつける青色のネクタイをしていた。でも、私はすぐにその正体に気がついた。
ローレル殿下……。
シオン殿下が言うには、「恋多き男のウワサをなくすには、付き合う女性を一人に絞ればいいと思うんだ。そうすれば、自然とウワサも消えるはず」とのこと。
「なるほど。それにシオンが恋人に親切にしている姿を皆に見せれば、乱暴や性格が悪いというウワサのイメージも薄れるかもしれません」
「そうだね」
同意しながらも、シオン殿下の紫色の瞳が不安そうに揺れている。
「でも、そうなると、私だけのリナリアが学園内で有名になってしまう」
「そうですねぇ」
あの第二王子シオン殿下の新恋人が、こんなモブ女だと分かれば学園中が驚くでしょうね。
それに、シオン殿下におかしなウワサが流れている今でも、第二王子の婚約者の座を狙っている女生徒はたくさんいる。そんな殿下を独り占めするのだから、他の女生徒たちからのイジメや嫌がらせも覚悟しておかないと。
「殿下……じゃなくて、シオンの悪いウワサが消えるなら、私はなんでもします」
私の忠誠心が伝わったようで、シオン殿下は「なんでも、か。うん、良い言葉だね」と満足そうだ。
「それに、シオンの恋人の役は私にしかできませんから」
「リナリア……。やっと私の気持ちに気がついて……もちろん、そうだよ」
感極まっているシオン殿下に、私は微笑みかけた。
「やっぱりそうですよね! だって、私はシオンとは結婚できないので、ウワサが消えて別れるときに都合が良いですもんね。さすがシオン殿下(・・)、先のことまで考えていらっしゃる」
満面の笑みで私が拍手を送ると、シオン殿下はあの凄みのある笑みを浮かべた。
「リナリア……うん。そうだね、君はそういう人だよ」
フッフッフッと怪しく笑いながら「やっぱり君にはお仕置きが必要だね」と言ったシオン殿下の瞳は少しも笑っていない。
「え? どうしてですか?」
「それは……今、私を『シオン殿下』と呼んだから、かな?」
なんだか、はぐらかされているような気がするけど、確かにうっかり『シオン殿下』と呼んでしまった。
「お仕置きは、なんですか?」
優しいシオン殿下の考えるお仕置きは、どんなものだろうかと少し興味が湧いた。正直に言うと、前回、殿下の考えた罰ゲームは、私には罰ゲームになっていない。だって、恋人のふりだなんて、私にはただのご褒美だから。
未だに手を恋人繋ぎしているシオン殿下は、ニッコリと微笑んだ。
「じゃあ、リナリアが私を『殿下』と呼んだから、お仕置きで私にキスしてもらおうかな」
私ったら、殿下の魅力に脳がやられて、また都合の良い幻聴が聞こえているわ。
そんな自分にあきれながらも「それはどういう意味ですか?」と冷静に聞き返した。
「そのままの意味だけど?」
「そのままって、じゃあ、私が間違えて『殿下』と呼んでしまったら、シオンにキスして良いことになりますけど?」
自分で言っていて意味が分からない。
「そうだよ。はい、どうぞ」
そう言ったシオン殿下は好きにしてくれと言わんばかりに目を瞑る。紫水晶のような瞳が閉じられると、そこには無防備な顔があった。
何これ……? 控えめに言って神々が創った芸術品だわ。
そう思ってしまうほどシオン殿下の顔は整っている。
もしかして、殿下って『罰ゲーム』とか『お仕置き』の正しい意味が分かっていないのかしら?
生まれも育ちも高貴なシオン殿下には、関わりのない言葉なのかもしれない。もしくは、いろんな女性と軽々しくキスすることが当たり前の人生なのかしら? 後者だと思うと、少しだけ胸が痛む。
いつまでたっても目を開かないシオン殿下を見る限り『キスして』発言は本気のようだ。
私は困った末に、恋人繋ぎをしているシオン殿下の手を持ち上げ、その手の甲にほんの少しだけ唇を押し当てた。
すっごく恥ずかしい……。
私が赤面しながらうつむいていると、「うーん、これはキスする場所を指定しなかった私が悪いね」というシオン殿下の呟きが聞こえてきた。
私の顔を覗き込んだシオン殿下の顔には、悪戯っこのような笑みが浮かんでいる。
「仕方がないから、今日はこれで許してあげる。もう時間だね」
気がつけば、お迎えの馬車が来る時間になってしまっている。
シオン殿下は先に立ち上がると、私の手を優しく引いて立たせてくれた。サロンの入口までの短い距離なのに、私達の手はしっかりと恋人繋ぎになっている。
「またね。リナリア」
シオン殿下の温かさを感じられなくなった手のひらは、なんだか物足りない。礼儀正しく頭を下げたあと、私はサロンから出た。ふと見ると、扉のすぐ側にゼダ様が姿勢よく立っている。
あ、そうだわ。シオン殿下に明日の朝、本当に一緒に登校するのか聞かないと!
私が慌てて振り返ると、サロンの扉の隙間からシオン殿下の姿が見えた。殿下はなぜか自身の右手をジッと見つめている。そして、その右手がとても大切なものであるかのように胸に抱え込んだ。
えっと、シオン殿下は何をしているのかしら?
しばらくそうしていたかと思うとシオン殿下は、うっとりとした表情を浮かべながら自身の右手の甲にゆっくりと顔を近づけていった。そこは、先ほど私がキスした場所で……。
急に私の目の前で扉が閉まり、シオン殿下が見えなくなった。ゼダ様が不自然な咳払いをしながら扉を押さえている。
「ゼダ様?」
ゼダ様は、苦悩するような表情を浮かべながら「リナリア嬢は、シオン殿下のことをどうお思いですか?」と聞いてきた。
「シオン殿下は、とてもお優しく美しくて、私のような者にも丁寧に接してくださる素敵な方です」
私が淀みなくスラスラとシオン殿下を褒め称えている間に、ゼダ様の顔色がどんどん悪くなっていく。
「リナリア嬢」
「はい」
「もし、もしですよ? 殿下がそのような方ではなかったらどうしますか?」
「どうって……?」
私が戸惑っていると、ゼダ様はサロンの扉に背を向けて歩き出した。いつものように馬車の待合室の付近まで、私を送ってくれるようだ。
「ゼダ様、先ほどのお話ですが……」と私が声をかけると、ゼダ様は重いため息をついた。
「シオン殿下は、あなたがおっしゃるとおり、とても聡明でお優しい方です。私としても、お仕えできて光栄です」
「はい、そうですよね!」
ゼダ様がシオン殿下の悪いウワサを信じていないことが分かって、私は嬉しくなった。でも、ゼダ様の顔は青いままだ。
「リナリア嬢……。例えばですよ、シオン殿下が一人の女性を執拗に付け回したり、その女性に執着しすぎたりして、その方に関することになると道徳的な考えすらも吹き飛んでしまうような危ない一面があった場合、あなたはシオン殿下のことをどう思いますか?」
ゼダ様があまりに深刻な顔をしているので驚いて何も言えずにいると、ゼダ様は急に私の背後に鋭い視線を向けた。
「リナリア嬢、お話の続きはまた今度!」
そう小声で囁くとゼダ様は風のように走り去った。
いったい何が?
私が背後を振り返ると、遠目でも分かるくらいの輝く金髪を持った男子生徒が、こちらに歩いて来ているところだった。
この学園内で、あれほど美しい金髪を持っているのは王子様たちだけだ。
まっすぐ私に近づいてきた王子様は、シオン殿下の学年がつける青色のネクタイをしていた。でも、私はすぐにその正体に気がついた。
ローレル殿下……。