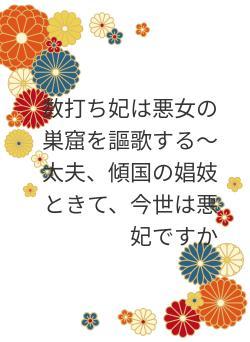「……どうしてこうなったのかしら?」
ザルハッシュ王太子直筆の招待状を無視できない立場の私は、訪れた夜会会場で思わず首を捻る。
「ヒッ」
小さな悲鳴は上げたのはチムニア公爵令嬢。私と目が合ったからか、恐怖に慄いてしまう。
チムニア嬢は服も濡れていないし、髪も整えて薄化粧。ちょっぴり疲労が滲んでいても、お肌にはピンと張りがある。
私の求めるブヨブヨの腐乱死体姿じゃないわ?
チムニア嬢をエスコートしているのは、世間一般的には麗しい部類に入る、金髪碧眼の王子様。彼こそが、この国の王太子であるザルハッシュ殿下。
ザルハッシュ王太子が直々に招待状を送ってきたからと言って、エスコートされない事は初めからわかっていたわ。だって私は子爵令嬢ですもの。
だから残念な気持ちが湧く事はない。
けれど王家主催の夜会に、まさかチムニア公爵令嬢を伴って現れるなんて……やるわね!
チムニア嬢が水没しなかった上に、この状況。ザルハッシュ殿下がチムニア嬢を救出したに違いないわ! 私、間違いなく断罪されちゃうのね!
今日こそ実刑――恐らくは無期懲役か国外追放、もしくは処刑――を言い渡されると心からワクワクする。
なのに……また期待外れに終わりそうな予感がするのは、どうして?
「では、認めるのだな?」
会場にいる大半の人間が、王太子と公爵令嬢の慶び事を想像していたはずよ。周りの人間は、期待に満ちた眼差しを2人の主役に送っていた。
そんな雰囲気の中、ザルハッシュ王太子が神妙な顔つきのまま、チムニア嬢に……何の確認かしら? 何かを確認したと思ったら、突然チムニア嬢を突き飛ばしてしまう。
するとチムニア嬢の父親である宰相が、慌てた様子で駆け寄った。
更にそれを見計らったかのように、タイミング良く騎士が現れて宰相を捕縛。
突然始まる、チムニア公爵家の断罪劇に、首をかしげる私。
恋愛小説の世界なら、王太子は令嬢の肩を抱き、悪役令嬢(配役;私のはずが、何故かチムニア嬢へチェンジ?)1人を断罪する。
これがセオリーよね?
なのに何がどうしたら、王太子単独で、家ごと断罪するシーンになるの?
「認めます! 認めますから! もう、もう……」
憐れな程、恐怖にガタガタ震えながら、罪を肯定するチムニア嬢。私と先日別れた時より、激しく震えている。
「王太子殿下! 冤罪です! 第一、陛下がお認めになるはずがありません!」
激高し、肯定断固拒否する宰相に、親子で面白いくらいの温度差を感じてしまう。
「チムニア公爵よ、そなたは我が王家を侮っておるのか。既に陛下は、そなたの宰相解任について決済しておる」
「そんな!?」
「脱税、人身売買、その他の暗殺事件についても、そこにいるチムニア嬢より証拠提出を受けた」
「何だと!? 貴様、それでも私の娘か!」
騎士に腕を捻られたまま、宰相が顔だけを娘に向ける。悪鬼の如き形相で、叫ぶ言葉は何だか陳腐。
ザルハッシュ王太子直筆の招待状を無視できない立場の私は、訪れた夜会会場で思わず首を捻る。
「ヒッ」
小さな悲鳴は上げたのはチムニア公爵令嬢。私と目が合ったからか、恐怖に慄いてしまう。
チムニア嬢は服も濡れていないし、髪も整えて薄化粧。ちょっぴり疲労が滲んでいても、お肌にはピンと張りがある。
私の求めるブヨブヨの腐乱死体姿じゃないわ?
チムニア嬢をエスコートしているのは、世間一般的には麗しい部類に入る、金髪碧眼の王子様。彼こそが、この国の王太子であるザルハッシュ殿下。
ザルハッシュ王太子が直々に招待状を送ってきたからと言って、エスコートされない事は初めからわかっていたわ。だって私は子爵令嬢ですもの。
だから残念な気持ちが湧く事はない。
けれど王家主催の夜会に、まさかチムニア公爵令嬢を伴って現れるなんて……やるわね!
チムニア嬢が水没しなかった上に、この状況。ザルハッシュ殿下がチムニア嬢を救出したに違いないわ! 私、間違いなく断罪されちゃうのね!
今日こそ実刑――恐らくは無期懲役か国外追放、もしくは処刑――を言い渡されると心からワクワクする。
なのに……また期待外れに終わりそうな予感がするのは、どうして?
「では、認めるのだな?」
会場にいる大半の人間が、王太子と公爵令嬢の慶び事を想像していたはずよ。周りの人間は、期待に満ちた眼差しを2人の主役に送っていた。
そんな雰囲気の中、ザルハッシュ王太子が神妙な顔つきのまま、チムニア嬢に……何の確認かしら? 何かを確認したと思ったら、突然チムニア嬢を突き飛ばしてしまう。
するとチムニア嬢の父親である宰相が、慌てた様子で駆け寄った。
更にそれを見計らったかのように、タイミング良く騎士が現れて宰相を捕縛。
突然始まる、チムニア公爵家の断罪劇に、首をかしげる私。
恋愛小説の世界なら、王太子は令嬢の肩を抱き、悪役令嬢(配役;私のはずが、何故かチムニア嬢へチェンジ?)1人を断罪する。
これがセオリーよね?
なのに何がどうしたら、王太子単独で、家ごと断罪するシーンになるの?
「認めます! 認めますから! もう、もう……」
憐れな程、恐怖にガタガタ震えながら、罪を肯定するチムニア嬢。私と先日別れた時より、激しく震えている。
「王太子殿下! 冤罪です! 第一、陛下がお認めになるはずがありません!」
激高し、肯定断固拒否する宰相に、親子で面白いくらいの温度差を感じてしまう。
「チムニア公爵よ、そなたは我が王家を侮っておるのか。既に陛下は、そなたの宰相解任について決済しておる」
「そんな!?」
「脱税、人身売買、その他の暗殺事件についても、そこにいるチムニア嬢より証拠提出を受けた」
「何だと!? 貴様、それでも私の娘か!」
騎士に腕を捻られたまま、宰相が顔だけを娘に向ける。悪鬼の如き形相で、叫ぶ言葉は何だか陳腐。



![[書籍化、コミカライズ]稀代の悪女、三度目の人生で【無才無能】を楽しむ](https://www.no-ichigo.jp/img/member/1350381/5icnoeybmt-thumb.jpg)