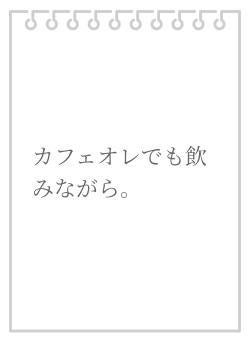階段を降りて昇降口まで歩いていくと、もうほとんど部活の人たちも帰ってしまって誰もいなかった。
外履きを取ると、私のよりひとつ斜め上の靴入れに、敬が手を伸ばした。
「原さんが書記だったら良かったな。」
靴を片手に下げて敬が言った。
「何で?」
私が聞いた。
「別に」
敬が言った。靴をつっかけながら、いつも通りの顔をしている。
靴紐を結びながら外を見ると、透明なガラス扉の向こうの景色はなんとなく青ざめて、まるで空全体が地上に落ちてきているようだった。
敬が言った。
「オレンジじゃない夕方は、特別な人と居る時間って気がするな。」