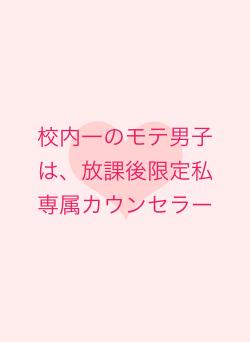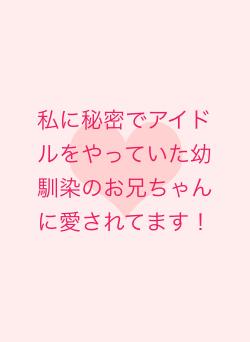私は菅谷くんの言葉に頷いた。あんなに響いているように感じた雨の音はもう耳に入ってこなくなっていた。
「川崎さん、大丈夫?症状出てきた?」
きっと菅谷くんは先ほど私が自分をギュッとしていた所が見えたのだろう。
「うん、大丈夫。もう治まってきたから」
「本当?」
「うん、本当!」
「そっか、なら良かった」
菅谷くんはいつも鋭くて、相手の変化にすぐ気づく。だからこそ出来るだけ迷惑をかけたくなかった。震えそうな手を無理やり力を込めて握って震えを止める。
「あと川崎さん、雨で濡れなかった?」
「全然濡れてないよ。屋根のあるところに始めからいたから」
菅谷くんが本当に雨に濡れていないかを確認するようにパッと私の髪を見た気がした。その菅谷くんの視線が私の膝の上で握りしめている両手まで下がっていったのが分かった。
「川崎さん、本当は症状出てるでしょ」
どうして私は嘘も誤魔化しも上手に出来ないのだろう。言葉を返せない私を見て、菅谷くんは私の症状を確信したようだった。
「川崎さん、手を貸して」
「え……?」
「川崎さん、大丈夫?症状出てきた?」
きっと菅谷くんは先ほど私が自分をギュッとしていた所が見えたのだろう。
「うん、大丈夫。もう治まってきたから」
「本当?」
「うん、本当!」
「そっか、なら良かった」
菅谷くんはいつも鋭くて、相手の変化にすぐ気づく。だからこそ出来るだけ迷惑をかけたくなかった。震えそうな手を無理やり力を込めて握って震えを止める。
「あと川崎さん、雨で濡れなかった?」
「全然濡れてないよ。屋根のあるところに始めからいたから」
菅谷くんが本当に雨に濡れていないかを確認するようにパッと私の髪を見た気がした。その菅谷くんの視線が私の膝の上で握りしめている両手まで下がっていったのが分かった。
「川崎さん、本当は症状出てるでしょ」
どうして私は嘘も誤魔化しも上手に出来ないのだろう。言葉を返せない私を見て、菅谷くんは私の症状を確信したようだった。
「川崎さん、手を貸して」
「え……?」