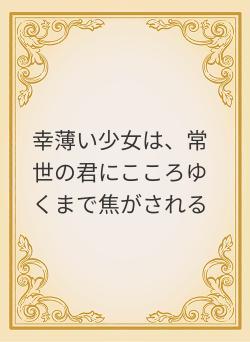それから毎週私たちは顔を合わせるようになった。
カフェ『STAR』の定休日は、私と流星の貸し切り。
でも、いっしょに帰ったのはあれっきり。
さすがにお互い受験生だし、流星は部活も生徒会もやっている。
彼の予定がない日はめったになくて、私は宿題をしたり本を読んだりしながら、流星の帰りを待っていた。
彼が帰ってくるとコーヒーを一杯ごちそうになり、談笑して帰る。
それが私と流星の二人きりの時間。
流星はどう思ってるか知らないけれど、これは私にとっては大きな楽しみだった。
そして、夏が過ぎ、秋が来た。
みんなの話題の中心は、受験のこと、高校のこと。
流星は成績もトップクラスでいつも学年三番以内に入ってる。対して私は中の上くらいだった。
そういえば流星が県外の高校を受験するという話を、こないだ姫野さんから聞いていた。
彼女はクラスの美化委員で、毎週の委員会の時に流星と顔を合わせるらしい。
放課後。
いつもの流星とのひととき。
家までの、帰り道。
暗くなるのが早くなったから、最近は送ってくれるようになった。
少しでも長く流星といられるから、嬉しかった。
「このあと、まだ時間ある?」
「うん」
「ちょっと遠回りしよっか」
流星と並んで、少し遠回りのルートを歩いた。
「流星、県外の高校受験するって聞いたけどほんと?」
「うん? 誰が言ってた?」
「……いろはちゃん」
「いろは? 誰?」
「姫野さん、私のクラスの」
「ああ、そんな話をしたこともあったかな」
「ふーん」
「県外に行くつもりはないよ。無難に地元の海星かな」
「うわ、一番の進学校じゃん。やっぱり偏差値高い人は違うねえ」
「咲麻はどうするの?」
「うーん、高専もありかなって思ってる」
「え、高専? なんで?」
「情報系、興味あるしね」
「高専って男、多いんじゃなかった?」
「それがどうかした?」
「いや、別に……なんでも」
ちらりと横目でうかがう流星の横顔。
表情は読めない。
昔なら泣いてるか笑ってるかのどちらかだった単純な表情も、今では何を考えてるのかわからないことが多々ある。
「ホントのこと言うとさ、咲麻と同じ高校いきたいんだ」
「……そう、なの?」
「うん、咲麻は?」
「まあ、行けるなら……でも海星は、どうだろう……私の成績じゃギリギリアウトかも」
「いっしょに行こうよ。部活も終わったし時間はあるから、いっしょに勉強しよ」
「そう言ってくれて嬉しいけど、りゅうの足は引っ張りたくないし」
「なんで! そんな風に思わないでよ」
珍しく強めの口調で、私につっかかってくる。
「俺は本気だよ。咲麻と同じ学校にいきたいから」
「わかった。そこまで言うなら私も腹くくろうかな。なんとかりゅうにくらいつくよ」
「それでこそ僕の知ってる咲麻だよ! あ、そうだ。来週、楽しみにしててね。じゃあまた」
そう言って流星は軽やかに去っていった。