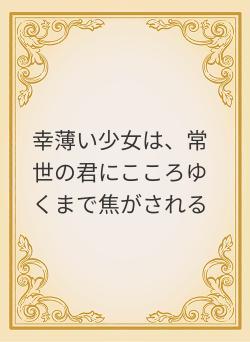「見て! 流星くんだよ!」
誰かが叫んだ。
机に頬杖を付きながら、ちらりと盗み見た視線の先。
運動場の中心でさわやかな笑顔をみせている男の子。
サッカー部のエースで、校内一のイケメンといわれているらしい。
おまけに生徒会長までつとめている。
あれが、あの『りゅう』なの? ホントに?
私の名前は長森咲麻。
この春から中学三年生。
小学五年生の時に転校した私は、三年の時を経て元の町へ戻ってきた。
中三になってまさか環境が変わると思ってなかったけど、知ってる子もいたし転校の不安は少なかった。
なによりも……。
幼少期から、いつもいっしょにいた男の子。
青山流星。
彼とまた会えるという期待が一番大きかったかもしれない。
私の後ろでいっつも泣いてばかりいたはずの幼馴染。
しかし、そんな彼はもうどこにもいなかった。
男子たちに囲まれて楽しそうに話している彼の姿は、あの頃とはまるで違う。
艶のある綺麗な黒髪。
細身だけど適度に鍛え上げられたバランスのいい体。
なによりもその顔つきの違いは遠目でもわかる。
当時の面影は残しつつも、目鼻立ちがくっきりとしてぐんと男らしくなっている。
たった三年でこうも変わるものなのかと、ついつい何度も目をやってしまう。
「はあ……」
気が付くと、ため息をついている自分がいた。
たぶん流星は自分にとって遠い存在になってしまった。
この町に戻ってくることになった時、一番最初に思い浮かべたのは流星のことだった。
どこまでも広がる空の青を眺めながら、当時のことを思い出していた。
「えまちゃん、遊ぼー!」
「いいけど、何して遊ぶ?」
「鬼ごっこ!」
「やだ。りゅうくん、足遅いからつまんない」
「えぇ、そんな……」
私の心無い言葉に、流星はがっくりとしょげて泣きそうになる。
その頃の彼は、ひよわで、泣き虫で、おとなしくて、すぐ風邪をひいて、みんなからよくからかわれていた。
「りゅうくん、なんで泣いてるの」
「あ、えまちゃん……。それが、ね……グス……聞いてよ」
「なに? ハッキリ言いなよ」
「みんなが……グス……ひどいこと言うんだ……」
「だから、なんて?」
「ぼくはヘタだから、ボール遊びの仲間には入れないって」
「ふーん……たしかにりゅうくんヘタだもんね」
「え……えまちゃんまで、ヒドイ……」
「うそうそ、あんなやつらほっといて、わたしともっと大人の遊びをしよっか」
「えっ、大人の遊び?」
「そ、おままごと。わたしはおくさん。りゅうくんはだんなさん役ね!」
私と流星は家が近所ということもあって親同士も仲がよかった。
互いに一人っ子だったため、私たちは兄弟のようにいつもいっしょ。
互いの家で家族を交えて食事することもしょっちゅうあったし。
両親たちは私たちが結婚してくれたらなんてことを何度も口にしたりしたっけ。
「えまちゃん、大きくなったらぼくとけっこんしてください!」
「いや! りゅうくん泣き虫だもん」
「うえーん、えまちゃんにフラれたー!」
そういう時、気恥ずかしくなった私はきまって心にもないことを言ってごまかしていた。
口ではいろいろ言っていても、流星が隣にいてくれることは嬉しかったんだけどね。
むしろずっといっしょにいるものだとばかり思っていた。
無邪気な幼少期はあっという間に終わった。
小学校にあがっても彼との関係はあまり変わらなかった。
「りゅう、まだ食べてるの!?」
「えま……。僕ピーマン苦手でさ……」
「好き嫌いばっかり言ってたら大きくなれないよ? もっとガツガツいきなって」
「ごめん」
「あやまるところも、ダッサイなあ。男ならもっとシャキッとして!」
「う、うん。ごめんね……」
「ふん! 好き嫌いばっかりのりゅうなんてキライ!」
「えー! もっと男らしくするから、嫌いにならないで!」
「それは本当に男らしくなったらね」
「僕はずっとえまちゃんが好きだから……」
その言葉を聞くたびに、内心ではうれしくてうれしくてたまらなかった。
なんだかんだ言って、私も流星が好きだったんだよね。
「咲麻。りゅうくんに会えるの楽しみなんじゃない?」
「べつに」
この町に帰ってきてから最初の週末。
私は休日に母と二人である場所へ向かっていた。
流星の両親がやっているカフェ。
たしか私がここを離れる少し前にオープンし、開店当初はお客さんも少なかったので、流星といっしょによく入り浸っていたのを覚えている。
コーヒーがまだ飲めなかった私はいつもオレンジジュースをもらってたっけ。
三年ぶりに訪れたカフェ『STAR』は町の人気店になっていた。
先に店内に入った私は、後ろの母を振り返る。
「お客さんいっぱいだよ」
「そうねえ。これだとりゅうくんと話せないかもしれないわね」
「だから! べつにりゅうと話しに来たわけじゃないし」
「でも学校でまだ話してないんでしょ?」
「だってクラス違うんだもん」
その時、カウンターにいたアゴヒゲの男性がこちらに手を振った。
「二人ともいらっしゃい。奥のテーブル空いてるからどうぞ!」
マスターでもある流星の父親だ。三年前にはなかったアゴヒゲがマスターの風格を漂わせている。
その後、席につくと流星の母親が水を運んできてくれた。
流星の姿はまだ見えない。いないのかな。
「咲麻ちゃん久しぶりー。おっきくなったねえ。りゅうは今練習行ってて、もうすぐ帰ってくると思うけど」
「えっ! いや……」
うろたえている私の様子を、母が向かいの席でにっこりしながら眺めている。
その後、チーズケーキとコーヒーを注文し、母といっしょにいただいた。
口の中にふわっと広がる濃厚なチーズの風味。
言うことなし。
こんなにおいしかったっけ。
おばさんの作るケーキと、おじさんの淹れるコーヒー。
これは人気店になるのもうなずけるほどのおいしさだった。
「このケーキ、おばさんの手作りなんだよね。おいしいよね」
「すごいわねえ。母さんも作ってみようかな」
そうやって母としゃべっていると、ふいにそばに誰かが立った。
「や、久しぶり」
聞き覚えの無い低い声。
「えっ」
流星だった。
うそ……声……。
いつのまにか声変わりしたようだ。
流星だけど流星じゃない。
私の知らない、新しい流星がそこにいた。
母が感嘆の声をあげる。
「りゅうくん、大きくなったわねえ! 声も変わっちゃって」
「どうも……お久しぶりです」
照れながら母とあいさつをかわす流星。
そんな二人のやりとりを眺めていると、母が私の方を見て微笑んだ。
「お母さん、先に帰るね。二人でゆっくりしてきな」
母の余計な一言に、私はとたんに目を白黒させる。
「いやいや、えっ? だって、部活で疲れてるでしょ? 悪いから」
「俺なら大丈夫。時間あるなら、ちょっと話そうよ」
内心ドキドキしながら、私は小さくうなずいた。
恥ずかしくて流星の目は見れなかったけど。
「ねえ、咲麻、久しぶりにあそこ行こうよ」
やっぱり聞きなれない流星の声。
でも、とても男らしくて耳障りのいい声だった。
店を出た私たちは、二人でよく遊んだ公園に向かった。
並んで歩いていると、流星の身長の高さにおどろいた。
私より低かったはずなのに、この三年間であっという間に追い越されている。
頭一つ分違う彼の顔を見上げながら、何を言おうか考えてしまう。
なんだか、あの頃とは違う空気感……。
うそでしょ……。
何を話せばいいの……。
心臓が不自然に鳴り響く。
流星とただ話すだけなのに、こんなに勇気がいるなんて。
ふいに向こうが、こちらを見ながら吹き出した。
「なんか、何話したらいいかわかんないね」
……。
「ふふっ、私もそう思ってた」
「ホント!? おんなじだね」
このやりとりで、いっきに場が和んだ気がした。
「りゅう、身長伸びたね」
「そう? 咲麻も……変わったよ」
久しぶりに名前を呼ばれ、顔が少し熱くなった。
「変わった? なにが?」
「かわいくなった」
一瞬、呼吸の仕方を忘れるところだった。
とっさに息を吸い込む。
「な、なにそれー! りゅうってそんなキャラだっけ!」
「え、違う違う。ホントのこと言っただけ」
流星はあの頃と同じ澄んだ目で私の顔をのぞいてくる。
けど顔つきはとても男らしくなっていて、悔しいけどカッコいいよね……。
こんなのほんとにもう、反応に困る。
今私の顔、真っ赤になってるんじゃないかな。
私は話題をそらそうと、必死でまくしたてる。
「ねーねー、サッカー部入ってたんだね。見たよこの前、練習。みんなともうまくやってる感じだったね」
「え、見ててくれたの?」
流星の顔に、あの頃のような無邪気な笑顔が咲いた。
「うん、まさかりゅうがサッカーやってるなんてね。ビックリした」
「だよね。いやあ、咲麻に笑われないようにさ、これでもけっこう頑張って練習したんだよ」
ちょ、なにそれ。
なんだかまるで私にいいところ見せようとしたいみたいな。
そんな……泣き虫流星が、まさかね。
彼は申し訳なさそうに声を絞り出す。
「ごめんね。ホントは学校で話したかったんだけど、いろいろ忙しくて」
「んーん、ぜんぜん。生徒会長もしてるんでしょ? すごいよね」
「やりたくなかったんだけど、みんながやれやれってうるさくてさ」
私の知らない人間関係もあるんだよね。
そりゃもちろんそうだよ。
だって生徒会長だもん。
それでいてサッカー部のエース。
みんなから期待されてる存在。
すぐそばを歩いてるはずの流星の足音が、なんだか急に遠ざかっていくような気がした。
翌日。
授業中、ずっと流星のことが頭から離れなかった。
「久しぶりに咲麻に会えて、めっちゃ嬉しかった」
昨日、家まで送ってくれた別れ際、流星はそんなことを言った。
私も、とは言えなかった。
だって、恥ずかしかったし。
その時、ラインも交換した。
昨日から何度も見返してるトーク画面を、またもついつい眺めてしまう。
『今日はありがと! また学校で』
『うん、部活頑張って』
『咲麻が応援してくれるなら、頑張れる』
これだけのやりとり。
これは、まだ続けてもよかったのかな。
迷ってるうちに送りそびれてしまい、タイミングを逃してしまった。
「長森さん?」
「──!」
急に声をかけられて背筋が伸びる。
相手はクラスメイトの、姫野いろはさんだった。
クラスの中で一番目立っているので名前は覚えていた。
髪も肌も綺麗で女の子らしい。うらやましいくらいにかわいい女の子。
小学校は別だったから面識はなく、しゃべるのも初めてだ。
「姫野さん、どうかした?」
「いろはでいーよ。みんなそう呼んでる」
「う、うん……いろはちゃん」
「ありがと、あたしも咲麻ちゃんって呼ぶね」
初めてしゃべるのに、とんでもないコミュ力で距離をつめてくる。
「どう? 学校慣れた?」
「うん……まあまあ、かな」
「聞いたよ。咲麻ちゃんは第二小出身なんだってね」
「うん」
「それでさ、三組の流星と幼馴染なんだって?」
突然出た流星の名前に少し面食らう。
「流星……うん、青山流星のことだよね」
「そうそう、あ、ごめんね。下の名前で呼んでるんだあたし」
笑顔でうなずいてる姫野さんの表情には、妙な余裕があった。
「流星がどうかした?」
「んー、それがめずらしく弱音吐いてたんだよね、あいつ。生徒会に部活にいっぱいいっぱいだって」
その後、休み時間の間、姫野さんは流星のことをずっとしゃべっていた。
サッカーの大会を控えていることや、体育祭の準備で忙しくしていることなど、私の知らないことについて延々と。
きちんとヘアケアがされたさらさら髪を、指先でくるくるとまわしながら彼のことを語る姫野さんは印象的だった。
ああ、流星のこと、ほんとに好きなんだろうな。
彼女はそんなこと一言も言わないけれど、目を見ていれば自然とわかる。
私に向けた笑顔の裏で何を思っているかはわからないけれど、彼のことをこんなに話してくるなんて、理由は一つしか思い当たらない。
もしかして、流星に近づくなって釘さされてる?
「ねえ、咲麻ちゃんは流星と連絡とってたの?」
「いや、とってないよ」
あの頃はスマホを持ってなかったのもあって、ずっと連絡はとれていなかった。
「えー! 幼馴染なのに? そっか、そんなに仲良くなかったんだ?」
「んー、どうだろ……」
「まあいいけど、私はしょっちゅうラインしてるからさー」
胸がズキリといたんだ。
なぜかわからないけど、全身に悪寒が走る。
その時、別の女子が近づいてきて、姫野さんの肩をたたく。
「いろはちゃん、また流星くんの話してるのー? もうさっさとコクって付き合っちゃえばいいのに」
「えー、だって向こうから来てほしいじゃん? きゃはっ」
そんな会話を繰り広げながら、彼女たちは離れていった。
なんでこんなに、こころがいたいんだろう。
みんなの流星に対する評価が180度変わっていたことは、成長した彼を見たら納得だったけど。
なぜか、私の知らない流星になっているような、もうそばにはいてくれない、ずっととおくへ行ってしまったような気がして……。
窓の外に青はなく、どんよりとした雲がどこまでも広がっていた。
『急でごめん、今日時間ある?』
流星からそんなラインが来たのは、ホームルームが終わった直後のこと。
『うん大丈夫、どうかした?』
間を置かず、返信する。
『よかったらうちの店、寄っていかない? 話したいこともあるし』
うそ、ずっと話すきっかけを探してたから、素直にうれしかった。
あれ? でもたしか今日はお店は定休日のはずだけど……。
そう思いつつ、私はそのことには触れずに返信した。
『いいよ』
それだけ打ってから、すぐに教室を飛び出した。
流星は部活が終わってから来るのかな。宿題でもして待ってようかな。
昔と違ってコーヒーのよさもわかるようになったし、また行きたいと思っていたのでテンションが上がっていた。
すると昇降口を出たところで、突然後ろから声をかけられる。
「咲麻! よかった、やっと追いついた!」
「りゅう? あれ、どうしたの?」
息を整えながら、流星は私の横にきて自然と歩く。
「どうして先に帰っちゃうの? 教室に行ったらもういないって言われてびっくりしたよ」
「え……あー」
そういうことか。
放課後にうちの店で、というのはいっしょに帰ろうという意味も含まれていたのだ。
「ごめん。でも、今日は部活ないの?」
「今日はグランド整備の日で、部活は休み」
「ふーん。生徒会は?」
「生徒会の集まりも無し。今日は珍しく早く帰れるから、咲麻といっしょに帰りたいなって思って」
「そっか」
それならそうと言ってくれないと困る。
私はてっきり部活帰りの流星をカフェで待ってるつもりだったし。
でも──。
教室にわざわざ呼びに来たのか、私を。
その時、姫野さんはまだ教室に残っていたのかな。
流星が私を探していること、彼女は気づいたのかな。
別に、気にする必要もないことなんだけど、ついつい気にしてしまう。
「私といっしょに帰っても平気?」
「どういう意味?」
「んーん、別に」
「昔はよくいっしょに帰ったよね」
「うん」
「あそこのコンビニ覚えてる? なくなっちゃったんだよ」
「えー? あれ? でも私がいたころにはもうなかった気がするけど」
「あ、そうだっけ? あはは、そういえばさ──」
二人の話題は自然と小さい頃の思い出話になっていた。
少し変わった街並みを時折話題に出しながら、私たちは並んで帰った。
やっぱりカフェ『STAR』は、今日は休みだった。
「休みなのに、いいの?」
「うん、今日は特別。咲麻と俺の貸し切り」
「……ねえ、いつから『俺』って言うようになったの?」
「え、いつからだろ……中学あがったくらい。変かな?」
成長とともに一人称が変わることは、たぶん男の子にとっては普通なんだろうけど一応聞いてみる。
もしかしたらこっぱずかしいことだし、聞かれたくないかもだけど、そんな彼の反応も見てみたくて意地悪で突っ込んでみた。
「昔は僕って言ってたから、変わったなあって思ってさ」
「俺っていうの、そんなに変?」
「んーん、いいと思うよ」
「そっか。座ってて、今コーヒー淹れるから」
「え、コーヒー!?」
「うん、飲めるでしょ?」
あの頃は私も流星も苦くて飲めなかったけど、お互い少しは味がわかるくらいには成長したはずだ。
でもまさか、流星がコーヒーを淹れてくれるなんて思ってもみなかった。
私以上に大人びた流星に、少し戸惑いを感じる。口には出さないけど。
しばらくしてコーヒーのいい香りが漂ってくる。
「どうぞ、ミルクと砂糖はどうする?」
「んー、いらない」
「ほんとに!? すごいね。俺ミルクは入れるけど」
「……じゃあ、私もミルク」
「あは、なにそれ。でも一回、ブラックで飲んでみて」
すすめられるままに、一口飲んでみる。
「あっ、おいしい」
「お! よかったー」
コーヒーがこんなにおいしく感じたのは初めてだった。
流星が私のために淹れてくれたからだろうか。
その後、二人でまた話をした。
話題は幼稚園や小学校のことばかり。
本当は今の学校でのことも聞いてみたかったけど。
私に気を使ってあの頃の思い出話を語ってくれてるんだろうか。
それから毎週私たちは顔を合わせるようになった。
カフェ『STAR』の定休日は、私と流星の貸し切り。
でも、いっしょに帰ったのはあれっきり。
さすがにお互い受験生だし、流星は部活も生徒会もやっている。
彼の予定がない日はめったになくて、私は宿題をしたり本を読んだりしながら、流星の帰りを待っていた。
彼が帰ってくるとコーヒーを一杯ごちそうになり、談笑して帰る。
それが私と流星の二人きりの時間。
流星はどう思ってるか知らないけれど、これは私にとっては大きな楽しみだった。
そして、夏が過ぎ、秋が来た。
みんなの話題の中心は、受験のこと、高校のこと。
流星は成績もトップクラスでいつも学年三番以内に入ってる。対して私は中の上くらいだった。
そういえば流星が県外の高校を受験するという話を、こないだ姫野さんから聞いていた。
彼女はクラスの美化委員で、毎週の委員会の時に流星と顔を合わせるらしい。
放課後。
いつもの流星とのひととき。
家までの、帰り道。
暗くなるのが早くなったから、最近は送ってくれるようになった。
少しでも長く流星といられるから、嬉しかった。
「このあと、まだ時間ある?」
「うん」
「ちょっと遠回りしよっか」
流星と並んで、少し遠回りのルートを歩いた。
「流星、県外の高校受験するって聞いたけどほんと?」
「うん? 誰が言ってた?」
「……いろはちゃん」
「いろは? 誰?」
「姫野さん、私のクラスの」
「ああ、そんな話をしたこともあったかな」
「ふーん」
「県外に行くつもりはないよ。無難に地元の海星かな」
「うわ、一番の進学校じゃん。やっぱり偏差値高い人は違うねえ」
「咲麻はどうするの?」
「うーん、高専もありかなって思ってる」
「え、高専? なんで?」
「情報系、興味あるしね」
「高専って男、多いんじゃなかった?」
「それがどうかした?」
「いや、別に……なんでも」
ちらりと横目でうかがう流星の横顔。
表情は読めない。
昔なら泣いてるか笑ってるかのどちらかだった単純な表情も、今では何を考えてるのかわからないことが多々ある。
「ホントのこと言うとさ、咲麻と同じ高校いきたいんだ」
「……そう、なの?」
「うん、咲麻は?」
「まあ、行けるなら……でも海星は、どうだろう……私の成績じゃギリギリアウトかも」
「いっしょに行こうよ。部活も終わったし時間はあるから、いっしょに勉強しよ」
「そう言ってくれて嬉しいけど、りゅうの足は引っ張りたくないし」
「なんで! そんな風に思わないでよ」
珍しく強めの口調で、私につっかかってくる。
「俺は本気だよ。咲麻と同じ学校にいきたいから」
「わかった。そこまで言うなら私も腹くくろうかな。なんとかりゅうにくらいつくよ」
「それでこそ俺の知ってる咲麻だよ! あ、そうだ。来週、楽しみにしててね。じゃあまた」
そう言って流星は軽やかに去っていった。