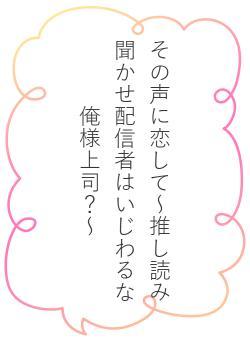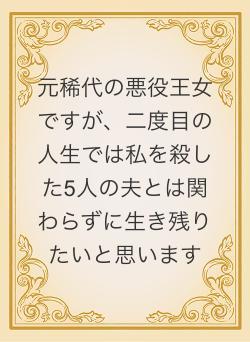「貴様はいらん。出て行け──鬼嫁」
赤胴色の冷たい瞳で見下ろされ、婚約者に捨てられた私は、その国、いや、その世界から追放された。
私、佐野千奈は元々この世界の住人ではない。
こことは違う世界の日本という小さな島国で生まれ、育ち、高校を卒業して就職したばかりの一般人だ。
中学生の頃に両親を事故で亡くし、まだその時まだ四歳と五歳だった弟達と一緒に祖母の家に引き取られ、ずっと『贅沢は敵だ』『働かざる者食うべからず』を合言葉に育ってきた。
そんな祖母も私が就職してすぐに病気でこの世を去り、八歳と九歳になった弟達を私が養っていこうと、日々仕事を頑張っていたはずが──。
ある日突然目が覚めると私はこの世界の、このラザミリ王国という大国にいた。
ファンタジーノベルか。
今流行りの異世界転生ってやつか。
いや、死んだ記憶はないから異世界転移ってやつ?
元々アニメやラノベ、漫画が好きだった私は、妙に落ち着いていたように思う。
──転移してきた場所はラザミリ城、召喚の間。
なんでも、神殿に女神様からのお告げがあったそうで、異世界人を召喚したんだとか。
お告げを聞いた神官曰く、『国王が異世界の女人と婚姻を結べば、国を繁栄に導くであろう』──だそうだ。
国の繁栄のためだけに突然召喚されて、国の繁栄のためだけにあんな、豊満ボディの恋人までいる人の妻になれって、おかしくない!?
自己中か!!
私にも生活はあるんじゃ!!
弟達の面倒どうしてくれんのよ!?
……だけど、一般人である私が逆らうことなどできず、ついには国王アレクサなんとかという長い名前の、御歳二十歳のバカき……いやいや、若き国王と婚約させられてしまったのだ。
が──。
「陛下。このクソ高いドレスの数はなんですか!? こんな高いプレゼントを頻繁に恋人さんに送るとか無駄遣いすぎます!!」
「陛下。もう今月の経費はカツカツみたいんですけど。もうちょい経費抑えてほしいって進言が来てますよ。ていうか女に貢ぐな」
「陛下。国民が苦しんでるっていうのに、こんな贅沢ばかりを愛人にさせるのはいかがなもんなんでしょうか!? パーティしすぎだし料理の量も多すぎて廃棄になる量も多いし、無駄がありすぎです!!」
「陛下、また税を上げるんですか!? いい加減無駄遣いをやめて、王家も身を削る努力をですね──」
質素倹約をモットーに生きてきた私は、我慢ができなかった。
恋人へのドレスやアクセサリーのプレゼント。
豪華な食事に頻繁に開催されるパーティ。
その裏で国民が就職難や重税に苦しんでいるというのに。
この世界に召喚されて六ヶ月。
ぐちぐちと提言し続けた結果が、冒頭の言葉である。
私は再び、目の前で豊満な身体の美女に絡みつかれたままこちらを見下ろす婚約者を見上げた。
今夜も何があるわけでもない、ただ踊り楽しむためだけのパーティの最中。
なんでもない日万歳!! って……意味わからん。
生粋の日本人である私にダンスは踊れないので、今日も壁の花となり、陛下とその恋人のダンスを見ているだけのはずだったのに。
「なんだ、その反抗的な目は。……そうだ。異界には鬼嫁という人ならざる者がいると聞く。お前はそれだ。鬼嫁。そうだな……お前に、魔界への追放と、魔王の嫁となることを命ずる!!」
「はぁ!?」
ざわめくダンスホール。
「千奈様が魔界へ嫁入り!?」
「そんな……ではこの国の繁栄は……」
戸惑いと批判的な声を、ぎろりと鋭い睨みで一蹴し、アレクサ……なんとか国王は薄ら笑いを浮かべて言った。
「魔王と鬼嫁──。人ならざる者同士、似合いじゃないか。さぁ、早々にこの国から出て行け!! 騎士達!! この鬼嫁を魔界へ連れ出せ!!」
若干興奮気味に声を上げた国王からの命令に、戸惑いながらも騎士達が私を取り囲む。
私を追放させたくない。でも逆らえない……か。
この人たちも大変な仕事よね。
「……わかりました。騎士の皆さん、よろしくお願いします」
そして私は、目の前の婚約者だった男へと、にっこりと笑顔を向けた。
「くたばれ、人間」
おおよそ乙女とは思えぬ言葉を吐き捨て、私は呆然とする騎士達を置いていくようにして抜き去り、ホールを後にした。
知ってる?
鬼嫁も──人間ぞ。
「──と、いうわけなのです。どうぞよろしく」
「待てどういうわけだ」
薄暗い部屋。
黒の皮張りのソファに当たり前のように座り、私は目の前の男性を見た。
真っ黒いフードを深く被り、僅かにのぞいた赤い瞳が怪訝そうに私を見る。
これが、今日初めてお会いし、婚姻の書類を交わし私の夫となった──魔王だ。
黒い。
黒すぎる。
この城も装飾品も、魔王自身も。
アニメやゲーム、漫画で見たような典型的な魔王だわ。
城の裏にある門の先。
禁断の森を抜けるとそこはもう魔王の住む世界。
けれど王家の馬車で通った際も、この城の中にも、魔物の姿はない。
なぜ?
駆逐された? この魔王に。
いや、同族にそれはないか。
「はぁ……。まったく……。突然文をよこしたかと思えば、不意打ちの強制婚姻の術付きとは……。しかもその相手はすでに馬車に乗り、城に入っていたのだからタチが悪い」
「それに関しては面目ないです」
でも悪いのはあのアレクサなんとか国王です。
私は一応被害者です。
「あの、魔王ならなんとかできるんじゃないんですか? この強制婚姻」
すごい力があるから魔王なんじゃないの?
なんでこの人、やり返すことなくおとなしくしたがってるのかしら。
魔王の方が国王よりも強そうなイメージなんだけど。
「国王にのみ受け継がれる【封制印】。あれを押されれば、たとえ魔王であろうと簡単には打ち破ることはできん。……厄介な品だ。はぁ……」
そんな便利な品持ってたの!? あのポンコツ国王!!
だからんなに強気なバカが出来上がったのか……。
妙に納得してしまうのは仕方がない。
あんな暴君初めて見たもの。
「魔王立場弱すぎません? 仮にも弟なんですよね? あの人」
「っ、……知っているのか。異世界人が」
「まぁ、ここにきてすぐこの世界についての教育を受けましたし」
そう。国王と魔王。
二人は元は母違いの兄弟だ。
王妃様の子どもとして生まれた魔王で国王の実兄のゼオンなんとか様、側室の子どもとして生まれた実弟の現国王アレクサなんとか様。
5歳で闇の魔力を持っていることがわかった魔王様は、母君である王妃様とともに魔界へ追放された。
そして三つ年下のアレクサなんとか様が王太子に。その母である側妃が王妃になった──。
「私はもう、あれに関わる気はない。ここで静かに生きて、静かに朽ちるのみだ」
えぇ……陰キャか。
「私は滅ぼしたい気持ちでいっぱいなんですけどね、あの国」
だって考えても見てほしい。
いきなり連れてこられて婚約者にさせられて、しかも相手には本命の彼女がいて、恋人贔屓されて挙句婚約破棄で追放よ!?
怒らない方がおかしいわ!!
私はあいにくと捨てられて泣くような可愛げのある性格はしていない。
泣いても状況は良くならないのだから、悲しむくらいならいっそのこと爆発させるタイプだ。
滅ぼしたって構わないだろう。
「悪魔か君は......」
若干頬を引き攣らせながら放たれたその言葉に、私はにっこりと晴れやかな笑みを返した。
「悪魔? いいえ────鬼嫁です」
「……」
そして魔王は本日何回目かの盛大なため息をついた。
魔王城に嫁いで三日。
城の一角に自室を与えられた私は、割と自由な日々を送っていた。
自分の行きたい場所に自由に入ってもいいし、城内の図書室の本だって好きに読めばいい。
書類上の夫となった魔王は朝昼晩必ず食事を共にしてくれる。
そしてその食事がなんといっても素晴らしく美味しいのだ。
量は王侯貴族が無駄に出すような大容量では無く、一般家庭の一人分と同じ程度の量。
決して贅沢品ではなく、食材も一般的なものだ。
王侯貴族から見れば、質素、という言葉が適しているのだろう。
だけど王侯貴族の食べるものよりも遥かに美味しいのだ。
さぞ名のあるシェフでも雇っているのだろうとも思ったけれど、厨房はいつも空。
それどころか私は未だに、この城で私と魔王以外の人を見たことがない。
故に──。
「暇だわ。ふあぁぁ……」
暇すぎてあくびが出てしまった。
常に日が当たらない魔界にいると体内時計が狂うのか、妙に眠くなってくる。
ついには私はその眠気に抗うことができず、深い夢の中へと落ちていてしまった。
***
──白い……霧……?
気づけば私は、深い霧の中に佇んでいた。
ここ、どこ?
さっきまで城の部屋にいたはずなのに。
部屋、ではないわよね?
辺りを見渡してみても何も見えない。
アンティークな机も、椅子も、クローゼットも、誰が用意したのか知りたくない少女趣味な天蓋付きベッドも。
これはどうしたことか……。
また別の世界にでも飛ばされたんだろうかと不安に思っていると──。
「いらっしゃい、可愛いお嬢さん」
透き通るような美しい声が響いて、そこには真っ白いドレスを着た金髪碧眼のお人形のような女性がこちらに笑みを向けて立っていた。
「あ、あの、お邪魔してます!!」
ここに来て初めて魔王以外の人に会えたという興奮から、妙に鼻息荒くなってしまったが仕方ない。
だって本当に久しぶりなんだもの、魔王以外の人間。
「ふふ、面白い子ね。異界の乙女がこんなに可愛らしい子だとは思わなかったわ。あぁそれとも、“中和の乙女”と呼んだ方がいいのかしら?」
「中和の──乙女?」
そんな呼び名は初めて聞いた。
私が女性から飛び出した言葉を反復させると、彼女はふんわりと微笑んで頷いた。
「あなたには、相対するものを中和させる力がある。善と悪。正と負。神と魔……。なんでも中和してしまうの、その力は」
え、すごっ。
まったく実感はないけれど。
「そうねぇ……目が覚めたら、城側とは反対の門へお行きなさい。そこにある魔法石に触れるの。そうすれば、事は動き始めるわ。あぁ、くれぐれも、ゼノンディウスには秘密で、ね?」
「ゼノン……あぁ、魔王のこと、ですか。でもなんで? そんなことしたら……」
「良いのよ。事を動かすには、きっかけを作らなきゃ、何も動かないわ」
事を、動かす……。
そうすれば何かが変わるのだろうか?
そうすれば、元の世界に帰ったりできるのだろうか?
あの子達の元に。
弟達の元に、帰ることができる?
こちらの世界に来てから数ヶ月。
あの子達を思い出さなかった事はない。
私がいなくなってしまったら、もう他に身寄りのないあの子達はきっと施設に入れられるはず。
衣食住の補償は、おそらく心配ない。
心配ない、のだけれど……。
やっぱり心配してしまうのが姉というものだ。
もし事というものが動いて元の世界に帰ることができるというのならば、試してみない手はない。
「わかりました……!! 私、行ってきます!!」
強奪された日常を取り戻すために。
「えぇ。行ってらっしゃい。いつでも見守ってるわ、あなた達を──」
美女の微笑みに私も笑みを返すと、刹那、再び霧が立ち込め、美女の身体を覆って消し去ってしまった。
朝だというのに相変わらずこの魔界に日は当たらない。
門一つ隔てた同じ世界のことなのに、それをくぐるだけで一歩進めば魔界となる不思議。
私は一人、薄暗く鬱蒼とした森の中を歩き続ける。
「それにしても静かね」
ラザミリ城で聞いた話では、魔界の森の中には魔物がウヨウヨしていて、足を踏み入れたら最後、たちまち奴らに囲まれる。だから王家の専用の馬車を使わなければ危険なんだ、って教わったのだけれど……。
森の中には魔王城内と同じく、何もいない。
気配すら感じない。
「魔界って過疎化してるの?」
私の呟きが、しんと静まり返った森の中に響く。
にしても、鳥の鳴き声ひとつしないのは、何だか不気味だ。
あの美人さんはこっちに行けって言ってたけれど、一体何があるんだろう?
早く行って早く帰ろう。
木々の間の一本道を進んで行くと、ようやく見えてきたのはぴっしりと閉じられた黒い門。
これ、城側の出入り口のものと同じ……。
まるでここから出ることを禁ずるとでも言わんばかりの、大きく重厚な門が威圧感を放つ。
「魔法石とか中和がどうのとか言ってたけど……これのこと?」
私が確かめるように、そっと門の中央にくっついている黒い宝石に触れた、瞬間──。
「っ!?」
宝石がが淡く白い光を放ち始め、そして──「消えた……」
まるで景色に溶けるようにして、忽然と消えてしまった門に、私は思わずその場に尻餅をついて呆然とその跡を見つめた。
さっきまであった……のよね?
え、待って、何で?
「アァー!!」
「っ!?」
突然何かくぐもったような大きな鳴き声が森に響き渡り、私は肩をびくりと跳ね上がらせて辺りを見渡す。
「か……帰らなきゃ……!!」
これ以上ここにいるのは──怖い。
私は震える足を無理やり立たせると、元来た道を全速力で駆けた。
「はぁっはぁっ──っはぁっ、はっ、キャァッ!!」
ズサッ!!
恐怖と不安で一心不乱に走り続けた私は、道の真ん中に飛び出た握り拳ほどの石につまづいて、勢いよく滑りこけてしまった。
「ったぁ~……」
地面に擦り付けた両膝から流れる赤い血。
暑く、ジンジン痛む。
暗雲立ち込める空からはぽつりぽつりと雫が落ち始めた。
「やばっ、雨!?」
痛む足を引きずりながらとりあえず近くの木の下へと移動すると私はその木の根元へと腰を下ろした。
ついてない。
本当についてない。ここのところの私。
私は泣きそうになるのを堪えるように、威力を増した雨を生み出す空をじっと見上げるのだった。
おかしい。
彼女が、いない。
3日前に不本意ながら私の妻になった女性──千奈。
クズだクズだと思っていた我が義弟だが、最低のクズだったことを再確認した日だった。
封制印を奴がもっているからには、私には抵抗もできない。
幸い、千奈は悪い人間ではなく、何より一緒にいて不快ではなかった。
あんなことがあっても挫けることなく、逆に「国を滅ぼしたい」という思考を持つ強さ。
前向きで、コロコロと表情が変わって、話していて楽だ。
そんな彼女の姿が見えない。
朝食は共に食べた。
変わった様子もなかったはずだ。
昼食に現れない彼女を屋敷中探し回ったが、どこにもいない。
魔界は封印されていて、こちら側からは出られないはず。
ということは、森か?
──この城は深い森に囲まれている。
そしてその森は、ぐるりと高い壁で囲まれ、その外は人間界となる。
壁の外に出るには黒い門を通らねばならない。
門は二つ。
城側と、反対側は崖壁と、崖の上は小さな町に続いていたはずだ。
魔界の者たちには彼女の前に姿を現さないよう伝えているから、怖がらせることはないだろうが……。
「アスト」
「──はい」
私の呼びかけに、私の前に黒い霧に紛れて黒い大鳥が現れた。
「空から彼女を探してもらえるか?」
「お任せを」
承知の言葉だけ残してから、アストは私の前から再び黒い霧に溶けるようにして消えた。
──アストが戻ってきたのは、それからすぐのことだった。
「ここから町側の門へ向かう途中の大木の下で、千奈様を発見いたしました。足に怪我をされているようで、心細そうに蹲っておいでです」
「怪我だと!?」
心細そうに……。
あの前向きで 強気な女性が、か?
想像ができない。
だが怪我をしているのならば、動くことは難しいのだろう。
早く行ってやらねば……。
私は黒い外套を羽織ると、窓を開け放った。
朝だというのにこの魔界は常に暗い。
そして今は雨が降りしきっていて、森の中はさぞ冷たく暗い状態になっていることだろう。
ここに追放されてしばらく、私は一人でこの城にいるのが怖くて仕方がなかった。
だけど一緒に追放された母が、ただ傍にいてくれたから──。
だから私は、生きてくることができた。
一人、暗闇にいる恐怖は、私が一番よく知っている。
光が灯った時の安心も。
「……行って来る」
そう言って窓の桟に足をかけたその時。
「もう一つご報告を」
アストが私を呼び止めた。
「何だ。手短にしろ」
「村側の門の封印が解かれている模様です」
「!!」
村側の、門の封印が……?
外に出ることを禁じられ、外から封印の術をかけられ、魔界に閉じ込められた私と母。
何度も、魔界の魔物たちに協力してもらって出ようと試みたが、封印は解くことができなかったが……。
今になって一体なぜ?
まさか、あの嫁が何かしたのか?
いや、まさか。
そんな力、彼女には……。
「……わかった。ご苦労だった。調理場に、温かい飲み物を用意するように伝えてくれ。あと、彼女の寝室に毛布を」
「はっ」
アストの返事を聞いてから、私は一人窓の外、暗闇へと飛び立った──。
「どうしよう……。暗くて、寒くて……ぶ、不気味……」
一人でこんなところにいることなんて、今までなかった。
両親が死んだ時、私には祖母と二人の幼い弟がいた。
祖母が死んだ時も、両親の時よりも少しだけ成長した弟たちがいた。
私は、一人じゃなかった。
灯りをつけて、二人が不安にならないように、明るく強く、しっかりと自分を保ってきたのに。
暗闇が──こんなに怖いだなんて。
こんなに、心細いだなんて。
知らなかった。
いや、知らないふりを、気づかないふりをしてきたんだ。
気づいてしまったら……私まで沈んでしまったら……、あの子たちを守ることができないと、無意識に心に盾を作っていた。
あの子たちを守って、親の代わりに育てること。
その目標が、バカ陛下の嫁召喚なんかで失われたんだ。
この世界、いや、人間界の奴らのせいで……。
私がいなくなって、弟たちは大丈夫なんだろうか?
どこか施設に入っているんだろうか?
ちゃんと、笑えているだろうか?
私は────。
「千歳……。千都……」
大丈夫じゃないのは、多分、私だ。
「会いたいよ……。……お父さん、お母さん、おばあちゃん──ゼノン」
自然と飛び出した魔王の名に気づき顔を上げた、その時だった。
「千奈!!」
「!!」
声が。
深く低い、焦ったような声が、私の耳に届いた。
と同時に、私の目の前に降り立った黒い影。
「ま……おう……?」
突然舞い降りた黒髪の美青年は私には見覚えのない顔をしていたけれど、それでも何となく、わかった。
いつもフードでほとんどの顔が隠れていたけれど、彼の特徴と一致したから。
真っ黒い服。
赤い双眸。
そして何より、その深く心に響く低音ボイス。
間違いない。
この美青年は──魔王だ。
「ど……して……」
何でここに?
どうしてここがわかったの?
色々聞きたいのに声が震えて言葉が出てこない。
「っ……怪我が……。少し、我慢していろ」
「え? っ、きゃぁっ!?」
言うや否や、魔王は私の背中に右手を回し、左手を私のひざ下へとくぐらせ、一気に持ち上げた。
所詮お姫様抱っこというやつだ。
まさか人生でこんなことをされる日が来るだなんて、夢にも思っていなかった。
「戻るぞ」
「へ? え、ちょ、ひやぁぁぁあっ!?」
どんどん地面から遠くなっていく視界。
空……飛んでる……!!
「急ぐぞ。舌を噛まないよう、口を閉じていろ」
「は? っ!?」
魔王の飛ぶ速度が一気に加速した。
息もできなくなるくらいに速く、視界が次から次へと変わって忙しくなる。
私は飛んでいる間、自分の目と呼吸を守るため、魔王の胸元に顔をうずめるしかなかった。
***
シュンッ──と風を切って暗雲立ち込める雨の空を飛び続け、開け放たれた窓から侵入したその先は、魔王城の私の部屋だった。
「ついたぞ」
そう言って私をベッドの淵へと優しく降ろした魔王は、その場にしゃがんで私の右足を手にした。
「!? ちょ、な、何して──っ!?」
「怪我……痛むか?」
「ぁ……」
私の右足を手に取ったまま、視線は左足にも向けられる。
じんじんと痛む両膝を交互に見てから、眉を顰める魔王。
もしかして、心配してくれてる?
熱心に私の傷を観察する魔王に、私は小さくうなずいた。
「ふむ……仕方ない、か……。──フラン!!」
「──お呼びでしょうか」
「!?」
魔王が「フラン」と人の名を呼ぶと、そのすぐ背後で黒い霧に包まれて現れたのは、白髪で人の良さそうな笑みを浮かべた初老の女性。
それだけならばまだ、何か手品でもして現れたのだろうと思い込むこともできたかもしれない。……頑張れば。
だけど彼女は、明らかに人とは違っていたのだ。
だって──彼女の肌は、全て余すことなく緑色で、耳もツンと尖っているのだから……。
「すまないが、彼女の足を見てやってくれ」
「かしこまりました」
女性は綺麗に頭を下げると、私の前まで進み出て、怪我をしている私の両膝に触れた。
「あらあら、結構深く傷ついてしまわれたのですわね?」
「え、えぇ……」
「よく耐えられましたわね」
女性はにっこりと笑って、私の両膝にその緑の両手をかざした。
刹那、彼女の手のひらから淡く白い光が溢れ、私の両膝へと吸い込まれていくと、みるみるうちに流れていた血が止まった。
傷はあるけど、でも、痛みがない……。
「うそ……え……えぇぇぇえええ!? 何!? どういうこと!? 傷はあるのに痛くない!!」
「ふふふ。良かったですわ。私の力では痛みを麻痺させ感じなくさせたり止血をすることが限界で申し訳ありませんが……」
そう言いながら女性はエプロンのポケットから次々と包帯やカット綿、消毒液にピンセットなどを取り出すと、私の足をきれいに処置し、最後に上半身がすっぽり入りそうな大きめのふわふわのタオルを、私の頭からかぶせた。
「彼女──フランはホブゴブリンでな。この城で侍女をしている」
「侍女!?」
使用人、居たの!?
今まで見たこともないのに……。
「ホブゴブリンって……それに侍女って……。でも、今まで一体どこに……?」
私の問いかけに、フランと呼ばれていた女性が目尻の皺を濃くして優しく笑った。
「人間がここに来た際には、私たちは姿を見えなくしております。彼らを驚かせないように、そして敵意がないことを示すために。それに魔王様から、人間の、しかも魔法のない世界から強制的に召喚されたお嬢様がお嫁様になったと聞いて、私たちは決めたのです。お嬢様がこの世界に慣れるまでは、姿を現さず、陰からのサポートに徹しようと」
それじゃぁ、ずっと屋敷の人達の姿が見えなかったのは──いないんじゃなくて……私を怖がらせないため?
厨房に人がいないのに美味しい料理が出てくるのも。
朝起きてそのままにしていても、夜にはベッドが綺麗に整えられて、ぽかぽかしているのも。
服の洗濯だって……。
全部、姿を消して、私に気づかれないようにしていたっていうの?
心にじんわりとした温かいものがこみあげてくる。
「……私……突然に無理矢理召喚されて、幼い弟たちと離れ離れになって……。でも、人間界では私を気遣ってくれる人なんていなかった」
ひとつ、また一つと、言葉が沸き上がってくる。
「異世界人と王が結婚すれば国が反映するなんてお告げのせいで婚約させられて……。その婚約相手は国庫から勝手にお金を出して、毎日けばけばしい恋人に貢ぎまくるし、ダンスも恋人と踊って私はほったらかし。自分の居場所のない世界でこれから生きていかないといけないことに、ずっと絶望してた」
憤って、絶望して、諦めて……。
だけど──。
「私……魔王に嫁いでよかった」
「っ……」
魔王の赤い瞳を見上げて笑った私に、なぜか魔王が言葉を詰まらせた。
「フランさん、お気遣い、ありがとうございました。あの、もう私、大丈夫ですから……だから、そのままでいてください。これからも、よろしくおねがいします」
「お嬢様……はい。こちらこそ、よろしくおねがいいたします」
フランさんと微笑み合うと、彼女は「それでは私はお風呂の準備をさせていただきますわね」と頭を下げてから、また黒い霧に消えた。
……普通にドアから出入りしてもらうように今度言っておこう。
私と魔王だけになった部屋で、魔王はじっとただ私を見つめたまま固まっている。
「あの、魔王……ありがとうございます。助けに来てくれて」
「ゼノン」
「はい?」
「ゼノンと呼べ」
そう小さな声で言われて、先程のことを思い出す。
雨に濡れて心細い中、その名が自分の口から漏れ出たのは無意識だった。
あの時は特に何も思っていなかったけれど、こうして思い返してみるとなんだかとても恥ずかしくなってくる。
「わ……わかりました。ぜ……ゼノン」
勇気を振り絞って名前を呼んでみれば、目の前で無表情のまま私を見つめていた魔王の顔が僅かに赤らんで、それから満足げにうなずいた。
「それでいい。で、お前は何であの場所に? しかも門の封印が解けていたようだが、何かしたのか?」
「ぁ……えっと……」
どうしよう?
夢の中で女性に行ってみろと言われたので行ってみました?
門に触ったらなんか変わっちゃいました?
……そんな突拍子もない話、信じてくれるかしら?
頭のおかしい奴だと、魔界からも追放されたら……?
いや──。
彼は、ゼノンはそんなことをする人じゃない。
彼のことを詳しく知っているわけじゃないけれど、そんな非情な人ではないことはわかる。
なら────「実は……」
***
私はゼノンにすべてを話した。
夢の中に見知らぬ綺麗な女性が現れて、私を中和の乙女だと教えてくれたこと。
目が覚めたら城の反対側の門の魔法石に触れるように指示したこと。
ゼノンに秘密で行くようにと言われたこと。
門の宝石に触れたら、門が消えてしまったこと。
怖くなって元の道を走って帰る途中こけて、さらに雨まで降ってきて雨宿りしていた事。
話している間、魔王は何も言わず、ただ難しい顔をしたまま私の隣に座り、じっと私の話に耳を傾けた。
そして聞き終わると、腕を組んだまま深いため息をついた。
「とりあえず、その女性は、外見的特徴からしておそらく私の母の思念体か何かだろう」
「は、母!?」
確かゼノンのお母さんは、ゼノンと一緒に追放されたって聞いた……。
それが夢に出てきたってことは、お母さんは……。
「私の話もせねばならんな。……私の力がわかってすぐ私は魔界に追放され、私を産んだ母も魔族なのではないかと疑いをかけられ、共に追放された。暗い魔界で、怖くて震えていた私を、母は懸命に守ろうとした。幸いにも魔物たちは皆心優しく、私と母を歓迎し、魔界での世話もしてくれたし、いろいろと教えてくれ、二人でここで生きていける希望を持った。その時だった。母が父から、死の呪いをかけられていたことを知ったのは……」
「死の呪い!?」
「あぁ。父は私を、母と魔族の子どもであると、母が不貞を犯したのだと考えたんだ。そして母に死の呪いをかけた。1年後に死ぬという呪いを、な。母はどんどん弱り、追放から一年後に死んだ。そして呪いの代償として、術者である父──先代の王もそれから5年後に死んだ」
「!!」
そんな……ひどい……!!
自分の奥さんを疑って憎んで、信じることなく殺すだなんて……。
「当時まだ幼かった弟の代わりに数年は側妃だった義母が政治ごとを代わってやっていたようだが……国王に即位した途端、バカげたお告げを信じて召喚の儀を行い、自分勝手に無責任にも君まで追放するとは……。すまなかったな」
申し訳なさそうに頭を下げた魔王に、私は慌てて首を横に振った。
「ゼ、ゼノンが謝る事じゃないです!!」
悪いのはあのポンコツ色ボケ陛下だ。
どうせ今もまだ国費を使って恋人に貢いでいるのだろう。
いつか痛い目に会えばいい。うん。
「ふっ、そうか」
かすかに笑ってゼノンが続ける。
「私が母の呪いのことを知ったのは、母が死んでから、母の日記を見て知った。もしももっと早く知って、誰かに相談していたら、母の死は防げたのかもしれないのに」
「ゼノン……」
悔しかったことだろう。
心細かったことだろう。
光の当たらない世界で、人間はただ一人になってしまったのだから。
するとゼノンは、私の目をまっすぐに見つめ、真剣な表情で言った。
「だから千奈。君は何かあれば、すぐに私に言ってほしい。どんな些細なことでも良い。言ってくれたなら、一緒に悩むことができる。答えを導き出すことができる。一人じゃない。私がいることを忘れないでほしい」
それはたった一人で魔族の中で生きてきたゼノンの、切実な願い──心からの叫びのように思えた。
「書類上とはいえ、私たちは……夫婦になったのだから」
「っ……」
まるで、家族なのだと言われているようで、目に熱いものがこみあげてきて、それを誤魔化すかのように、私は魔王の胸に思い切って飛び込んだ。
「なっ、おい!?」
慌てる魔王をよそに、私はぐりぐりとその硬い胸板に顔を押し付ける。
そして小さな声でこう言った。
「鬼嫁ですが、これからよろしくお願いします」
「っ……あぁ。こちらこそ。魔王だが、これからよろしく頼む」
そして私の頭上に、温かい魔王の手が触れた──。
魔王と鬼嫁。
最強の夫婦が誕生した日だった。