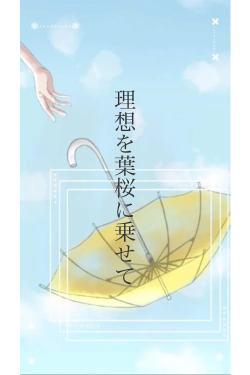槙くんと出会してから一週間がたった。
今日は会社の同期と飲み会に行く約束をしていて、気持ちがすっかり上向いていた。
散々飲んで飲んで飲みまくることは会社で起こった嫌なことを忘れられる大切なものである。
だからそんな日にまさかまたあの人に出会すなんて誰しも思わなかったであろう。
「かんぱーい!」
飲み会が始まるこの合図とともにみんなグイグイビールを飲み出した。
私も日頃のストレスを吹き飛ばすかのようにものすごい勢いでビールを飲む。
「おー、桜野さんいい飲みっぷりだねぇ。」
ビールを持ちながらもう片方の空いている手でおつまみを掴んで食べようとしているとおんなじ部署に所属する小鳥遊さんが声をかけてきた。
「そりゃぁ、日頃の疲れをこうしてプッハーッと吐き出すのも悪いものではないですからねぇ。」
なんて、何疲れ果てた老人みたいなことを言いているのだろう。
自分自身に恥ずかしく思いながらもやっぱりお酒好きにはこの言葉しか出てこないのだ。
「そっかぁ、いいね、あんまり酔いすぎないように気をつけなよー。」
小鳥遊さんはそんな私に呆れたのか知らないけどそのまま席を立ちスタスタとどこかへ行ってしまった。
お酒好きも少しは制限しないといけないのかなぁ。
自分の言動に一人で静かに反省していたその時だった。
ガララララと店の扉が開き誰かが中に入って来たことを感じ取った。
無意識に扉の方を見てみる。
「あ……。」
その声は案外大きなものだったみたいで店内に入って来たその人も私の存在に気づく。
二人して声を上げた。
「槙…!」「桜野!」と。
「お前、なんでまたこんなとこにいるんだよ。」
それはこっちのセリフだと内心毒づきつつも槙くんにまたもや出会したことに焦ってはいた。
「…別に、わたしは同期の飲み会に参加してただけ。」
平静を装いつつも槙くんを見つめると意外にも槙くんは顔を赤らめてそっぽを向いた。
そんなまたもや起こった最悪な再会にはぁとため息をつく。
と、そんな私たちの様子を見ていた小鳥遊さんが「なんだ?彼氏か?」と茶化してきた。
「そんなんじゃないですよー」なんて適当にあしらいつつ少しだけ小鳥遊さんを睨みつけた。
「おい、もうお前抜けていいぞ、彼氏と一緒にいたいだろう?二人で話しておいでよ。」
なんて小鳥遊さんは自分がとてもいいことをしているかのようなそんな迷惑にしかならない厚意を押し付けてくる。
そんな私の嫌な視線には気づくことすらせずまだ槙くんが私の彼氏だと勘違いしている小鳥遊さんを見てつい怒りが込み上げてくる。
「だから彼氏じゃないって言ってるで…」
しかしその言葉はある人によって遮られた。
「はい。そうです。桜野茜は俺の彼氏です。申し訳ないのですが少しだけ茜をお借りすることって可能でしょうかね?」
…は?
一瞬フリーズしかけた頭をもう一度たてなおすには数十秒間かかった。
ってか今槙くん私のこと彼女って言わなかった?というか今の言葉って本当に槙くんが言ったの?
そこにすら信じ難い、それほど私は驚いた。
頭の中が混乱している中、小鳥遊さんは「どーぞー。いくらでも話してくださいな。」なんて勝手に承諾しちゃってるし、本当になんなの?
何にも言えないまま小鳥遊さんと槙くんの話しはあっという間に終わり槙くんは私の方によって来てこう言った。
「よし、茜、一回出るぞ。」
いや、よしじゃないし…。
てか槙くん今更私に何の用があるのだか、それですら謎のまま槙くんに手を引かれるがまま外に連れ出された。
槙くんに手を引かれ連れ出されてから早30分、まだ一言も会話を交えずにいた私たちに少しながらも苛立ちを感じていた。
一体槙くんはどこへ向かっているのだ?
どんどんどんどん道に迷うことすらせずに目的地に向かって黙々と進んでいく槙くんに不信感が芽生える。
内心焦りを感じていると槙くんは急にピタっと足を止めた。
そしてくるりと私と向かい合うような姿勢をとる。
槙くん…?どうしたんだろう。
向かい合ってからも全く話し出さない槙くんを見て不安になってくる。
すると槙くんは凄まじい勢いで土下座をしきたのだった。
「桜野!中学生のとき俺は桜野が好きだった。だけど俺の言葉で桜野を傷つけてしまった。本当にすまなかった。」
槙くんはそう大声で怒鳴るように叫んでいた。
そして
「今も好きだ!今も桜野が好きで好きで、、、。久しぶりに会った時もう思いが爆発してしまって何も話せなかった。」
思いがけない衝撃の事実が発覚して声も出ずにいた私に槙くんは申し訳なさそうに眉尻を下げている。
「知ってたの?私が槙くんの元へ行かなかったことの理由。」
「うん…」
「じゃあなんでそんなこと言ったの?なんでカラダ目的とか言ったの?」
震える声で尋ねた。
「好きだったから。友達に茶化されるのが恥ずかしかったから。」
びっくりした。まさか槙くんがそんなふうに思っててくれていたなんて…。
今日は会社の同期と飲み会に行く約束をしていて、気持ちがすっかり上向いていた。
散々飲んで飲んで飲みまくることは会社で起こった嫌なことを忘れられる大切なものである。
だからそんな日にまさかまたあの人に出会すなんて誰しも思わなかったであろう。
「かんぱーい!」
飲み会が始まるこの合図とともにみんなグイグイビールを飲み出した。
私も日頃のストレスを吹き飛ばすかのようにものすごい勢いでビールを飲む。
「おー、桜野さんいい飲みっぷりだねぇ。」
ビールを持ちながらもう片方の空いている手でおつまみを掴んで食べようとしているとおんなじ部署に所属する小鳥遊さんが声をかけてきた。
「そりゃぁ、日頃の疲れをこうしてプッハーッと吐き出すのも悪いものではないですからねぇ。」
なんて、何疲れ果てた老人みたいなことを言いているのだろう。
自分自身に恥ずかしく思いながらもやっぱりお酒好きにはこの言葉しか出てこないのだ。
「そっかぁ、いいね、あんまり酔いすぎないように気をつけなよー。」
小鳥遊さんはそんな私に呆れたのか知らないけどそのまま席を立ちスタスタとどこかへ行ってしまった。
お酒好きも少しは制限しないといけないのかなぁ。
自分の言動に一人で静かに反省していたその時だった。
ガララララと店の扉が開き誰かが中に入って来たことを感じ取った。
無意識に扉の方を見てみる。
「あ……。」
その声は案外大きなものだったみたいで店内に入って来たその人も私の存在に気づく。
二人して声を上げた。
「槙…!」「桜野!」と。
「お前、なんでまたこんなとこにいるんだよ。」
それはこっちのセリフだと内心毒づきつつも槙くんにまたもや出会したことに焦ってはいた。
「…別に、わたしは同期の飲み会に参加してただけ。」
平静を装いつつも槙くんを見つめると意外にも槙くんは顔を赤らめてそっぽを向いた。
そんなまたもや起こった最悪な再会にはぁとため息をつく。
と、そんな私たちの様子を見ていた小鳥遊さんが「なんだ?彼氏か?」と茶化してきた。
「そんなんじゃないですよー」なんて適当にあしらいつつ少しだけ小鳥遊さんを睨みつけた。
「おい、もうお前抜けていいぞ、彼氏と一緒にいたいだろう?二人で話しておいでよ。」
なんて小鳥遊さんは自分がとてもいいことをしているかのようなそんな迷惑にしかならない厚意を押し付けてくる。
そんな私の嫌な視線には気づくことすらせずまだ槙くんが私の彼氏だと勘違いしている小鳥遊さんを見てつい怒りが込み上げてくる。
「だから彼氏じゃないって言ってるで…」
しかしその言葉はある人によって遮られた。
「はい。そうです。桜野茜は俺の彼氏です。申し訳ないのですが少しだけ茜をお借りすることって可能でしょうかね?」
…は?
一瞬フリーズしかけた頭をもう一度たてなおすには数十秒間かかった。
ってか今槙くん私のこと彼女って言わなかった?というか今の言葉って本当に槙くんが言ったの?
そこにすら信じ難い、それほど私は驚いた。
頭の中が混乱している中、小鳥遊さんは「どーぞー。いくらでも話してくださいな。」なんて勝手に承諾しちゃってるし、本当になんなの?
何にも言えないまま小鳥遊さんと槙くんの話しはあっという間に終わり槙くんは私の方によって来てこう言った。
「よし、茜、一回出るぞ。」
いや、よしじゃないし…。
てか槙くん今更私に何の用があるのだか、それですら謎のまま槙くんに手を引かれるがまま外に連れ出された。
槙くんに手を引かれ連れ出されてから早30分、まだ一言も会話を交えずにいた私たちに少しながらも苛立ちを感じていた。
一体槙くんはどこへ向かっているのだ?
どんどんどんどん道に迷うことすらせずに目的地に向かって黙々と進んでいく槙くんに不信感が芽生える。
内心焦りを感じていると槙くんは急にピタっと足を止めた。
そしてくるりと私と向かい合うような姿勢をとる。
槙くん…?どうしたんだろう。
向かい合ってからも全く話し出さない槙くんを見て不安になってくる。
すると槙くんは凄まじい勢いで土下座をしきたのだった。
「桜野!中学生のとき俺は桜野が好きだった。だけど俺の言葉で桜野を傷つけてしまった。本当にすまなかった。」
槙くんはそう大声で怒鳴るように叫んでいた。
そして
「今も好きだ!今も桜野が好きで好きで、、、。久しぶりに会った時もう思いが爆発してしまって何も話せなかった。」
思いがけない衝撃の事実が発覚して声も出ずにいた私に槙くんは申し訳なさそうに眉尻を下げている。
「知ってたの?私が槙くんの元へ行かなかったことの理由。」
「うん…」
「じゃあなんでそんなこと言ったの?なんでカラダ目的とか言ったの?」
震える声で尋ねた。
「好きだったから。友達に茶化されるのが恥ずかしかったから。」
びっくりした。まさか槙くんがそんなふうに思っててくれていたなんて…。