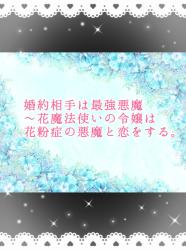数日後の夕暮れ時。
俺は自分のベットに腰掛けながら「俺、彼女出来るかも」と呟いた。遥斗の気持ちを確かめるために――。
遥斗はどんな反応をするんだろう。ヤキモチ妬いたりしてくれるかな?って考えると、期待する気持ちもあるし、緊張もする。
もちろん彼女が出来るかもなんて、嘘に決まっている。
遥斗にしか、興味がなかったから。
「えっ?」
白いテーブルのところで小説を読んでいた遥斗は、ぱっと勢いよく顔をあげ、こっちをみた。遥斗の表情が悲しそうに見える。悲しそうな表情に見えたのは、そうだったらいいのになと都合よく解釈をしているからそんなふうに、悲しそうに見えたのかもしれない、と一瞬考えたけれど――。
「よかったね! 莉久くんは頼りになるし、カッコイイもんね、彼女ぐらいすぐに出来るよね。莉久くんの彼女になった人はきっと、幸せになれるね」
明るい声で遥斗は言った。
欲しかった嫉妬の言葉はない……。
遥斗は読んでいる途中の小説を閉じた。いつもは水色の栞を挟んで閉じるのに、その栞はテーブルの端に置いたまま。
「あっ、ラーメン切らしてるんだった。たまにはコンビニ限定のやつ食べたいな。買ってくる」
外は雪が降っていて気温も低く、薄暗い。なのにコートを着ないで、薄い長袖一枚の部屋着のまま、そそくさと出ていった。普段なら、コンビニや寮にある購買部に用事がある時は、何か買ってきて欲しいものがあるか聞いてきたりする。まして親しくなってからはどっちかがコンビニに行く話をすると、一緒にコンビニへ行く流れになっていたりしたのに。
遥斗が使っているベットの隣にある棚には、いつものように実家から送られてきたカップラーメンが、いくつも並んでいる。
「ラーメンあるし……っていうか、外、寒いだろ……」
しかもコンビニまでの距離は五分以上ある。
俺はコートを急いで着て、遥斗のコートを持つと走って追いかけた。
動揺を隠そうとしていたっぽいけれど、全く隠せていない遥斗。最後の言葉は震えていた。
どうして遥斗の気持ちを知りたいからって、こんな馬鹿なことしたんだろう。遥斗に嫌な思いをさせてしまった。言葉では本音を教えてくれないけれど、いつもと違う不自然な行動で遥斗の気持ちが分かった気がする。
だけど俺は、直接遥斗の口から本音を知りたい。教えて欲しい――。
俺は自分のベットに腰掛けながら「俺、彼女出来るかも」と呟いた。遥斗の気持ちを確かめるために――。
遥斗はどんな反応をするんだろう。ヤキモチ妬いたりしてくれるかな?って考えると、期待する気持ちもあるし、緊張もする。
もちろん彼女が出来るかもなんて、嘘に決まっている。
遥斗にしか、興味がなかったから。
「えっ?」
白いテーブルのところで小説を読んでいた遥斗は、ぱっと勢いよく顔をあげ、こっちをみた。遥斗の表情が悲しそうに見える。悲しそうな表情に見えたのは、そうだったらいいのになと都合よく解釈をしているからそんなふうに、悲しそうに見えたのかもしれない、と一瞬考えたけれど――。
「よかったね! 莉久くんは頼りになるし、カッコイイもんね、彼女ぐらいすぐに出来るよね。莉久くんの彼女になった人はきっと、幸せになれるね」
明るい声で遥斗は言った。
欲しかった嫉妬の言葉はない……。
遥斗は読んでいる途中の小説を閉じた。いつもは水色の栞を挟んで閉じるのに、その栞はテーブルの端に置いたまま。
「あっ、ラーメン切らしてるんだった。たまにはコンビニ限定のやつ食べたいな。買ってくる」
外は雪が降っていて気温も低く、薄暗い。なのにコートを着ないで、薄い長袖一枚の部屋着のまま、そそくさと出ていった。普段なら、コンビニや寮にある購買部に用事がある時は、何か買ってきて欲しいものがあるか聞いてきたりする。まして親しくなってからはどっちかがコンビニに行く話をすると、一緒にコンビニへ行く流れになっていたりしたのに。
遥斗が使っているベットの隣にある棚には、いつものように実家から送られてきたカップラーメンが、いくつも並んでいる。
「ラーメンあるし……っていうか、外、寒いだろ……」
しかもコンビニまでの距離は五分以上ある。
俺はコートを急いで着て、遥斗のコートを持つと走って追いかけた。
動揺を隠そうとしていたっぽいけれど、全く隠せていない遥斗。最後の言葉は震えていた。
どうして遥斗の気持ちを知りたいからって、こんな馬鹿なことしたんだろう。遥斗に嫌な思いをさせてしまった。言葉では本音を教えてくれないけれど、いつもと違う不自然な行動で遥斗の気持ちが分かった気がする。
だけど俺は、直接遥斗の口から本音を知りたい。教えて欲しい――。