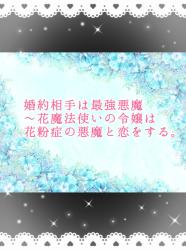「僕たち、出会ってから、結構経ったよね」
「そうだな、一年と半年以上か……」
「この部屋の座布団を一緒に選んだり、ラーメン食べたり色々したよね――」
もうすぐ冬休みになる時期。今、部屋の掃除をふたりでしている。そして出会った時からの思い出話をしていた。
「実は莉久くんと初めて出会った時ね……、やっぱり言うのやめた」
「何? すごく気になる」
俺は床磨きをしていた手を止め、窓を拭いている遥斗を見た。遥斗も手を止め、こっちを見る。
「怒らないで聞いてね?」
「遥斗に怒ったことないし、怒らないし……」
「莉久くんのこと、すごく怖い人って思ってたんだ」
そう思われていたのも納得できる。当時は気を遣う必要がないと思っていて、本当に無愛想だったから。
「あの時は、怖がらせてごめんな」
「いや、全然謝ることじゃないよ!」
「……遥斗は、その時から可愛かったよな」
「えっ? 僕、そんなふうに思われてたの?」
遥斗の目がぱっと大きく開いた。
「うん、思ってた」
「……そうだったんだ。僕はもしかしたら嫌われているのかな?って、その時に思ってた」
「いや、そもそも初対面で嫌いとか、意味わからないし」
「嫌われていなくて、よかった!」
窓の上の方を拭くために遥斗は、微笑みながら白いテーブルを少しずらし、そこに椅子を置いた。窓の上の方を拭こうと更に背伸びをする。するとふらふらして落ちそうになった。
「遥斗、大丈夫か?」
「……ううん、だいじょばない。ちょっと怖いかな」
「じゃあ、俺そこやるわ」
「ありがとう」
最近、遥斗が本音で話をしてくれている感じがして、嬉しい――。
俺は両手を差し出すと、遥斗は俺の両手を握りながら、ゆっくりと椅子から降りた。そして手を握ったまま「でもね、莉久くんと関わっていくうちに、莉久くんはすごく優しくて、怖くないって知ったよ!」と微笑んだ。
「優しいなんて言われたことがなかったから、なんか照れるな」
多分自分が優しくなれるのは、遥斗の前でだけだ。
いつも怖そうとか、そんなことしか言われないから、なんだろ、全身がムズムズしてくる。
「莉久くん、優しい!」
遥斗は、くふふと声を出して笑った。
最近は自然な笑顔も見せてくれるようになった。
その笑顔をずっと見ていたいし、本音ももっとずっと聞かせて欲しい。でももうすぐ冬休みだ。
「そうだな、一年と半年以上か……」
「この部屋の座布団を一緒に選んだり、ラーメン食べたり色々したよね――」
もうすぐ冬休みになる時期。今、部屋の掃除をふたりでしている。そして出会った時からの思い出話をしていた。
「実は莉久くんと初めて出会った時ね……、やっぱり言うのやめた」
「何? すごく気になる」
俺は床磨きをしていた手を止め、窓を拭いている遥斗を見た。遥斗も手を止め、こっちを見る。
「怒らないで聞いてね?」
「遥斗に怒ったことないし、怒らないし……」
「莉久くんのこと、すごく怖い人って思ってたんだ」
そう思われていたのも納得できる。当時は気を遣う必要がないと思っていて、本当に無愛想だったから。
「あの時は、怖がらせてごめんな」
「いや、全然謝ることじゃないよ!」
「……遥斗は、その時から可愛かったよな」
「えっ? 僕、そんなふうに思われてたの?」
遥斗の目がぱっと大きく開いた。
「うん、思ってた」
「……そうだったんだ。僕はもしかしたら嫌われているのかな?って、その時に思ってた」
「いや、そもそも初対面で嫌いとか、意味わからないし」
「嫌われていなくて、よかった!」
窓の上の方を拭くために遥斗は、微笑みながら白いテーブルを少しずらし、そこに椅子を置いた。窓の上の方を拭こうと更に背伸びをする。するとふらふらして落ちそうになった。
「遥斗、大丈夫か?」
「……ううん、だいじょばない。ちょっと怖いかな」
「じゃあ、俺そこやるわ」
「ありがとう」
最近、遥斗が本音で話をしてくれている感じがして、嬉しい――。
俺は両手を差し出すと、遥斗は俺の両手を握りながら、ゆっくりと椅子から降りた。そして手を握ったまま「でもね、莉久くんと関わっていくうちに、莉久くんはすごく優しくて、怖くないって知ったよ!」と微笑んだ。
「優しいなんて言われたことがなかったから、なんか照れるな」
多分自分が優しくなれるのは、遥斗の前でだけだ。
いつも怖そうとか、そんなことしか言われないから、なんだろ、全身がムズムズしてくる。
「莉久くん、優しい!」
遥斗は、くふふと声を出して笑った。
最近は自然な笑顔も見せてくれるようになった。
その笑顔をずっと見ていたいし、本音ももっとずっと聞かせて欲しい。でももうすぐ冬休みだ。