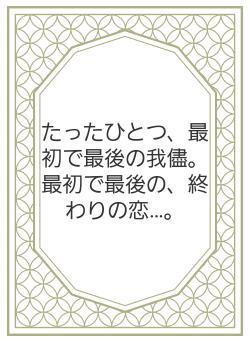そんなことを思って、制服の胸の辺りに手を当てて小さく溜息を吐いていると、ピロリンと鞄の中のスマホが控えめに鳴った。
「あ。もう会議終わったのかな?」
そう呟くと、私は教室を出て光樹くんが此方に迎えに来る前に、彼のいる生徒会室へと向かう。
こんこん
少し小さなノック。
もし、誰かいたら光樹くんが嫌がるかもしれないから、と何時も緊張してしまう、瞬間。
「光樹くん…いる?」
「…葉子?いいよ、入っておいで?」
そう穏やかな声で言われて、かちゃりとドアを開けると、会議後の生徒会室にはもう光樹くん以外の人はおらず、私を見ると光樹くんはにっこりと微笑んで、
「葉子、迎えに来こうと思ってたのに、わざわざ来てくれたの?ありがとう」
「ううん。私こそ…あの…もう大丈夫?邪魔してない?」
「ん?あぁ、もう平気だよ。てか、葉子が折角迎えに来てくれたのに、帰らないとかないから」
くすくすと微笑んだまま、ブレザーの上を羽織って、今まで緩めていたのかネクタイを縛り直す。
そんな彼が、とても格好良くて、また一つドキドキが増してしてしまう。
「ん?どうしたの?葉子?」
「う、ううん!なんでもないよ?」
かぁーっと赤くなるのを抑えようとして、顔を逸らそうとすると、何時の間にか傍に近付いていた光樹くんに、頬をすりっと撫でられそのくすぐったさに首をすくめると、おでこにちゅっとキスをされる。
「もしかして、今ので惚れ直しちゃった?」
「…え、あの…ちがくて…これは…」
と、私がわたわたしていると、光樹くんは楽しげに此方の方に距離を詰めて来て…。
「じゃあ、さ。このネクタイ、葉子が付けてくれる?」
なんて、とんでもないことを言って来た。
確かに、滅茶苦茶格好いいって思ったし、ときめいたし、光樹くんの言う通り惚れ直したけど!
男の子慣れを全くしていない私には、そんなこと出来るはずなくて…。
思わず、ぽかぽかと光樹くんのブレザーの胸元を叩いた。
「み、光樹くん!」
「葉子、かーわいい」
そう、言って破顔する光樹くんに、それ以上何も言えなくなって、私は下を向く。
きゅうんとしてしまう胸の鼓動の正体は、一体なんなんだろう。
「光樹くんてば、私のことかいかぶり過ぎだよ?」
「なんで?葉子が可愛いことは揺るがないよ?たとえこの世界がひっくり返ったとしても、ね」
一生懸命、きゅうきゅうとしてしまう胸の音を落ち着かせようと、努力するもそれは光樹くんの前では叶わない。
「光樹くんは、もっともっと格好いいよ?」
「そう?俺こんなだから、モテたことないけどね。でも、葉子が格好いいって言ってくれるんだったら、それだけでもういいや」
にっこり
そんな顔をして言われたら、開いた口が塞がらなくなる。
…嘘でしょう?
だって、王子様だよ?
毎日のように告白されてるんだよ?
手紙だって、プレゼントだって…。
勿論、それらを受け取った所をみたこともないし、目の前で繰り広げられる女子との会話は、滅茶苦茶素っ気ないものばかりだけれど。
そこが氷の王子様って言われる所以なんだろうけども…。
ぱちぱちと瞬きを数回繰り返すと、光樹くんは楽しそうに、口唇へとちゅっとキスをされる。
「っ!」
「いや、だった?」
「そ、そんなことない!」
「ありがと」
まだ、放課後の生徒会室、さっきもそうだけど。
生徒会室から出ていない内に、もう何回キスされたことか…。
もしかして、光樹くんて…キス魔?
本当に氷の王子様なの?手慣れてるから…とかじゃなく?
でも、ぎゅーっと抱き締められると、その心地よさに抱いている疑問はすぐに溶けて消えてしまう。
「葉子、帰り寄り道しても大丈夫?」
「う、うん?」
「なーんで、疑問系?ほら、俺達新婚じゃん?放課後デートしようよ?」
「し!新婚?!」
「あはは!葉子、目が落っこちちゃうよ?」
なんていうことを言い出すんだと、目を大きく開いたら、また楽しげに笑い出す光樹くん。
そんなに眩しい笑顔で微笑まれたら、なんでも許してしまいそういなる…。
でも、本当になんで?
なんで私のことを選んでくれたの?
私は告白されて、その真剣さに根負けして、お付き合いをし出して一ヶ月…未だに光樹くんの気持ちが、というか光樹くんの本心が分からない。
人を好きになることに理由なんていらないのかもしれないけれど…それでも…いくらなんでもこんな平々凡々な私に光樹くんは目をつけたんだろう?
隣に私なんかがいて、光樹くんは恥ずかしくないのかなぁ…?
そんなことを思うと、また、つきん、と胸の真ん中が痛くなった。
「あ。もう会議終わったのかな?」
そう呟くと、私は教室を出て光樹くんが此方に迎えに来る前に、彼のいる生徒会室へと向かう。
こんこん
少し小さなノック。
もし、誰かいたら光樹くんが嫌がるかもしれないから、と何時も緊張してしまう、瞬間。
「光樹くん…いる?」
「…葉子?いいよ、入っておいで?」
そう穏やかな声で言われて、かちゃりとドアを開けると、会議後の生徒会室にはもう光樹くん以外の人はおらず、私を見ると光樹くんはにっこりと微笑んで、
「葉子、迎えに来こうと思ってたのに、わざわざ来てくれたの?ありがとう」
「ううん。私こそ…あの…もう大丈夫?邪魔してない?」
「ん?あぁ、もう平気だよ。てか、葉子が折角迎えに来てくれたのに、帰らないとかないから」
くすくすと微笑んだまま、ブレザーの上を羽織って、今まで緩めていたのかネクタイを縛り直す。
そんな彼が、とても格好良くて、また一つドキドキが増してしてしまう。
「ん?どうしたの?葉子?」
「う、ううん!なんでもないよ?」
かぁーっと赤くなるのを抑えようとして、顔を逸らそうとすると、何時の間にか傍に近付いていた光樹くんに、頬をすりっと撫でられそのくすぐったさに首をすくめると、おでこにちゅっとキスをされる。
「もしかして、今ので惚れ直しちゃった?」
「…え、あの…ちがくて…これは…」
と、私がわたわたしていると、光樹くんは楽しげに此方の方に距離を詰めて来て…。
「じゃあ、さ。このネクタイ、葉子が付けてくれる?」
なんて、とんでもないことを言って来た。
確かに、滅茶苦茶格好いいって思ったし、ときめいたし、光樹くんの言う通り惚れ直したけど!
男の子慣れを全くしていない私には、そんなこと出来るはずなくて…。
思わず、ぽかぽかと光樹くんのブレザーの胸元を叩いた。
「み、光樹くん!」
「葉子、かーわいい」
そう、言って破顔する光樹くんに、それ以上何も言えなくなって、私は下を向く。
きゅうんとしてしまう胸の鼓動の正体は、一体なんなんだろう。
「光樹くんてば、私のことかいかぶり過ぎだよ?」
「なんで?葉子が可愛いことは揺るがないよ?たとえこの世界がひっくり返ったとしても、ね」
一生懸命、きゅうきゅうとしてしまう胸の音を落ち着かせようと、努力するもそれは光樹くんの前では叶わない。
「光樹くんは、もっともっと格好いいよ?」
「そう?俺こんなだから、モテたことないけどね。でも、葉子が格好いいって言ってくれるんだったら、それだけでもういいや」
にっこり
そんな顔をして言われたら、開いた口が塞がらなくなる。
…嘘でしょう?
だって、王子様だよ?
毎日のように告白されてるんだよ?
手紙だって、プレゼントだって…。
勿論、それらを受け取った所をみたこともないし、目の前で繰り広げられる女子との会話は、滅茶苦茶素っ気ないものばかりだけれど。
そこが氷の王子様って言われる所以なんだろうけども…。
ぱちぱちと瞬きを数回繰り返すと、光樹くんは楽しそうに、口唇へとちゅっとキスをされる。
「っ!」
「いや、だった?」
「そ、そんなことない!」
「ありがと」
まだ、放課後の生徒会室、さっきもそうだけど。
生徒会室から出ていない内に、もう何回キスされたことか…。
もしかして、光樹くんて…キス魔?
本当に氷の王子様なの?手慣れてるから…とかじゃなく?
でも、ぎゅーっと抱き締められると、その心地よさに抱いている疑問はすぐに溶けて消えてしまう。
「葉子、帰り寄り道しても大丈夫?」
「う、うん?」
「なーんで、疑問系?ほら、俺達新婚じゃん?放課後デートしようよ?」
「し!新婚?!」
「あはは!葉子、目が落っこちちゃうよ?」
なんていうことを言い出すんだと、目を大きく開いたら、また楽しげに笑い出す光樹くん。
そんなに眩しい笑顔で微笑まれたら、なんでも許してしまいそういなる…。
でも、本当になんで?
なんで私のことを選んでくれたの?
私は告白されて、その真剣さに根負けして、お付き合いをし出して一ヶ月…未だに光樹くんの気持ちが、というか光樹くんの本心が分からない。
人を好きになることに理由なんていらないのかもしれないけれど…それでも…いくらなんでもこんな平々凡々な私に光樹くんは目をつけたんだろう?
隣に私なんかがいて、光樹くんは恥ずかしくないのかなぁ…?
そんなことを思うと、また、つきん、と胸の真ん中が痛くなった。