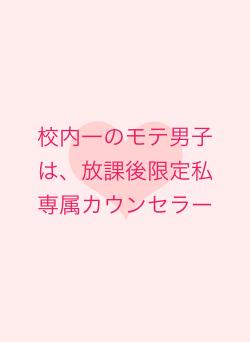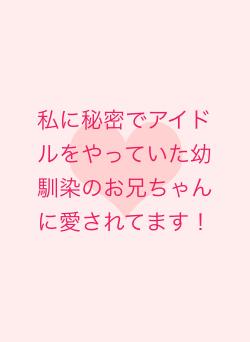しかし、しばらくして当然のように口を開いた。
「体が勝手に動いていた。それとも、君があのままグラスを投げられるのを黙って見ていれば良かったとでもいうのか?」
私の手を握っているクラヴィスの手にさらに力が入ったのが分かった。
「クラヴィス、痛いで……」
述べようとした言葉は、クラヴィスの表情を見た瞬間に止まってしまった。
クラヴィスが握っている私の手を見つめている。
「……あまり無茶はするな」
そうクラヴィスが呟いたように聞こえた。
「体が勝手に動いていた。それとも、君があのままグラスを投げられるのを黙って見ていれば良かったとでもいうのか?」
私の手を握っているクラヴィスの手にさらに力が入ったのが分かった。
「クラヴィス、痛いで……」
述べようとした言葉は、クラヴィスの表情を見た瞬間に止まってしまった。
クラヴィスが握っている私の手を見つめている。
「……あまり無茶はするな」
そうクラヴィスが呟いたように聞こえた。