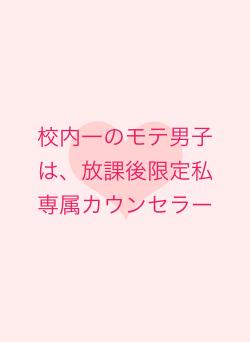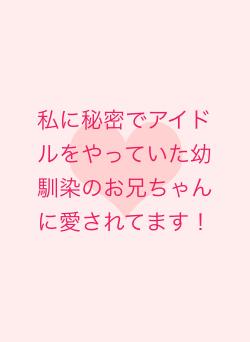「お騒がせしましたわ。この度はご婚約おめでとうございます」
その様子を見て、先ほど私に話しかけた貴族は逆上した。
そして、私に空になったワインのグラスを投げつけた。
「舐めやがって!」
私はギュッと目を瞑ることしか出来なかった。
顔を守る仕草すら取る余裕がなかった。
ガシャン。
何故か痛みを感じない。
私がそっと目を開けると、目の前にクラヴィスが立っている。
グラスを使用人が持っていたトレイで弾き飛ばしたようだった。
そして、クラヴィスが私の方を向いた。
「助けて欲しい時は、助けてと声を上げないと駄目だ」
クラヴィスが、私の顔に滴るワインをハンカチで優しく拭いている。
その仕草に私はひどく安堵してしまった。
その様子を見て、先ほど私に話しかけた貴族は逆上した。
そして、私に空になったワインのグラスを投げつけた。
「舐めやがって!」
私はギュッと目を瞑ることしか出来なかった。
顔を守る仕草すら取る余裕がなかった。
ガシャン。
何故か痛みを感じない。
私がそっと目を開けると、目の前にクラヴィスが立っている。
グラスを使用人が持っていたトレイで弾き飛ばしたようだった。
そして、クラヴィスが私の方を向いた。
「助けて欲しい時は、助けてと声を上げないと駄目だ」
クラヴィスが、私の顔に滴るワインをハンカチで優しく拭いている。
その仕草に私はひどく安堵してしまった。