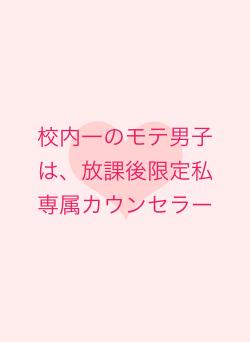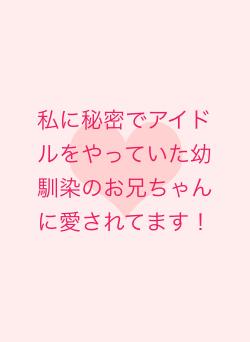私は立ち上がって、前を向いた。
「やめなさい。私はこの国の第一王女。無礼な真似は控えなさい」
顔を上げて、クロルに「大丈夫」と視線を送る。
私の言葉に周りの者たちは「どの口がっ!」と苛立っている。
それでも、ワインをかける手と髪を引っ張る手を止めることが出来た。
私は近くの使用人に声をかけた。
「ねぇ、貴方。ここを掃除してくれないかしら?」
私はワインで濡れた床を指差した。
使用人は私に呼ばれてビクッと肩を震わせたが、すぐに床を拭き始める。
どれだけ床を拭いても、濡れている私がこの場にいては会場が片付かない。
ドレスの替えはないし、私に貸してくれる者もいないだろう。
私はこの場から……この会場から去らなければいけない。
それでも、このまま去っては逃げるだけのように見えてしまう。
慌てているのに、頭の熱だけが冷めているように感じる。
「やめなさい。私はこの国の第一王女。無礼な真似は控えなさい」
顔を上げて、クロルに「大丈夫」と視線を送る。
私の言葉に周りの者たちは「どの口がっ!」と苛立っている。
それでも、ワインをかける手と髪を引っ張る手を止めることが出来た。
私は近くの使用人に声をかけた。
「ねぇ、貴方。ここを掃除してくれないかしら?」
私はワインで濡れた床を指差した。
使用人は私に呼ばれてビクッと肩を震わせたが、すぐに床を拭き始める。
どれだけ床を拭いても、濡れている私がこの場にいては会場が片付かない。
ドレスの替えはないし、私に貸してくれる者もいないだろう。
私はこの場から……この会場から去らなければいけない。
それでも、このまま去っては逃げるだけのように見えてしまう。
慌てているのに、頭の熱だけが冷めているように感じる。