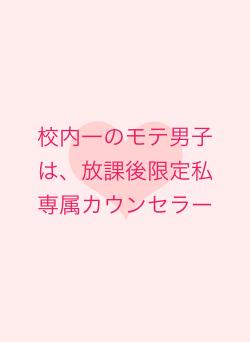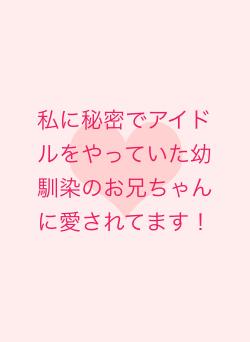しかし、クラヴィスは私とクロルの不安をよそに、翌日にはもう私のクラスを訪れた。
そして、私のことをこう呼ぶのだ。
「【マリーナ王女殿下】、少しよろしいですか?」
クラヴィスが私に話しかけたことに周りの者は大層驚いていた。
「クラヴィス様がどうしてあの悪女に……!」
「クロル様のように脅されているのではなくて!」
「絶対にそうだわ。隣国の公爵家まで無下に扱うなど、あり得ない」
噂というものは、きっとこうやって尾ひれがついていくのだと思った。
そして、私のことをこう呼ぶのだ。
「【マリーナ王女殿下】、少しよろしいですか?」
クラヴィスが私に話しかけたことに周りの者は大層驚いていた。
「クラヴィス様がどうしてあの悪女に……!」
「クロル様のように脅されているのではなくて!」
「絶対にそうだわ。隣国の公爵家まで無下に扱うなど、あり得ない」
噂というものは、きっとこうやって尾ひれがついていくのだと思った。