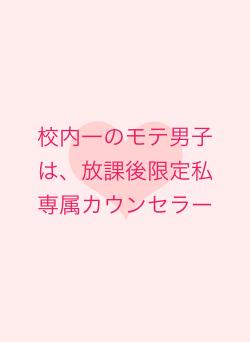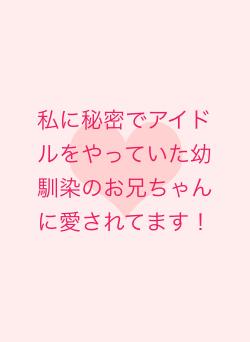クラヴィス様の問いに私はすぐに答えることが出来なかった。
クラヴィス様は私が思考を巡らせている間もずっと私と目を合わせて、私の反応を見極めているようだった。
そう、きっと私は見定められている。
「先ほど彼女たちに述べたことと同じですわ。私が国一番の悪女かどうかはクラヴィス様が見極めて下さいませ」
「私から見れば、貴方は噂とは違う人物に見える。しかし、今の出来事だけで判断するのは早計すぎるだろう」
クラヴィス様が私にあと二歩ほどでぶつかる距離まで近づく。
「王女殿下……いや、マリーナと呼んでも良いだろうか」
ここは学園であり、皆平等に学べる場である。
学園内では貴族間の身分制度を考えず、共に学びを深めることが目標とされている。
しかし、実際この国の王族に気軽に接すること出来る者はいないだろう。
ましてや、隣国の公爵子息が王女を呼び捨てにするなど考えられない。
それでも私の場合は国一番の大悪女であり、敬称なく呼ばれること、それこそ「悪女」と呼ばれ陰口を言われることも多かった。
先ほどからクラヴィス様は言葉遣いを含め、わざと私と距離を縮めようとしているように感じる。
しかし、それでいて敬意を全く持っていない様子でもない。
クラヴィス様は私が思考を巡らせている間もずっと私と目を合わせて、私の反応を見極めているようだった。
そう、きっと私は見定められている。
「先ほど彼女たちに述べたことと同じですわ。私が国一番の悪女かどうかはクラヴィス様が見極めて下さいませ」
「私から見れば、貴方は噂とは違う人物に見える。しかし、今の出来事だけで判断するのは早計すぎるだろう」
クラヴィス様が私にあと二歩ほどでぶつかる距離まで近づく。
「王女殿下……いや、マリーナと呼んでも良いだろうか」
ここは学園であり、皆平等に学べる場である。
学園内では貴族間の身分制度を考えず、共に学びを深めることが目標とされている。
しかし、実際この国の王族に気軽に接すること出来る者はいないだろう。
ましてや、隣国の公爵子息が王女を呼び捨てにするなど考えられない。
それでも私の場合は国一番の大悪女であり、敬称なく呼ばれること、それこそ「悪女」と呼ばれ陰口を言われることも多かった。
先ほどからクラヴィス様は言葉遣いを含め、わざと私と距離を縮めようとしているように感じる。
しかし、それでいて敬意を全く持っていない様子でもない。