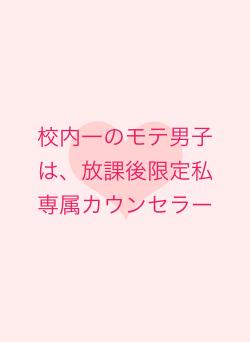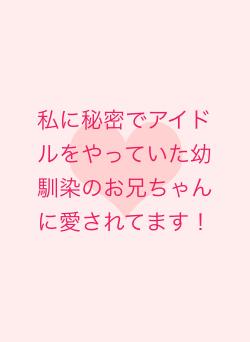従者が馬車の扉を開ける。
「リーリル様、到着しました」
私が馬車を降りると、従者は深く頭を下げた。
この者も事情を知っている。
「私はこのまま屋敷に戻ります。お嬢様が沢山の人たちに好かれて帰ってくるまで、しっかりと屋敷を皆で守ります。それでももし辛くなったら、いつでも……」
その従者はわざと「帰って来てください」と最後まで言わなかった。
私が外に出た勇気を汲んでくれた。
それでも、最後まで「私の居場所があると伝えてくれた」のだ。
「本当にありがとう。折角だから、外での生活を楽しんでくるわね」
だからニコッと笑って、そう答えるのが一番の優しさだと思った。
馬車がいなくなり、後は学園に入るだけ。
「ねぇ、リーリル。クロル。私ね、自信があるの。優しい人たちに囲まれている自信が。だから、毎日笑顔で過ごしているわ。幸せだもの」
「だからね、私の笑顔を見せびらかすつもりで外に出る。私はこんなにも幸せですって。最高に魅力的な人たちに囲まれているのよって」
「何も心配しないでね」
そう言った私はどんな表情をしていたのだろう。
でも、もう決意は決まった。
その決意を持ち、私は学園に足を踏み入れた。
「リーリル様、到着しました」
私が馬車を降りると、従者は深く頭を下げた。
この者も事情を知っている。
「私はこのまま屋敷に戻ります。お嬢様が沢山の人たちに好かれて帰ってくるまで、しっかりと屋敷を皆で守ります。それでももし辛くなったら、いつでも……」
その従者はわざと「帰って来てください」と最後まで言わなかった。
私が外に出た勇気を汲んでくれた。
それでも、最後まで「私の居場所があると伝えてくれた」のだ。
「本当にありがとう。折角だから、外での生活を楽しんでくるわね」
だからニコッと笑って、そう答えるのが一番の優しさだと思った。
馬車がいなくなり、後は学園に入るだけ。
「ねぇ、リーリル。クロル。私ね、自信があるの。優しい人たちに囲まれている自信が。だから、毎日笑顔で過ごしているわ。幸せだもの」
「だからね、私の笑顔を見せびらかすつもりで外に出る。私はこんなにも幸せですって。最高に魅力的な人たちに囲まれているのよって」
「何も心配しないでね」
そう言った私はどんな表情をしていたのだろう。
でも、もう決意は決まった。
その決意を持ち、私は学園に足を踏み入れた。