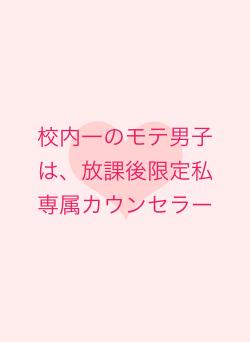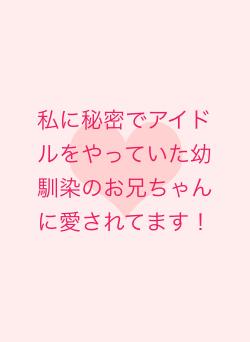「そろそろ私だって屋敷を出ないといけないわ」
「お嬢様!お嬢様が思うより屋敷の外は……!」
「厳しいのでしょう?」
私はリーリルの言葉を遮り、そう述べた。
「お嬢様……」
「ねぇ、リーリル。私だって毎日想像していたの。外に出たらどんな扱いを受けるだろうって。だって私は国一番の大悪女ですもの」
「本当は知っていたの。両親が政策の失敗を全て私のせいにしたことにより、屋敷まできて私を攻撃しようとする者も多かったこと。そんな者たちから貴方たちが必死に私を守っていてくれていたことも」
「でも、私が守られるだけなんて性に合わないことをリーリルもよく知っているでしょう?」
私はリーリルに心配をかけないように、わざと自信満々にニコッと笑った。
「お嬢様!お嬢様が思うより屋敷の外は……!」
「厳しいのでしょう?」
私はリーリルの言葉を遮り、そう述べた。
「お嬢様……」
「ねぇ、リーリル。私だって毎日想像していたの。外に出たらどんな扱いを受けるだろうって。だって私は国一番の大悪女ですもの」
「本当は知っていたの。両親が政策の失敗を全て私のせいにしたことにより、屋敷まできて私を攻撃しようとする者も多かったこと。そんな者たちから貴方たちが必死に私を守っていてくれていたことも」
「でも、私が守られるだけなんて性に合わないことをリーリルもよく知っているでしょう?」
私はリーリルに心配をかけないように、わざと自信満々にニコッと笑った。