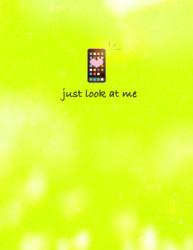◇
「……それはそうと。
私、君の名前も知らないわ」
「え、うそでしょ。
さっきのセリフ『それはそう』で片付けられんの?
普通に恥ずいやん」
「変よね、1年も通っておいて」
「ほんで聞いてくれんし。
……瞬ですよ。俺の名前」
「素敵。名前まで儚いのね」
「ちなみに俺は知ってますけどね、麗子さん」
「名乗ったかしら」
「昔、1回だけね。
ほら。元彼との会話の再現してた時に。
……あんま思い出したないけど」
「知ってたなら、呼んでくれても良かったのに」
「だってなんか悔しいでしょ。
麗子さんは俺の名前知りもせんのに」
「そういうものなのね」
「というか、いつまでそのエセ関東人やるんすか。
さっきの『ちゃうよ』って……
関西べ……母国語に戻すってことやないんですか?」
「今の自分も、案外気に入ってるの。
穏やかでいられるし」
「そういうもんすか」
「ええ」
「……………………今日はもう閉めよかな、店」
「あらそう。
じゃあ私、おいとまするわ」
「えっ、うそやん。
だからこの後どっか……って、ほんまに帰りそうやん」
「うん」
「さすがに、もうちょい一緒におりたいんですけど……」
「勢いで一夜を共にできるほど安くないのよ、私」
「い、一夜……って!
いやいや、そういうことやなくて」
「はい、これ。お会計ね」
「いや、いらんっすよ。だって……」
「だめよ。当然の対価なんだから」
「ちょっ、まって。じゃあせめて連絡先は?」
「もう。仕方ないわね。手だして」
「え?ハイ……って、こしょば!」
「じゃ、またね」
「ええ…………。ほんまに帰ってまうし。
てか、今どき人の手に番号書く人おる?
……洗われへんやん」
◇