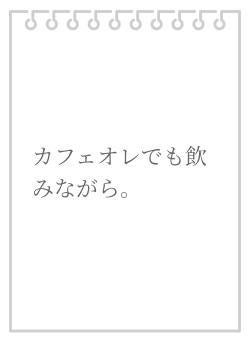帰りのホームルームの後、恋の席に、鞄を背負った理央がやってきた。
「恋!。調理実習の事メモした?」
「理央。もちろんしたよ。家のカレンダーにも書いてある。」
「みんなで料理するのは楽しいけど、ちょっと面倒くさいよね。上野くん、恋に料理作ったりする?」
ロッカーの前に居た宗介に、理央が聞いた。
宗介は学校に置いておく教材を整理していた所だった。
「時々。」
宗介が言った。
「チャーハンとかそんなんだけど。親が出掛けてる時は自分で作るし、恋にも食べさせるよ。そういや、この間も恋にチャーハン作ったな。」
「チャーハンなんて。」
斜め前の席から、䄭風が恋を振り返って言った。
「新田さん、そんな雑な物食べさせられてるの?。かわいそうに。」
「うざった。僕が作るチャーハンの何がいけないって言うんだよ。」
「どうせ上野は、適当な食材を適当に作ってるだけに違いない。その点僕が作るグラタンとか濃厚なカルボナーラとかは。是非一度新田さんに食べさせたいね。」
「樋山くん、料理得意なの?」
「うん。何でも作れるよ。」
䄭風が笑った。
「新田さん、うちに来て。何でも好きな物言ってよ。作ってあげるから。」
「言っとくけど。恋。」
宗介が割って入った。
「樋山んちなんか行ったらただじゃおかないぞ。それは浮気だ。僕を裏切ってる。」
「報道によれば、新田さんは僕の彼女なのに、上野にふらついてる。」
しれっとした顔で䄭風が言った。
「新聞部もやりようによっちゃ便利だね。ちょっと馬鹿らしいけど。そういや、」
䄭風がなんでもないことの様に続けた。
「放課後僕にさる女子たちの一団が来て、新田さんを辞めて自分にしませんかって言ってきた。」
「えっ凄い」
「樋山くんそれって告白じゃ、」
「そうらしいよ。」
䄭風は試す様にじっと恋の顔を見やった。
「どんな子だった?」
恋が聞くと䄭風はくすくす笑いながら言った。
「なんか結構可愛い見た目の子だったよ。僕にその気がないのに、無駄に自信あり気なのと照れてるのを除けば、普通だったかな。」
「へえ……」
「ふーんそれは良かったね。じゃあ早くそっちにしろよ、樋山。」
宗介が言ったが、䄭風は無視した。
「確かに顔は可愛かったけど、それだけだ。だから、新田さん。」
䄭風が恋を覗き込んだ。
「僕が新田さんを追いかけてるのも今のうちだよ。早くしないと、君の手を滑り落ちて、他の子の所へ行っちゃうから。警戒してよ。そうならないようにって思ってよ。早く上野と別れて。ね。」
恋はなんと答えていいか分からず、うーんと唸った。