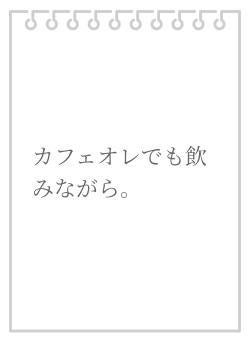並んだ大体の店の中を見回ってから、宗介と恋は2階のフードコートに入った。
フードコートのアイス屋では、フルーツシャーベットのフェアをやっていて、店には可愛らしいフルーツの模様の飾り付けがしてあった。
宗介と恋は、シャーベット買ってから、ガラス張りの窓際に席を取った。
「お前が狐だっていうことで、引け目を感じてたら言ってやる。」
シャーベットを食べながら宗介が言った。
「動物になれるのなんかお前くらいだ。僕はむしろ良いと思ってる。貴重だしね。お前の特別なところ。」
宗介は話を変えた。
「恋、この間学校で貰った資料に、部活動のパンフレットがあったけど、お前はもうどの部活にも入らなくて良いんだよな?」
「うん。」
「部活は時間を使うだけ。お前はこれから家で勉強しなきゃならないんだから、余計な事考えない様にね。パンフレットもお愛想程度に見て、捨てた方が良いよ。どうせ入らないんだし。」
「うん、分かってるよ」
宗介は窓から外の景色を見た。
2階のこのガラス窓からは駅と近くの街並みが見える。
夕方になりかけた空は、不思議な色合いをしていた。
「お前がこれからひとつも変わらなくても、僕はお前を好きで居てあげる」
空を眺めながら宗介が言った。
「お前がこれからどれだけ失敗しても、僕がそれを取り戻してあげるよ。」
宗介の決意は固かった。
宗介は、この狐の女の子を、一生守ってやろうと決めていた。
そのために大人になって、どんなことでもしようと決心していた。
ガラス張りの壁一面に、夕焼けが映って、雲の上に居るみたいだ。
宗介はシャーベットを置いた。
「約束。これから先もお前を困らせるものがあったら、全部僕がなくしてやるよ。」
言ってから、宗介はセンチメンタルな気分に気づいた。
「その代わり。」
宗介が口を開いた。
「もしもお前が僕を捨てたら、お前の行く所全部にこいつは狐だってバラして、お前の事は絶対に狐汁にして食うから、後悔することになるよ。嫌がること全部して泣かすから。良い?」
ニコッと宗介が笑った。
底知れないどす黒い渦巻く愛情に、恋は気づかない。
「……」
「言っておくけど、僕誰にもお前のこと譲る気ないからな。そ・れ・とそれってどういう意味か分かる?。」
「うん、」
恋は困った顔で言った。
「お前が狐で良かった。秘密は弱みになるし。」
宗介は、ふと恋の腕を取ると、テーブルの上で顔を寄せて触れるだけのキスをした。
「今日は楽しかったよ、恋。」
宗介が笑った。
恋はきょとんとした顔で宗介を見返した。
「……アイスを食べた後だと、アイスの味のキスをしたっていう事になるのかなあ。」
恋が言った。
宗介はそっけなかった。
「さあ。なるのかもね。でも、そういうの、ちょっとしつこい。」
それからついでのように、
「帰りチョコレート買っていこうか。お前と田山がお菓子の話したせいで、なんか食べたくなった。」
と言った。