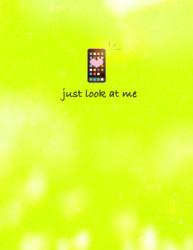◆
「いらっしゃいませ………
って、今日もアナタですか」
「こんばんは。
今日も今日とて寂しい店ね」
「週末は賑わうんですけどねぇ。
アナタがこーへんだけで。
……いつものですか?」
「そう。あの、味のない"ギムレット"」
「そない文句言うなら、
別のんにしはったらどうですか」
「褒めてるのよ。あの丁度良い薄さ。
神がかってるとしか思えない」
「……今度ベース抜いてみたろかな。
はい、どーぞ」
「知ってる?今日でちょうど1年」
「え、うそやん。もうそんな経ちますか」
「記念に、私がこのbarにたどり着いた話でもしようか」
「いや、十分聞いたんでもうええです。
3年付きおうた彼氏に捨てられて、
この街に逃げてきたなんて話」
「そうそう。
でも、どうしたって虚しくて。
酔い潰れるためにドアを開けたのに。
この儚い薄味が、それすらも許してくれなかったの」
「擦りすぎて、なんの記念にもならんな」
「ここに来ると、いつも君が居たわ」
「だから。俺しかおらへんのですって。
ワンオペ店長なんでね。……雇われやけど」
「ほんと、いつまでも洗練されないのね。
普通は『マスター』って言うんじゃないの?」
「俺に似合わんでしょ。そんな小洒落た肩書き」
「で?恋人とはどう?」
「恋人ちゃうって言うてるやないですか。
………まだ」
「諦め悪いね、君も」
「それはアナタでしょ。
いま飲んでるソレ、もはや鎖やん」
「痛いなあ。もうちょっと気遣ったりできない?」
「そんなん求めてないくせに」
「嘘。
本当はわかってるよ。
このグラスに入ってる優しさ」
「………さいですか。
他のん頼む気になったら言うてください。
おすすめは"ブルー・バード"」
「もちろん。そんな日が来たらね」
◇