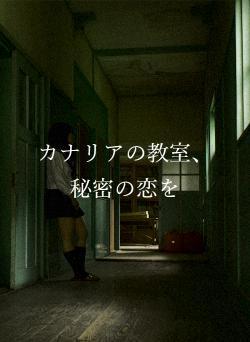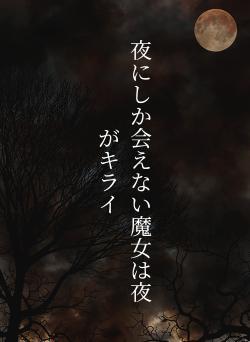まだ何もしてないのに緊張が走る。
強引でめちゃくちゃなのに、真剣な瞳をしていたから。
それほど大切なことなんだって。
でも、だからこそ私には…
「お断りします」
頭を下げる、深々と。
そんなこと私にできるわけないもん。
「……。」
頭を下げて数秒、何も返事がなくて少し不安になる。
え…、いつまでこの体制でいればいいの?
でも別に悪いことしてるわけじゃないもんね、許してもらうとかそーゆうんじゃないから…
顔を上げる、もうこれで話は終わりだと思って。
「俺はお前以外考えていない」
真っ直ぐ私を見てた。息をするのにも緊張するぐらい、刺すような瞳で。
「そ…っ、そんなこと言われても無理です!そんなのやったことないし、やれる気もしないしっ」
「それはやってみなきゃわからないだろ」
「わかるから!もっとちゃんとして人に頼んで…っ」
あまりにぶれない瞳は私の方が負けそうになって、一瞬視線を逸らしかけちゃって息を飲んだ。
「どうして私なの?」
一寸の迷いもなく答えが返って来た。
「俺の理想にピッタリだったから」
そんなこと言われるのは初めてで、次の言葉が出て来なかった。
私の前に立ち上がる、机に手を付いて身を乗り出して手を伸ばした。
ドキドキと心臓が震え出して、何が起きるのかと思うとメガネを取られるように外された。視界が悪くなってつい目に力が入ってしまう。
「いい目だ」
「え?」
ぼやける視界でどんな表情をしてるのかわからないけど、たぶん笑ってた。
「俺に選ばれたんだから自信を持て」
そんなこと、言われても。
モデルなんてやったことないし、学祭とは言えランウェイを歩くなんて荷が重すぎる…そんなこと、私の人生に絶対ありえないことなんだから。
強引でめちゃくちゃなのに、真剣な瞳をしていたから。
それほど大切なことなんだって。
でも、だからこそ私には…
「お断りします」
頭を下げる、深々と。
そんなこと私にできるわけないもん。
「……。」
頭を下げて数秒、何も返事がなくて少し不安になる。
え…、いつまでこの体制でいればいいの?
でも別に悪いことしてるわけじゃないもんね、許してもらうとかそーゆうんじゃないから…
顔を上げる、もうこれで話は終わりだと思って。
「俺はお前以外考えていない」
真っ直ぐ私を見てた。息をするのにも緊張するぐらい、刺すような瞳で。
「そ…っ、そんなこと言われても無理です!そんなのやったことないし、やれる気もしないしっ」
「それはやってみなきゃわからないだろ」
「わかるから!もっとちゃんとして人に頼んで…っ」
あまりにぶれない瞳は私の方が負けそうになって、一瞬視線を逸らしかけちゃって息を飲んだ。
「どうして私なの?」
一寸の迷いもなく答えが返って来た。
「俺の理想にピッタリだったから」
そんなこと言われるのは初めてで、次の言葉が出て来なかった。
私の前に立ち上がる、机に手を付いて身を乗り出して手を伸ばした。
ドキドキと心臓が震え出して、何が起きるのかと思うとメガネを取られるように外された。視界が悪くなってつい目に力が入ってしまう。
「いい目だ」
「え?」
ぼやける視界でどんな表情をしてるのかわからないけど、たぶん笑ってた。
「俺に選ばれたんだから自信を持て」
そんなこと、言われても。
モデルなんてやったことないし、学祭とは言えランウェイを歩くなんて荷が重すぎる…そんなこと、私の人生に絶対ありえないことなんだから。