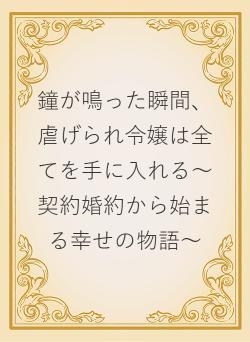リゼットが出て行った扉を見つること数秒。足音が聞こえなくなるまで待ってから、私は溜め息を吐いた。
「何であんな飛躍した考え方になったんだ。いや、私のせいか」
五歳でマニフィカ公爵家にやってきたリゼットは、幼くともまだ、伯爵令嬢らしい子どもだった。
それが変わったのは、いつのことだっただろう。
他に兄弟もいなかった私は、まるで妹ができたみたいに、リゼットの世話を焼いた。が、却ってリゼットに、負担をかけていたらしい。
私の婚約者にふさわしくあろうと、努力し始めたのだ。その点に関しては、嬉しくなかったわけじゃない。だが……。
「無理をし過ぎるんだ。何をするにも、リゼットは……」
両親がリゼットに用意した家庭教師の数は、私の比ではなかった。それだけ期待されているのだろう、とリゼットも思ったのかもしれない。
「何であんな飛躍した考え方になったんだ。いや、私のせいか」
五歳でマニフィカ公爵家にやってきたリゼットは、幼くともまだ、伯爵令嬢らしい子どもだった。
それが変わったのは、いつのことだっただろう。
他に兄弟もいなかった私は、まるで妹ができたみたいに、リゼットの世話を焼いた。が、却ってリゼットに、負担をかけていたらしい。
私の婚約者にふさわしくあろうと、努力し始めたのだ。その点に関しては、嬉しくなかったわけじゃない。だが……。
「無理をし過ぎるんだ。何をするにも、リゼットは……」
両親がリゼットに用意した家庭教師の数は、私の比ではなかった。それだけ期待されているのだろう、とリゼットも思ったのかもしれない。